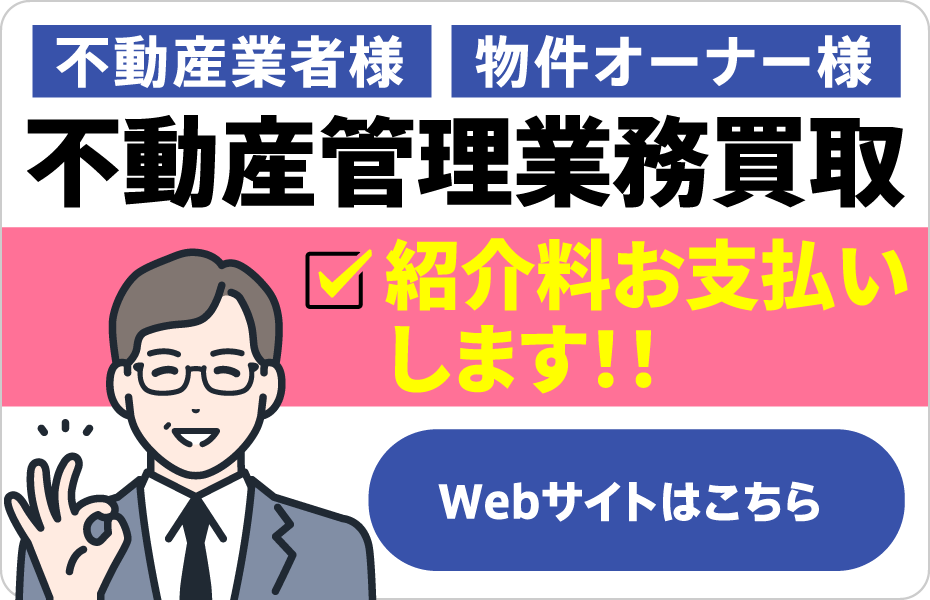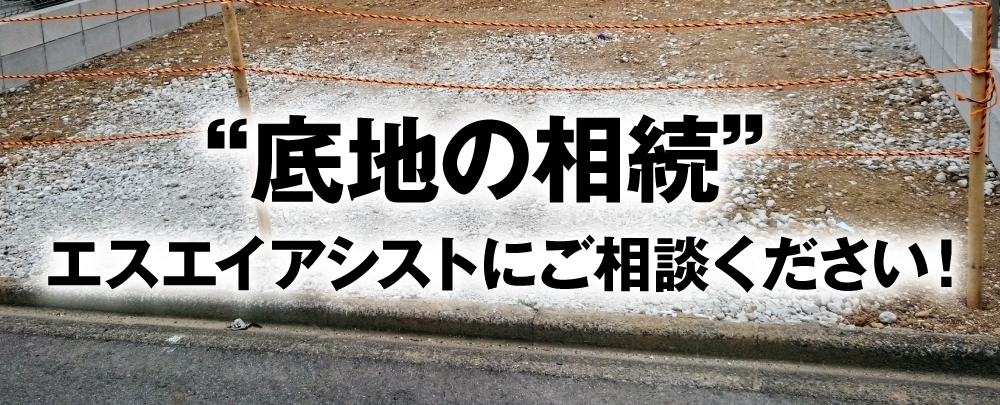
独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!今回は底地のメリット・デメリットや方法を解説します。
底地とは?
「底地」とは、簡単に言うと、誰かに貸している土地のことを「底地」と呼びます。これは地主の立場から見た呼び方で、「貸地(かしち)」という言い方をすることもあります。
「底地」は地代を受け取る側の土地であり、「借地権」はその土地を使う側の権利ということになります。なお、借地権が認められるのは、建物を建てることが目的の場合です。ここで注意したいのが、「底地」は完全な所有権ではないという点です。たとえば、土地と建物の両方を同じ人が持っている場合は、自由に使える「完全所有権」となります。しかし、底地の場合は、土地の所有権は底地人が持っていても、その土地の上にある建物や使用権は借地人が持っているため、「不完全所有権」と呼ばれます。
つまり、底地とは、土地の権利と使用権が分かれている状態なのです。土地所有者が自由に活用できないという制約があるため、不動産市場では一般的に扱いづらい物件と見なされる傾向があります。特に、借地人の権利が法律によって強く保護されていることから、地主である底地人の権利は制限されがちです。その結果、底地には収益性や流動性の面で課題が多く、積極的に取得しようとする人は限られています。
底地を所有するメリット
底地は土地の上に底地人の権限が及ばない借地権が設定されており、訳アリ不動産として扱われる傾向にありますが、維持した地代を受けられたり、相続税対策にもなり、得をする可能性があります。
①地代を受け取ることができる
底地を取得する場合、借地権を新たに設定するケースは少なく、ほとんどはすでに借地人が存在している土地の権利を引き継ぐ形になります。つまり、地代を支払ってくれる借地人がすでにいる状態で、土地の所有権だけが移るということです。地代という定期的な収入が見込めるため、安定したキャッシュフローを生む資産としての側面も持っています。
底地は一見すると制約の多い不動産に見えますが、視点を変えれば、すでに稼働している収益物件としての魅力もあるのです。
②管理の手間やリスクが少ない
底地を所有することは、管理面での負担が少ないという利点があります。底地人は、土地の所有権を持っているものの、実際の利用や管理は借地人が行います。借地人はその土地に建物を建てて使用しているため、建物の維持管理はもちろん、土地の使用に関する日常的な管理も借地人の責任となります。このため、底地人は物件の管理に直接関与する必要がなく、管理コストや手間がほとんどかからないというメリットがあります。例外として、借地人が土地を適切に利用できるようにするための最低限の修繕義務は底地人に課されるため、その分の費用は発生する可能性がありますが、底地は「所有しているが使っていない土地」でありながら、安定した収益を得つつ、管理負担が少ない資産として活用できる可能性があります。
③土地の広さによっては相続税対策人なる可能性がある
土地や建物などの不動産をはじめ、財産を相続する際には、避けて通れないのが「相続税」です。底地のような不動産では、条件を満たせば相続税の負担を軽くする制度があります。
それが「小規模宅地等の特例」と呼ばれるもので、相続後も借地人との契約が続いていて、かつ土地の面積が一定以下である場合に適用される制度で、相続税の評価額を大きく減らすことができる可能性があります。
底地を所有するデメリット
①土地を自由に売却できない
底地の場合、借地人によってすでに建物が建てられており、所有者はその建物を利用することも撤去することもできません。このような制限は、投資や活用の自由度を著しく低下させる要因となります。自由に使えない土地は市場での需要が限られ、流動性が低くなるため、底地の売却は一般的な更地や自用地と比べて困難です。このような背景から、底地の評価額は通常の土地よりも大幅に低く設定される傾向があります。
②税金がかかる
底地を所有する場合、通常の不動産と同様に、固定資産税や都市計画税といった継続的な税負担が発生します。これらは、土地の所有者である底地人が支払う義務を負うものであり、収益性が限定的な底地にとっては、コスト面での懸念材料となり得ます。特に、収益性が低い底地を相続するケースでは、評価額に対して税負担が相対的に重くなる可能性があるため、事前の資金計画や税務対策が重要です。このように、底地の所有には一定の税務リスクが伴うため、取得や相続の際には、収益性・保有コスト・税負担のバランスを慎重に見極めることが求められます。
③収益化できない場合がある
底地人の権利は借地人に比べて相対的に弱い立場にあることも少なくありません。特に都市部では、借地権割合が80%、底地割合が20%といったケースも見られ、資産価値の面でも借地権の方が優位に立つ状況が生じています。
そのことから底地人は地代の増額によって収益性を高める以外に手段が乏しいのが現状です。しかし、地代の改定には借地借家法に定められた条件を満たす必要があり、以下の3つの事由に該当する場合に限って増額請求が可能です
・地価の上昇などによる経済事情の変化
・周辺の賃料相場との乖離
・借地条件の変更による影響
これらの条件を満たしていることを立証するには、専門的な知識と資料が必要となり、実務上のハードルは高いことに加えて、借地権の法的保護が強いため、地代の増額交渉は現実的には困難を伴うケースが多いのが実情です。
底地を相続した場合にどうすればよいのか
底地を相続したものの、今後も所有し続ける意思がない場合は、専門の買取業者への相談をおすすめします。一般的な不動産仲介業者に依頼すると、買い手が見つかるまで時間がかかることが多く、売却までに長期間を要する可能性があります。一方で、底地の取り扱いに慣れた専門の買取業者であれば、迅速かつ柔軟に対応してくれるケースも多く、スムーズな売却が期待できます。不要な負担を避けるためにも、まずは専門の買取業者に相談してみることが賢明です。
まとめ
今回は底地のメリット・デメリットについて解説してきました。基本的には底地主側が不利なことも多く、収益化することは難しいため、専門の不動産買取業者への相談をお勧めします。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することができますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!