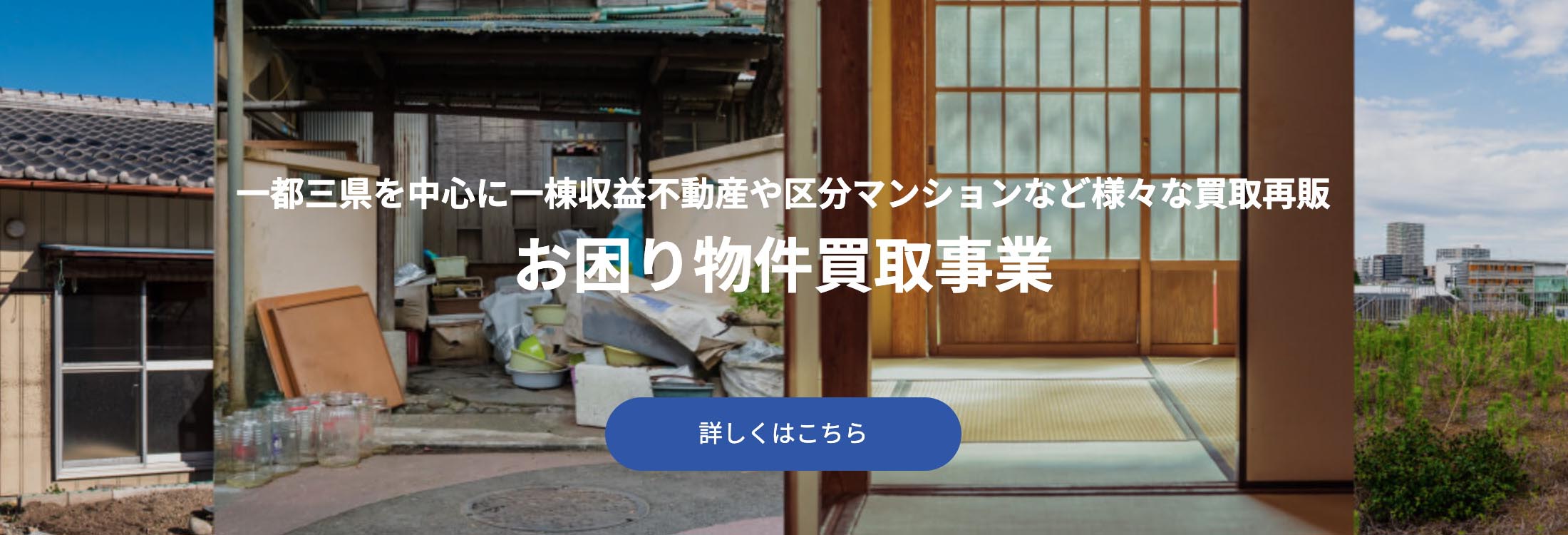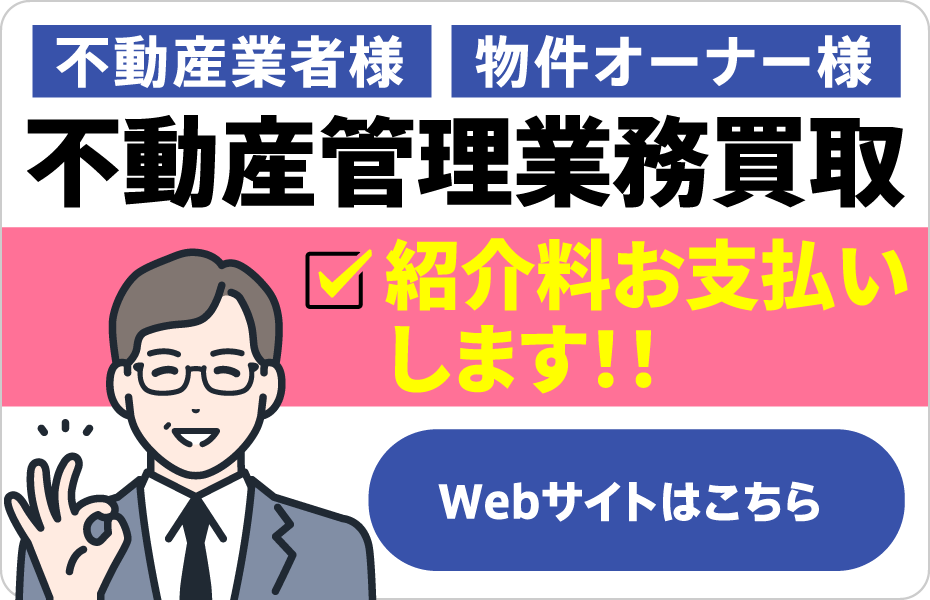独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第133回目は「修繕積立金不足で売れない理由」です。
「親から相続した古いマンションを売りたいが、なかなか買い手が付かない…。もしかして、修繕積立金不足が理由で売れないのでは?」と、不安を抱えていませんか?実は、国土交通省の調査でも全国の3〜4割のマンションに、計画に対して資金が足りていないというデータもあり、決して他人事ではありません。この問題を放置すれば、将来的な資産価値の下落だけではなく、いざ売却しようにも手放せないという事態を招きかねません!
今回の記事では、修繕積立金不足がなぜマンションの売却を妨げるのか、その具体的な理由とともに、2026年に施行が予定されている「区分所有法」改正がどのように影響する可能性があるのか解説します。読み終えれば、住民間の合意形成が難しい状況から抜け出すための、マンション売却法が見えてきます。ぜひ最後までお付き合いください。
「修繕積立金不足の問題とは?」その基礎を解説!

まず、マンションにおける「修繕積立金」とは何か、その役割と管理費との違いを確認します。
「修繕積立金」とは、かんたんに言えば「マンションの将来のための共同貯金」のことです。外壁、屋上、エレベーターといった共用部分は必ず劣化するため、これらを将来的に修繕するために所有者全員で毎月お金を積み立てます。
ちょっと似た言葉で「管理費」がありますが、これは日常清掃・共用電気代・管理員人件費など「日々の運営費」です。一方で、修繕積立金は「将来の大きな修繕のための原資」。性質と使途が異なります。
多くのマンションでは「長期修繕計画」という、今後おおむね25〜30年程度の修繕スケジュールと費用見込みを定めた計画を作成します。大規模修繕(外壁補修・防水改修・共用設備更新など)は、十数年に一度の高額出費になるため、計画に基づく積み立てが欠かせません。
国土交通省の「修繕積立金に関するガイドライン」では、平均的な水準の目安が示され、専有面積1㎡あたり月額200円台のレンジで、物件規模・設備仕様・劣化の進み方で必要額は上下するとしています。たとえば70㎡なら月額で概ね1.2万〜2万円台が一つの基準感です。
ただ、その基準も2回目・3回目の大規模修繕では1回目より単価が上がる傾向が見られます。「令和5年度マンション総合調査の結果について」によれば、築年が進むほど修繕項目は増え、配管やエレベーターなど「重い工事」が加わることが言われています。
この修繕積立金が不足すると起こり得る問題として、修繕の先送りによって外観・共用部の目に見える劣化、事故・漏水等のリスクの増加などがあります。そして将来の一時金徴収や急な積立月額の大幅値上げの必要性が挙げられることになります。
このように、修繕積立金はマンションの建物としての健康、すなわち「資産価値」を維持するために必要不可欠な資金です。
修繕積立金不足が起きる理由と合意形成の壁!
つぎに、積立計画を立てているはずなのに、なぜ多くのマンションで修繕積立金不足という状況が発生してしまうのでしょうか?その主な理由には以下のようなものがあります。
①新築分譲時の設定が低すぎる
新築マンションを販売しやすくするために、買い手さんの月々の負担感が軽く見えるよう、あえて修繕積立金を著しく低く設定して販売するケースがあります。これが、将来的な資金不足の根源となります。
②段階増額積立方式の盲点
そうして新築分譲時に安く設定しても、将来的に積立金を値上げしていく「段階増額積立方式」によって帳尻を合わせられるとします。しかし、いざ値上げの時期が来ても住民間の合意が得られず、計画通りに増額できないまま資金不足に陥ってしまうことが盲点となります。
③物価や人件費の高騰
それに加え、長期修繕計画を立てた当初の想定よりも、近年の物価高騰や建設業界の人手不足により、実際の工事費用や資材費が大幅に高騰する現実があります。たとえ計画通りに積立てていても、予算が足りなくなるのです。
④突発的な修繕や滞納などによる計画崩れ
さらに、台風や地震などによる計画外の突発的な修繕や、一部の所有者さんによる管理費や積立金の長期滞納によって、資金計画が狂うことも起こり得るケースです。
⑤住民の高齢化と合意形成の壁
追い打ちをかけるように、建物の経年劣化とともに、管理組合の構成員の高齢化も進み、2つの老いに直面します。年金生活者にとって積立金値上げは死活問題。必要な増額決議が通らないという構造的な問題を抱えます。
これらの要因が複雑に絡み合い、将来の修繕に必要な資金が確保できない修繕積立金不足に陥ってしまうワケです。
修繕積立金不足が招く売れない理由!
では、修繕積立金不足という事態が、なぜ「マンションが売れない!」という状況に直結してしまうのでしょうか?その理由を、買い手側のシビアな視点から紐解いていきましょう
①将来のランニングコスト増に嫌気
その修繕積立金が不足している以上、近いうちに値上げされることは不可避だと感じる人は多いでしょう。買い手さんからすれば、「毎月のランニングコストが将来的に跳ね上がるかもしれない」という予測不能な不安を抱えることになります。
②将来の「一時金」負担への恐れ
もしくは大規模修繕の時期に、各戸から一時金として数十万円から百万円単位の高額な費用が徴収される可能性が高くなります。将来的に高額な請求が来る恐れがある物件は検討から外されます。
③管理状態の悪さへの懸念
また、「積立不足=管理状態の悪さ」のサインとして受け止められます。外壁のひび、共用部の不具合、清掃状態の悪化は、「放置の証拠」として懸念材料となり評価を下げます。
④住宅ローン審査への影響
そして、金融機関は物件の担保価値を評価する際、修繕積立金の状況をチェックします。「積立金不足で将来の資産価値維持が怪しい」と判断されれば、融資額が減額されたり、ローン審査が通らない可能性すらあります。
つまり、買い手さんは「目に見える建物の古さ」のみならず、「目に見えない将来の金銭的リスク」と「管理組合の問題」を敏感に察知しているのです。
「修繕積立金不足だけじゃない?」売れない理由!

とはいえ、修繕積立金不足は大きな要因ですが、築古マンションでは複数のマイナスが重なりやすく、売れにくさを加速させます。以下の3点に集約できます。
①建物の構造的な老朽化と耐震性の不安
まず、1981年以前の旧耐震基準の建物や耐震診断未実施の物件は、購入後の補強費やローン審査への不安から敬遠されがち。価格交渉で大幅な減額要因になります。
②設備の老朽化や設計の陳腐化
また、給排水管やエレベーター等の重い更新が迫ると将来費用が読みにくく、間取り・断熱・防犯性能の時代遅れ感も不利に働きます。内覧時の印象の悪さはそのまま成約率の低下につながります。
③管理体制の不備(自主管理/小規模建物/管理費滞納問題)
さらに、自主管理で会計や長期修繕計画が曖昧、総戸数が少なく一戸当たり負担が大きい、修繕積立金のみならず管理費の滞納が目立つ、といった要素は「将来コスト高」のシグナルになります。
これらは修繕積立金不足と同様に管理組合での合意形成や解決に、手間と時間を要するものばかりです。
2026年区分所有法改正が及ぼす売却への影響とは?
ここでは、修繕積立金不足や高齢化により合意形成が停滞した古いマンションの売却に、2026年4月施行予定の「区分所有法」改正が、どのように現実的な影響を及ぼすのか解説します。なお、この法改正は、老朽化したマンションの建て替えや売却といった「再生」の手続きを円滑化し、管理不全(管理が行き届いていない)を解消することを目的としています。
①再生決議の円滑化と「所在不明者」問題の解決
この法改正の中核は、5分の4の賛成(または特定事由がある場合の4分の3)で、建物と敷地の一括売却や一棟リノベーション(建物の更新)といった、新たな再生手法の決議が可能になる点です。さらに重要なのは、所在不明の区分所有者さんを決議の母数から除外できる措置が導入されることです。これにより、再生の決議が成立しやすくなる見込みです。
②修繕等の「普通決議」の緩和
また、日常の管理や小規模な修繕に関する決議は、現行法でも「区分所有者および議決権の過半数」が必要ですが、改正法では「集会に出席した者の過半数(電磁的方法の活用も含む)」で可能になる予定です。修繕積立金の値上げや長期修繕計画の見直しといった重要な案件の実務的な合意形成がしやすくなり、管理不全の脱却に向けて踏み出しやすくなります。
③売却市場への心理的影響
そして、これらの決議の緩和は、投資家や買い手さんに対して「このマンションは、将来の建て替えや売却といった出口戦略が具体化する可能性がある」という前向きなメッセージとなります。一方で、再生の決議に向けて動き出せない管理不全のマンションは、さらに売れにくくなる傾向が強まり、二極化が進むとも考えられます。
管理不全マンションについて国が深刻に捉えている以上、今後もこの変化は続いていくのかもしれません。ただ、決議要件の緩和がされる見込みとはいえ、依然としてハードルは高い(賛成者への金銭負担の大きさ、非賛成者への補償義務、二重ローンリスクなど)ので、法改正後の影響は限定的でしょう。
最終的に決議を進めるためには時間と労力が必要であり、待つ余裕がない所有者さんにとっては即効性のある解決策にはなり得ません。
売れない理由を改善し資産価値を上げる!
そこで、修繕積立金不足を理由に売却を諦めないためにも、管理組合での改善に尽力し、資産価値を維持または向上させる方法を検討しましょう。
①長期修繕計画の抜本的な見直し
はじめに、建築士などの専門家を交えて長期修繕計画を再点検し、最新の物価高騰や建物の劣化実態に即した計画に、抜本的に見直すことが重要です。
②積立金の適正化
つぎに、不足が明らかになった場合は、総会において勇気を持って積立金の値上げを決議し、将来の不安を解消する必要があります。また、今後の負担額が読みにくい段階増額積立方式から、均等積立方式への変更も検討します。
③管理計画認定制度の取得
そして、国土交通省などが定める「マンション管理計画認定制度」の認定の取得を目指します。「管理が適切に行われている」という行政のお墨付きを得られれば、買い手さんへの大きなアピールポイントになります。
④管理費や支出の見直し
さらに、管理会社への委託費が適正か、他社との相見積もりを取るなどしてコストを削減し、その浮いた分を修繕積立金に回すという対策も考えられます。
⑤運営の透明化と情報開示
さいごに、積立金の総額や滞納の有無、修繕履歴などの運営の透明化を図ります。ネガティブな情報も含めて包み隠さず情報開示し、買い手さんの不安を取り除く努力に努めます。
これらの対策は、時間と労力や合意形成の難しさが伴いますが、実行できれば資産価値の低下を食い止めることが可能です。
修繕積立金不足の解消に向けた合意難での売却法とは?
そうして、マンションとしての資産価値を高めることができれば、不動産仲介によって一般市場から買い手さんを見つけ、相場通りの売却価格を望むことが可能になります。
とは言え、「管理組合での改善を待っている時間がない…」あるいは「高齢者が多くて積立金増額等の合意形成が絶望的…」など、修繕積立金不足での解消に向けた合意を得ることが難しいケースは多いでしょう。
そんな場合に検討してほしい売却法が、「不動産買取」という選択肢です。「不動産買取」とは、専門業者が直接取引によってその物件を買い取る方法で、一般的な仲介とは根本的に違います。
①問題があっても現状のまま買い取ってもらえる
ひとつ目に、修繕積立金不足の問題や将来のリスク、管理組合の複雑な事情をすべて承知の上で、「現状のまま」買い取ってもらえる点が最大のメリットです。一般の買い手さんのようなリスクを恐れてのキャンセルの心配がありません。
②早期かつ確実にマンションを現金化できる
ふたつ目に、一般の買い手を探す広告期間やローン審査待ちなどが一切不要なため、最短数日~数週間というスピード感で、売買契約から決済(現金化)が可能です。「売れない…」と不安に思う時間や手間が不要です。
③見えていない問題による売却後のトラブルが少ない
みっつ目に、買取の場合は、売主さんが負う契約不適合責任(契約内容にない隠れた不具合に対する責任)が免除されるケースがほとんど。売却が完了した後に、隠れた瑕疵(不具合や欠陥)による損害賠償などのトラブルから解放されます。
もちろん、売却価格は一般の仲介による市場価格と比べると低くなる傾向にはあります。ただ、修繕積立金不足という明確な「売れない」理由を抱え、時間と手間がかかり続ける状況を打開する、最も早く確実で現実的な売却法と言えるでしょう。
まとめ
今回の記事では、修繕積立金不足でなぜマンションの売れないのか、その具体的な理由と対策について解説してきました。
まず、「修繕積立金」とは、「マンションの将来の修繕ために、所有者全員で毎月お金を積み立てる共同貯金」のことで、「将来の大きな修繕のための原資」になります。
多くのマンションでは「長期修繕計画」という、今後おおむね25〜30年程度の修繕スケジュールと費用見込みを定めた計画を作成します。たとえば70㎡なら月額で概ね1.2万〜2万円台が一つの基準感ですが、築年が進むほど修繕項目は増え、大規模修繕の単価が上がる傾向が見られます。
この修繕積立金が不足すると起こり得る問題として、修繕の先送りによってマンションの劣化が進むことで、将来の一時金徴収や急な積立月額の大幅値上げの必要性が挙げられることがあります。
つぎに、なぜ多くのマンションで修繕積立金不足になるのか、その主な理由は以下。
①新築分譲時の設定が低すぎる
②段階増額積立方式の盲点
③物価や人件費の高騰
④突発的な修繕や滞納などによる計画崩れ
⑤住民の高齢化と合意形成の壁
では、修繕積立金不足という事態が、「マンションが売れない!」という状況に直結するのか、理由は以下。
①将来のランニングコスト増に嫌気
②将来の「一時金」負担への恐れ
③管理状態の悪さへの懸念
④住宅ローン審査への影響
つまり、買い手さんは「目に見える建物の古さ」のみならず、「目に見えない将来の金銭的リスク」と「管理組合の問題」を敏感に察知しているのです。
とはいえ、修繕積立金不足は大きな要因ですが、築古マンションでは複数のマイナスが重なり、より売れにくくなります。
①建物の構造的な老朽化と耐震性の不安
②設備の老朽化や設計の陳腐化
③管理体制の不備(自主管理/小規模建物/管理費滞納問題)
これらは修繕積立金不足と同様に管理組合での合意形成や解決に、手間と時間を要するものばかりです。
修繕積立金不足の古いマンションの売却に、2026年4月施行予定の「区分所有法」改正が、どのように現実的な影響を及ぼすのか解説。
①再生決議の円滑化と「所在不明者」問題の解決
②修繕等の「普通決議」の緩和
③売却市場への心理的影響が改善
管理不全マンションについて国が深刻に捉えていますが、法改正後の影響は限定的であり、即効性のある解決策にはなり得ません。
そこで、修繕積立金不足を理由に売却を諦めないために、資産価値を維持または向上させる方法を検討しましょう。
①長期修繕計画の抜本的な見直し
②積立金の適正化
③管理計画認定制度の取得
④管理費や支出の見直し
⑤運営の透明化と情報開示
これらの対策は、時間と労力や合意形成の難しさが伴いますが、実行できれば資産価値の低下を食い止めることが可能で、仲介によって相場通りの売却価格を望むことが可能になります。
とは言え、「管理組合での改善や積立金増額等の合意形成が絶望的」など、修繕積立金不足での解消に向けた合意が難しい場合の売却法が、「不動産買取」という選択肢です。
①問題があっても現状のまま買い取ってもらえる
②早期かつ確実にマンションを現金化できる
③見えていない問題による売却後のトラブルが少ない
もちろん、売却価格は一般の仲介による市場価格と比べると低くなる傾向にはありますが、修繕積立金不足で「売れない」理由を抱え、時間と手間がかかり続ける状況を打開する、現実的な売却法と言えるでしょう。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較していただければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。
引用・参考資料
国土交通省「令和5年度マンション総合調査」の結果概要 (2024年6月公表)
国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 (令和6年6月改訂)
法務省「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法」 (令和6年12月改訂)