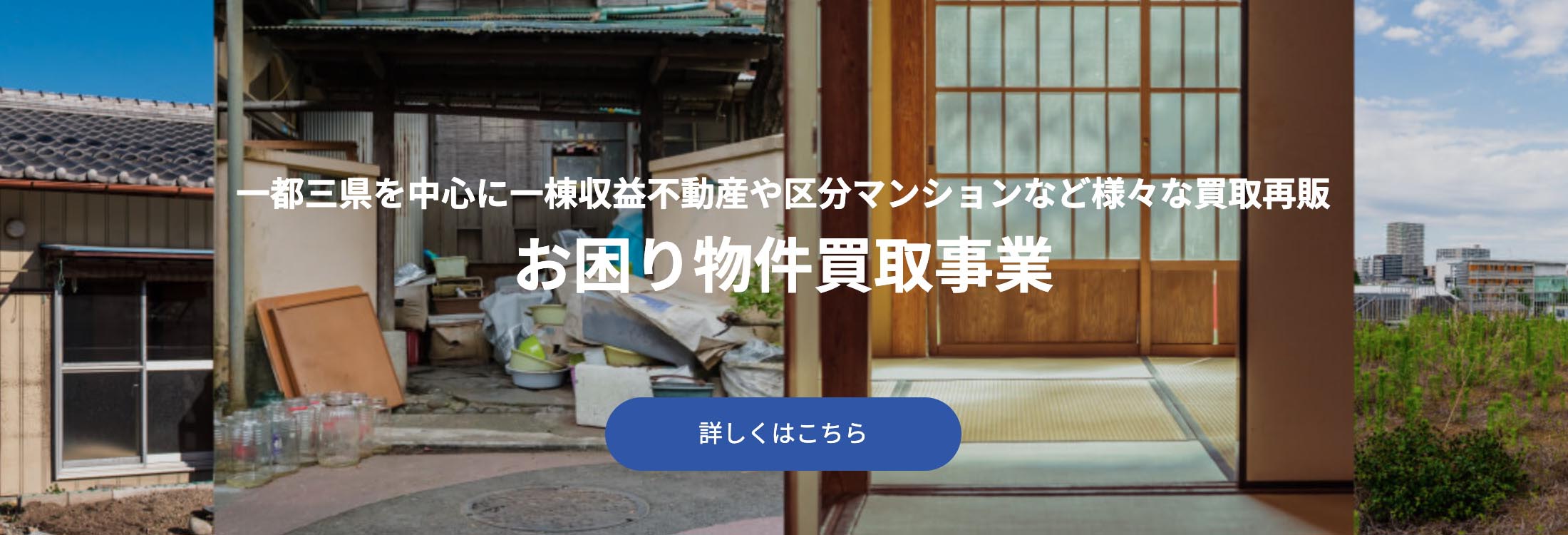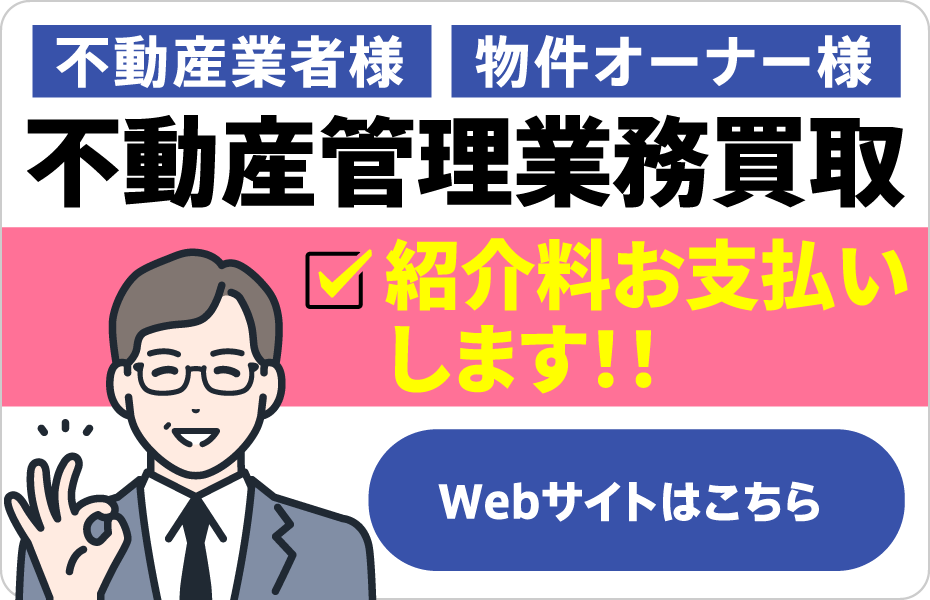独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第129回目は「老朽化マンション売却と区分所有法改正」です。
築40年以上の老朽化マンションに住む夫婦二人、子どもは独立、仕事はそろそろ引退期。住宅ローンの残債や専有部の改修の負担、管理組合の高齢化が進み共有部の管理面も気がかりで、「そろそろ売却すべきか持ち続けるか」と迷い続けていませんか?
今回の記事では、老朽化マンションにおける悩みを専有部と共有部に分けて可視化し、日本の現状と区分所有法(現行と2026年改正)を生活目線で解説。その上で「待つ」リスクと「動く」ときの壁の乗り越え方、老朽化マンション売却への現実解へと導きます。ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
老朽化マンション所有者の悩みとは?

はじめに、築40年以上に及び管理組合が機能しなくなりつつある「老朽化マンション」は、共有部において下記のような問題を抱えている場合が多いです。
・外壁や屋上:コンクリートのひび割れや剥落、鉄筋の露出、屋上防水の劣化による雨漏り
・給排水管:錆や詰まりによる水質の悪化や漏水があり、交換には多額の費用がかかる
・エレベーター:頻繁な故障や、部品供給が停止している旧式設備の維持困難
・耐震性の不足:1981年6月以前の「旧耐震基準」で建てられていれば、大地震への不安がある
・修繕積立金の不足:長期修繕計画が甘く、いざ大規模修繕という段階で資金が足りず
・理事会の機能不全:理事の担い手不足や総会出席率の低下で意思決定が停滞
ただ、共有部のみならずご自身の専有部にも問題を抱えます。
・設備の劣化:水回り(キッチン・浴室・トイレ)の配管や電気系統設備の劣化
・断熱性や気密性の低さ:冬は寒く夏は暑い。結露やカビが発生しやすく、光熱費もかさむ
・内装の陳腐化:段差や建具不良、床・クロスの傷みで内見時の印象が低下
それらは、家計や生活へダイレクトに影響し、毎月の管理費・修繕積立金の増加に加えて、突発的な修繕費用やリフォーム費用が重くのしかかります。
子供たちは独立し、仕事の引退や老後を意識するようになる中で、「年金生活でこの先の維持費を払い続けられるだろうか」「もし大規模な地震が来たら…」「この家を子どもたちに相続させても、かえって負担になるだけではないか」といった不安が、売却か維持かの迷いをより一層深くさせていきます。
老朽化マンションを取り巻く日本の現状!
また、老朽化マンションを取り巻く日本の現状は、一段と深刻なものになってきています。
①2つの老い
ひとつに、マンションの2つの老いがあり、「建物」の老朽化とそこに住む「居住者」の高齢化が同時に進行しています。高経年(築古)マンションは今後も増加することがほぼ確定する中、それらの居住者さんの高齢化により、管理組合の役員のなり手がおらず、活動が停滞。結果として、建物の老朽化に適切な対策が打てないという悪循環に陥っています。
②荒廃が進むマンションの増加
つぎに、管理不全に陥ったマンションは、外観が悪化し空室が増加。結果として住民間のコミュニティの維持が難しくなるケースもあります。最悪の場合、適切な管理が放棄され、衛生面や防犯面で問題のある状態に至る恐れがあります。
③所在不明の区分所有者への対応
そして、相続未登記や海外居住などで、区分所有者さんと連絡が取れない住戸が増えています。大規模修繕や建替えといった重要な意思決定には、集会(総会)での多数の賛成が必要ですが、所在不明な人がいると定足数を満たせず、何も決められないという事態が発生します。
④行政不介入の現実
さらに、これまでの運営管理は区分所有者間の自助が原則。マンションはあくまで「個人の資産の集合体」であるため、これまで行政は管理組合の運営に積極的に介入できませんでした。問題が深刻化しても、基本的には当事者間で解決するしかないのが実情。
⑤建て替えの実現性の低さ
さいごに、老朽化の最終的な解決策である「建て替え」は、区分所有者さんの5分の4以上という非常に高い合意形成のハードルがあります。加えて、数千万円にも及ぶこともある所有者一人ひとりの費用負担が重く、全国的に見ても実現しているケースはごく僅かです。
以上の問題が複雑に絡み合い、多くの老朽化マンションが身動きの取れない状況に追い込まれているのです。
2026年改正の区分所有法で変化の兆し?
これらの問題が、2026年4月の区分所有法改正によって、変化の兆しとも捉えられる動きがありそうです。2025年に公布されたもので、今後段階的に施行される予定で以下が決まっています。
①所在不明者への対応強化
まず、これまで意思決定の妨げとなっていた所在不明者などを、裁判所の決定を得ることで集会の決議の母数から除外できるようになります。これにより、管理組合の意思決定がスムーズになることが期待されます。
②集会決議の要件緩和
つぎに、通常の集会決議の範囲が広がり前に進めやすい方向に。特定の更新工事に関する決議要件であること、あるいは特定の瑕疵(かし:欠陥)やバリアフリーに関する変更決議が3分の2に要件緩和されます。
③管理組合による専有部への介入
また、管理規約の改定などを前提に、給排水管の工事といった他の居住者さんの利益を守るため、共用部保全に必要な範囲で専有部へ立ち入るなど、実務上の詰まり解消や不適切な管理への是正に資する仕組みが整備。
④建替えの要件緩和と多様な出口の追加
そして、耐震性不足など生命に危険が及ぶマンションの建替え決議が、従来の「5分の4以上」から「4分の3以上」の賛成に緩和されます。また、建替え・一括売却・一棟リノベーション・解体後の敷地売却といった選択肢が機能しやすくなる方向にあります。
⑤管理不全マンションへの行政介入
とくに外壁の剥落など、周囲に危険を及ぼす恐れのある管理不全マンションに対し、行政(市区町村長)が指導・勧告、さらには代執行を行えるようになります。これにより、管理組合の怠慢に一定の抑止力が働くことが期待されます。
これら区分所有法のみならず、他にも、
・マンション管理計画認定制度:適切な管理計画を持つマンションを自治体が認定する制度で、住宅融資支援機構による金利優遇や減額措置を受けられる可能性あり
・相続登記義務化:相続を知った日から3年以内の登記申請が義務化され、所有者不明問題の発生を抑制する効果に期待
などといったマンション再生への好循環を促す法整備が進んできています。
ただし、依然として残る懸念点もあります。
・法改正は「決めやすくする」が、最終的に行動を起こすのはあくまでも管理組合や区分所有者
・建替えなどにかかる高額な費用は、法改正後も所有者一人ひとりに重い負担
・行政の介入は、あくまでも周辺への危険が明白な場合に限られ、安易に発動されない
・決議要件が下がったとは言え、合意形成への難易度は高い
老朽化マンション売却を「待つ」ことで起こるリスク!

ともあれ、これから改善へと進むのであれば、老朽化マンションもすぐには売却せずに、情勢が整うのを「待つ」という選択肢もありそうです。しかし、その選択には大きなリスクが伴います。
①価格の逓減(ていげん)と競合増る
そもそも建物のさらなる老朽化とともに、資産価値は刻一刻と下落していきます。今後、同じように売却を考える老朽化マンションの競合が市場に増え、買い手を見つけるための価格競争はさらに激しくなることが見込まれます。
②保有コストの累積
不動産は住んでいなくても、管理費、修繕積立金、固定資産税は毎年発生します。今後、修繕積立金が値上げされたり、大規模修繕のための一時金(積立不足分を補う)が徴収されたりする可能性も高く、保有しているだけでコストはかさみ続けます。
③時間と手間の消耗
時間や手間も明確なコストです。金銭的な負担だけでなく、管理組合の役員としての活動や、住民間のトラブル対応などの手間、時間的な負担も増大し精神的に消耗します。貴重な老後の時間を、マンションの問題に費やし続けることになりかねません。
そのため、ただただ楽観的に「待つ」姿勢でいることは、リスクかもしれません。あまりにも将来的な不確定要素が多すぎます。
老朽化マンション売却で「動く」ことで立ちはだかる壁!
では、現状の苦しい状況を変えるためにも、老朽化マンション売却に向けて「動く」ことは、もう一つの選択肢です。ただ、そこにも立ちはだかる壁があります。
①融資の壁
たとえ買い手が見つかっても、マンションに旧耐震や管理不全懸念があると、担保評価が低くなり住宅ローン審査が難航。住宅ローン減税の適用外(耐火構造では25年以内など)であることもあり、買い手の裾野はより狭くなります。
②耐震の壁
そもそも旧耐震基準のマンション(建築申請が1981年5月31日以前)は、買主さんから敬遠されがちです。地震への不安を拭うためにも、耐震診断や補強工事をしたいところですが、それには多額の費用がかかり売却の大きな足かせとなります。
③管理の壁
加えて、修繕積立金の滞納が多い、長期修繕計画が存在しない、総会の議事録が整備されていないなど、管理状況が悪いと、買主は将来の費用の不確実性を懸念します。これらの情報は売買時に告知義務があり、売却価格の低下や、最悪の場合は売買不成立につながります。
これらの壁を個人で乗り越えるのは、精神的にも肉体的にも非常に困難な道のりです。
老朽化マンション売却には「見える化」が大切!
それでも、老朽化マンション売却に向けて「動く」と決めたなら、まずは現状を客観的に把握し、買主さんに対して情報を開示できる状態にすることが重要です。これを「見える化」と呼びます。
①管理状況の見える化
まずは、管理規約、長期修繕計画書、総会議事録、収支報告書などを一式揃え、マンションがどのように維持管理されてきたかを明確に示せるように準備します。これにより、少しでも買主さんの不安を払拭できるよう努めます。
②住宅・耐震診断で見える化
また、専有部のみならず建物全体の専門家によるインスペクション(建物状況調査)や耐震診断を実施し、建物の現状を客観的なレポートとして示します。費用はかかりますが、問題点を正確に伝え後のトラブルを防ぎ、誠実な取引につながります。
③専有部の費用対効果の見える化
そして、専有部について、いつどこをリフォームしたか、設備の状況などをまとめておきます。フルリノベーションは資金回収が難しいので、むしろ買主さんが自分好みにリフォームできるよう、その分価格で調整する方が賢明な場合も多いです。
その上で、経済面(管理費・修繕積立金・固定資産税など)と生活面(住み替え時期・現役引退時期など)から、意思決定の期限や売却価格、不動産「仲介」を諦め「買取」への切替条件を明確することが大切です。
老朽化マンションが管理不全や積立不足でも現実解はある?
これらの「見える化」を進めた上で、具体的な出口戦略を検討します。主な選択肢は3つです。
①賃貸として活用
ひとつに、売却せずに賃貸に出し、家賃収入を得る方法です。ただし、空室リスクや家賃滞納リスク、入居者トラブル、設備の修繕費負担などが伴います。当然、建物の老朽化が進めば、借り手を見つけること自体が難しくなる可能性も考慮しなければなりません。
もし、うまく運用できて家賃収入という「収益の見通し」を付加すれば、投資家向けに訴求することが可能になるケースもあります。
②仲介による通常売却
つぎに、不動産仲介業者に依頼し、一般の買い手を探してもらう方法です。市場価格に近い値段で売れる可能性がありますが、手間や時間がかかる、価格交渉が入る、といった不確実性があります。特に老朽化マンションであれば、売れ残ってしまうリスクが低くありません。
ただ、物件の条件が悪くても、立地などの好条件が他にあれば、思った以上に高額売却の可能性があります。
③業者買取での売却
さいごに、不動産買取専門業者に、直接物件を買い取ってもらう方法です。売却価格は一般市場相場の7〜8割程度になるのが一般的ですが、スピーディに現金化でき、仲介手数料もかかりません。
また、建物の欠陥などに対する「契約不適合責任(契約内容と実態が違った際の売主責任)」が免責されるケースが多く、売却後の心配から解放されるという大きなメリットがあります。
これらの判断基準は以下となります。
・賃貸活用での「可能性」と仲介の「相場狙い」、買取の「確度高い提示」を手取りで比較する
・時間と手間をかけて得られる価値を見極める
・許容できるリスクを正しく把握する
ただ、老朽化マンションのような、管理不全・積立不足・旧耐震・記録不備、さらには駅から遠いなどの悪条件では、仲介は長期化・価格調整のリスクが相対的に大きくなりやすい傾向にあります。
一方買取であれば、スピード・確実性・手離れの良さで「生活合理性」が高い現実解であると言えます。
まとめ
今回の記事では、老朽化マンションの売却における、日本の現状と区分所有法(現行と2026年改正)を生活目線で解説。その上で売却への現実解についてお話してきました。
はじめに、築40年以上に及び管理組合が機能しなくなりつつある「老朽化マンション」は、耐震性懸念や修繕積立金の不足などといった問題があり、共有部のみならず専有部にも、設備と内装の劣化や陳腐化などといった問題を抱えます。
それらは、家計や生活へダイレクトに影響し、負担は重くのしかかり、ライフステージの変化による不安で、売却か維持かの迷いを生みます。
また、老朽化マンションを取り巻く日本の現状は、一段と深刻なものになってきています。
①「建物」と「居住者」の2つの老い
②荒廃するマンションの増加
③所在不明の区分所有者への対応の難しさ
④行政不介入の現実で意思決定が進まない
⑤建て替えの実現性の低さ
これらの問題が、2026年4月の区分所有法改正によって、変化の兆しとも捉えられる動きがありそうです。
①所在不明者への対応強化
②集会決議の要件緩和
③管理組合による専有部への介入
④建替えの要件緩和と多様な出口の追加
⑤管理不全マンションへの行政介入
他にも「マンション管理計画認定制度」「相続登記義務化」などといったマンション再生への法整備が進んできています。ただし、「建替えなどの高額費用負担」「合意形成への難易度はまだ高い」などの依然として残る懸念点があります。
老朽化マンションは売却せずに、情勢が整うのを「待つ」という選択肢もありますが、リスクが伴い将来的な不確定要素が多すぎます。
①価格の逓減(ていげん)と競合増
②保有コストの累積
③時間と手間の消耗
老朽化マンション売却に向けて「動く」ことも選択肢ですが、そこにも立ちはだかる壁があり、精神的にも肉体的にも非常に困難な道のりです。
①融資の壁
②耐震の壁
③管理の壁
それでも「動く」と決めたなら、まずは現状を客観的に把握し、情報を開示できる「見える化」することが重要です。
①管理状況の見える化
②住宅・耐震診断で見える化
③専有部の費用対効果の見える化
これらの「見える化」を進めた上で、具体的な出口戦略の選択肢は3つです。
①賃貸として活用
②仲介による通常売却
③業者買取での売却
これらを「手取りで比較する・得られる価値を見極める・許容リスクを把握する」といった基準で判断します。
ただ、老朽化マンションのような悪条件では、仲介はリスクが相対的に大きくなりやすい傾向にあります。
一方買取であれば、スピード・確実性・手離れの良さで「生活合理性」が高い現実解であると言えます。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較していただければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。