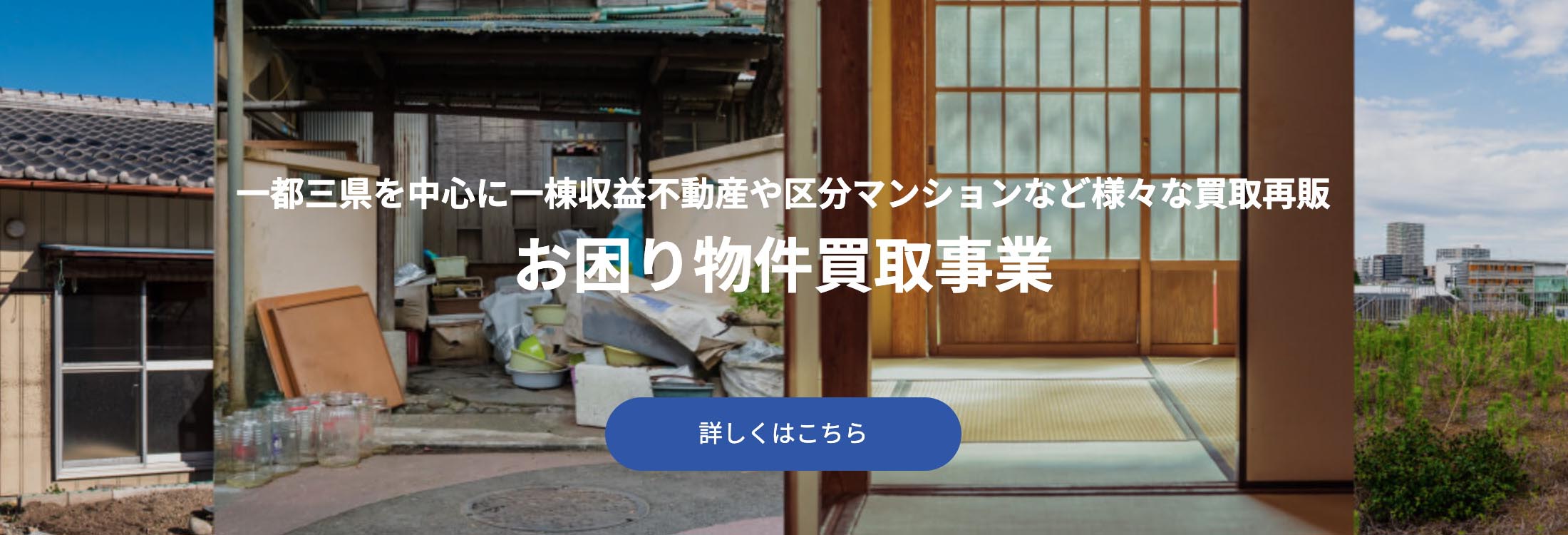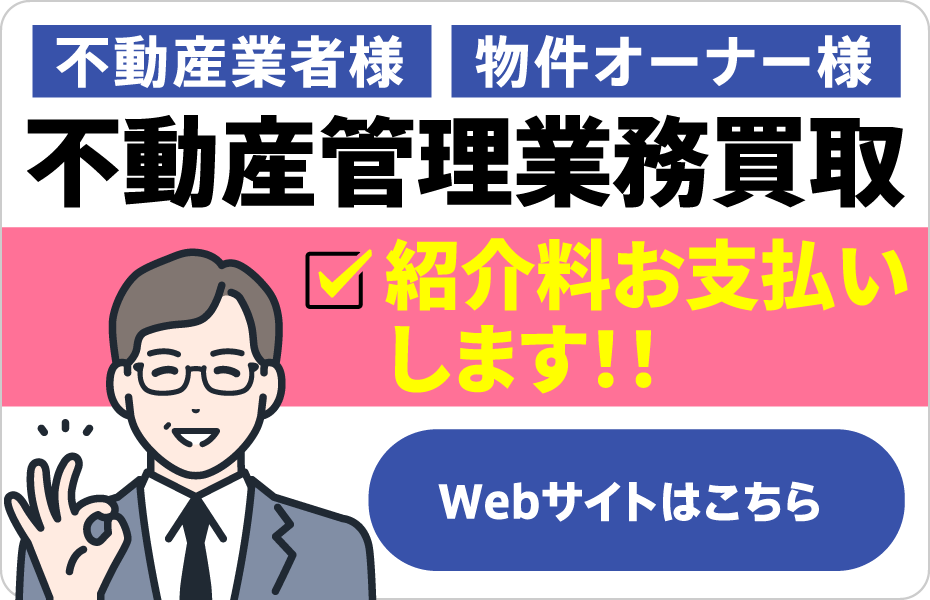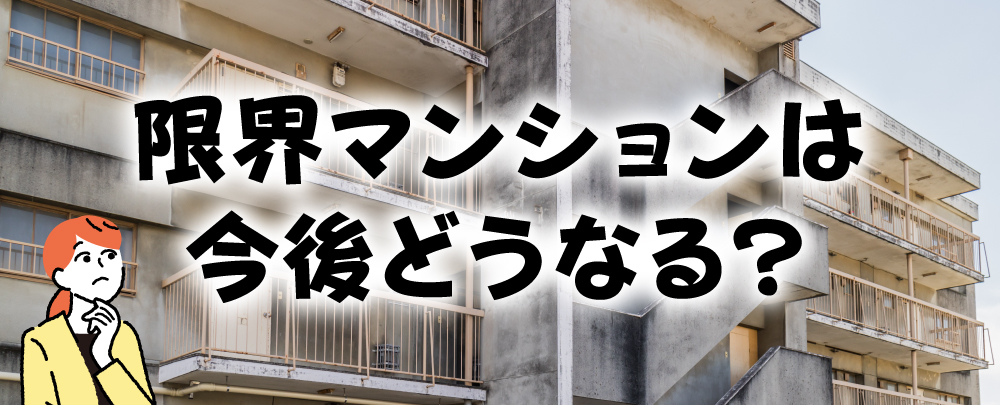
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第97回目は「限界マンションをどうするか?」です。
「築年数が古いマンションを所有しているけれど、このまま住み続けても大丈夫だろうか?」と、そう感じたことはありませんか?現在の日本では、空き家問題が度々クローズアップされています。それは、マンションも例外ではありません。このことから、実は同じような不安を抱える人が、年々増えてきています。老朽化してきているのに、管理費や修繕積立金が不足したり、管理組合の活動が停滞していたりする…。この「限界マンション」は今後どうなっていくのでしょうか?
今回の記事では、「限界マンション」が抱える問題と、スラム化させないための対策、そして最終手段としての不動産売却も検討すべき状況についてまで、分かりやすく解説します。もし老朽化や管理組合のトラブルが深刻化しはじめたら、解決を先送りにするのではなく、不動産売却も視野に早めの対策をしていきましょう!
限界マンションとは?

はじめに、「限界マンション」とは、「築年数が古く老朽化や管理不全によって十分な維持管理ができなくなった(限界がきてしまった)マンション」のこと。建物の安全性や快適性が低下して、住民さんの生活にも支障をきたしている状態です。また、不動産としての価値も低下してしまっています。
なぜそんな状況にあるのか、主な要因は以下。
・築年数の経過:概ね築40〜50年を超えてきている上、住民が高齢化している
・建物の老朽化:適切な時期に大規模修繕が行われずに劣化が出ている
・修繕積立金の不足:大規模修繕や設備更新のための資金が集まっていない
・空室率の上昇:イメージが悪く入居希望者がいない上、相続も発生している
・管理不良:日常的な清掃や点検も行われていない
・建て替え不可:「居住者の5分の4以上の賛成」が得られない
こうした状況に陥ると、マンションそのものの価値が下がるばかりか、空き部屋が犯罪の温床になることへの懸念、住民同士でのトラブルも増える恐れがあります。また、建築基準法における新耐震基準に適合しておらず、耐震補強工事も適切に行われていないため、耐震性にも懸念があります。
にも関わらず、一戸建てに対して権利者さんが多いマンションでは、問題解決に向けての対応がしづらいんです。複雑化した権利関係でがんじがらめになり、動きたくても動けないケースもたくさんあります。
近年、こうした限界マンションが増加しており、国や自治体も対策に乗り出しています。例えば「マンション建替円滑化法」や「マンション管理適正化法」など、制度の整備を進めているものの、それでも住民間で合意形成ができず、抜本的な解決に至らないケースも多いのが実情です。
老朽化と管理組合の機能不全!
つぎに、限界マンションの代表的な要因である「老朽化」と「管理組合の機能不全」について、もう少し深堀りしてみましょう。
必要な点検や修繕をしないでいると、時の流れとともに老朽化が顕在化し、マンション全体の維持管理に大きな負担がかかります。一般的には、築10〜15年ごとに計画的な大規模修繕を行い、外壁や配管、エレベーターなどの設備を補強・更新していかなくてはなりません。
しかし、資金不足などにより適切な修繕が行えていないと以下のような状況を生みます。
①外壁の劣化や防水不良
分かりやすく変化するのは、外壁の劣化です。コンクリートのひび割れ、屋上などの防水不良、タイルの剥落などが放置されると、ときには落下物による事故の可能性もあり、美観だけではなく安全面にも悪影響が及びます。また、雨水がクラック(亀裂)から入り、中の鉄筋が腐食すれば、建物自体の耐久性も大幅に低下することになります。
②配管の腐食や詰まり
つぎに、配管の劣化の恐れです。給排水管が古くなると内部がサビなどで狭くなり、水漏れや汚水の逆流が起こりやすくなります。特に古いマンションでは、給排水管が駆体(主体構造)内部に組み込まれているケースがあり、修繕などの対処もしづらい場合があります。もし、一部の住戸で配管トラブルがあると、上下階や隣戸にも被害が及ぶため、トラブル対応費用も膨大になります。
③設備の故障や陳腐化
そして、設備は古いまま使い続けると、故障リスクが高まり修理部品の調達が難しくなることも。エレベーターであれば、一般に耐用年数は20〜25年程度とされますし、宅配ボックスやオートロックなどの新しい設備が未設置の場合、住民の利便性や防犯性の面で魅力も低下します。
これらを全て修繕しようとすると、多額の費用がかかります。そこで、通常であれば区分所有者である住民全員で参加する管理組合が、集金や資金管理といった運営を主体的に行っていくことになります。
ところが、下記の理由で管理組合が機能不全を起こすことがあります。
・人材不足:高齢化の進むマンションにおいて理事会役員のなり手がすくない(敬遠する)
・所有者が不明:相続などで名義が複雑になり所有者がはっきりしなくなる
・資金不足:管理費や修繕積立金を滞納する所有者が増えて資金繰りが悪化する
・住民間の対立:経済状況やライフスタイルの違いから運営方針で住民間の対立が起こる
・合意形成の難航:建て替えやリノベーションについての賛成多数を得られずに頓挫する
これらの問題が顕在化すると、管理組合は形式上は存在していても、実質的には何も進まない状態に!その結果、マンションの老朽化は加速し、「限界マンション」に近づいていきます。
「限界マンションは今後どうなる?」スラム化のリスク!
では、そのままの状態を放置すると、限界マンションは今後どうなるのでしょうか?その答えの一つとして挙げられるのが、「スラム化」とも言うべき状態です。スラム化の特徴は以下のようなもの。
①建物の美観が損なわれ荒廃する
まず、「割れ窓理論」ってご存知ですか?「はじめは小さな割れ窓でも放置すれば、モラルが低下して広がっていく(破損が気にならなくなる)」というもの。壁のひび割れや汚れ、落書きなどが放置され、マンション全体が荒んでいきます。日常の清掃がままならず、美観が損なわれ荒廃します。
②周辺地域への影響
それは当然のように周辺地域に影響していきます。ゴミの不法投棄や部屋を不法占拠する人間も現れます。衛生的にも防犯的にも問題が大きくなり、近隣住民や自治体から苦情が寄せられることもあるんです。また、地域全体の地価に影響が及ぶ可能性も否定できません。
③設備等の管理不良
さらには、廊下の照明は切れたまま変えられることはなく、エレベーターのメンテナンスはされずに停止しています。共用部の管理が行き届かないと安全性や快適性は失われ、ますます住民さんは離れて行くことになります。
④空室率の上昇とさらなる資金繰りの悪化
そうして、空室率が上昇するなか、「何だか治安が悪そう…」と感じる人が増えれば、新たな入居者さんも増えていきません。資金繰りはさらに悪化の一途を辿り、修繕どころか日常的に管理するチャンスをも逃し、またイメージが悪くなるという悪循環から抜け出せません。
⑤不動産価値の急激な低下
そんなマンションの空室率や管理状態の悪さは一目瞭然です。いざ物件を売りたいと思っても、買い手さんがつかず、不動産価値はさらに急激な低下は避けられません。売りどきを逃し、結果として大きな損失を被る恐れがあります。
この悪循環に陥ると、マンションに住み続ける人がさらに減り、スラム化が深刻化してしまいます。最終的には、建物の安全性が危険なレベルに達することもあるため、行政代執行による解体が執り行われる可能性も出てきます。それを避けるためには、早期の対策が欠かせないんです。
国による限界マンションへの取り組み!

もちろん、全ての築古のマンションがスラム化するワケではありません!きちんと計画を立て、住民同士が協力すれば再生のチャンスはあります。ここでは、国が進める取り組みを確認していきます。
①マンション建替円滑化法
まず、マンションの建て替えを円滑に進めるために定めた法律で「マンション建替円滑化法」があります。この法律では、建物の耐震性不足・火災安全性不足などの理由で「要除却認定」を受けたマンションを対象としています。主な内容として、容積率緩和特例(同じ敷地で規模の大きいマンションに建て替えられる)や、「マンション敷地売却制度」というマンションと敷地を一括売却の合意形成がしやすくする仕組みもあります。
②マンション管理適正化法
つぎに、管理組合の適正な運営を促し、良好な居住環境を確保するために、「マンション管理適正化法」といって各戸の区分所有者間でしっかり話し合いを行うための法律があります。マンション管理士といった専門家さんを活用する仕組みが整えられており、管理計画の策定や管理業者さんとの契約内容のチェックなど、実務面での指導・支援が期待できます。
③空家対策特別措置法
そして、地域活性化と住宅資源の有効活用を促すため、特定空家等(安全性や衛生的に著しく問題のある空き家)への対処を目的とした法律で「空家対策特別措置法」があります。主に一戸建ての空き家に対して想定された法律ですが、マンション内の空き住戸においても例外ではありません。倒壊などの危険性や著しい物件に対して、自治体が指導・勧告してきます。先述した通り、最終的には行政代執行で強制的に解体・撤去するケースも考えられます。大変大きなペナルティですが、逆に言えば、コレを避けるために住人間で一致団結することが出来るかもしれません!
限界マンションをスラム化させないための対策!
その上で、限界マンションをスラム化させないための、具体的に打てる対策を見ていきましょう。前提として、住民間の合意形成は不可欠ですが、行動を起こすことで事態が好転するかもしれません!
①管理組合の活性化や専門家の介入
まずは、管理組合の活性化に向けての取り組みを諦めてはいけません!管理組合が機能してこそ、大規模修繕や建て替えなどの議論も進められます。理事会のメンバーに若い世代や新しく入居した人にも積極的に参加してもらい、柔軟な意見が出やすくなるでしょう。そこに、管理会社や不動産の専門家さんを交え、客観的なデータに基づく議論を行うのも有効です。第三者の専門家さんの介入により、スムーズに手続きが進む可能性があります。
②将来像の共有と修繕積立金・管理費の見直し
つぎに、マンションの将来像を住民間で話し合っていきます。「このままマンションの老朽化を放置するとどうなるか?」を共有することが重要です。長期修繕計画の策定や建て替えの検討などを明確にしていきます。修繕積立金と管理費の見直しを行い、少額でも安定して積み立てられる体制を整えます。ときに、補助金や助成制度が使える場合もあるため、自治体の情報を小まめにチェックしていきます。
③設備の更新やリノベーションの検討
そして、マンションの価値を維持及び向上をしていくために、設備の更新やリノベーションの検討をしていきます。共用部分の大きな改修には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要ですが、実行できれば建物の機能性や快適性を改善することができます。エレベーターや宅配ボックスなどの設備が充実すれば、不動産としての魅力を向上し、入居者さんが増えるかもしれません。それによって空室率が下がれば、管理費収入を増やすことができます。
④世帯数を増やす建て替えの検討
さらに、耐震性が低い、老朽化が著しい、設備が古すぎる、十分な大規模修繕費用の用意が見込めない場合は、世帯数を増やす建て替えの検討をするのも一つの手段です。マンション建替円滑化法などを活用すれば、容積率緩和特例を得られる可能性があります。世帯数を増やすことで管理費収入が増し、マンション全体が安定的に運営できることも。建て替えには、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上の賛成という合意形成のハードルは高いものの、成功すれば大幅なバリューアップが期待できる上、新しい分譲によって資金を作れる場合もあります。
⑤マンション全体の売却を検討
さいごに、なかなか住民の合意形成が取れず、老朽化が進むばかりというケースでは、先述の「マンション敷地売却制度」を活用し、マンション自体を一括で売却する選択肢もあります。ただし、この方法には組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上が合意する必要があり、協議が長期化しやすい点に注意が必要です。その一方で、デベロッパーや不動産会社に一括で売却することで、建て替えや再開発への道が開ける場合もあります。
スラム化する前に不動産売却も検討しよう!
ただ、対策を打ったところで、実際には「他の住民の理解が得られない」「費用負担が重すぎる」「住環境が悪くなる一方」などといったケースもあるでしょう。そこで、最後の選択肢として、スラム化する前にご自身の不動産のみの売却も検討しましょう!
不動産仲介で売却するなら、一般の不動産市場を通じて買主さんを探すことで、築年数や立地、専有部分の状況によっては、思いの外高く売れる可能性があります。しかし、老朽化が深刻な限界マンションでは買い手さんが付かず、売りに出しても長期間まったく動きがない場合もあります。それどころか、売却活動に手間取った挙げ句に売却できないことも。
限界マンションは、仲介を利用しても「売りたくても売れない」という状態に陥るケースが殆どです。そこで、不動産仲介での売却が難しい場合は、不動産買取も一つの選択肢となりますが、どうしても売却価格は低く見積もられることになります。
ただ一方で、不動産買取は以下のようなメリットが得られます。
①老朽化があっても売却可能
ひとつに、老朽化があっても売却可能です。見た目の古さだけでなく、立地や間取りなど総合的に評価してもらえるため、リノベーションや建て替え前提で購入してもらえます。それは、瑕疵(隠れた欠陥)があることも踏まえて買取業者さんは判断しているので、売却後の責任も回避できます。
②スピーディーな現金化
つぎに、買取業者との直接交渉のため、スピーディーに売却が決まることがあります。早期に現金化の目処が立てば、新たな住まいや生活環境を整えやすくなるでしょう。
③他の住民に知られずに売却できる
さらに、内覧や広告といった売却活動が不要なため、他の住民に知られずに売却できることになります。手間や時間をかけずに、プライバシーも守れます。
とは言え、「こんな限界マンションでも買い取ってくれるの?」と思われるかもしれませんが、実際には限界マンションでも、買取実績を持つ不動産買取業者さんは多数存在します。まずは無料査定だけでも依頼し、現状を客観的に把握してみる行動が大切です。
まとめ
今回の記事では、「限界マンション」が抱える問題と、スラム化させないための対策、そして最終手段としての不動産売却も検討すべき状況についてまで、分かりやすく解説していきました。
はじめに、「限界マンション」とは、「築年数が古く老朽化や管理不全によって十分な維持管理ができなくなった(限界がきてしまった)マンション」のこと。建物の安全性や快適性、不動産としての価値も低下してしまっています。
こうした状況にある主な要因は、築年数の経過・建物の老朽化・修繕積立金の不足・空室率の上昇・管理不良・建て替え不可があります。
こうした状況に陥ると、マンションそのものの価値が下がるばかりか、空き住戸が犯罪の温床になる・住民同士でのトラブル・耐震性にも懸念があります。にも関わらず、複雑化した権利関係でがんじがらめになり、動きたくても動けないケースもたくさんあります。
一般的には計画的な大規模修繕を行い補強・更新していかなくては「老朽化」しますが、資金不足など「管理組合の機能不全」により適切な修繕が行えていないと以下のような状況を生みます。
①外壁の劣化や防水不良
②配管の腐食や詰まり
③設備の故障や陳腐化
これらを全て修繕しようとすると、多額の費用がかかります。そこで、通常であれば管理組合が、集金や資金管理といった運営を主体的に行っていくことになりますが、人材不足・所有者が不明・資金不足・住民間の対立・合意形成の難航により、管理組合が機能不全を起こすことがあります。
問題が顕在化しても限界マンションをそのまま放置すると、「スラム化」します。スラム化の特徴は以下のようなもの。
①建物の美観が損なわれ荒廃する
②周辺地域への影響
③設備等の管理不良
④空室率の上昇とさらなる資金繰りの悪化
⑤不動産価値の急激な低下
この悪循環に陥ると、マンションに住み続ける人がさらに減り、スラム化が深刻化してしまいます。それを避けるためには、早期の対策が欠かせないんです。
限界マンションがスラム化することを防ぐために、国が進める取り組みを確認していきます。
①マンション建替円滑化法(及びその中にマンション敷地売却制度がある)
②マンション管理適正化法
③空家対策特別措置法
その上で、限界マンションをスラム化させないための、具体的に打てる対策は以下。
①管理組合の活性化や専門家の介入
②将来像の共有と修繕積立金・管理費の見直し
③設備の更新やリノベーションの検討
④世帯数を増やす建て替えの検討
⑤マンション全体の売却を検討
ただ、対策を打ったところで、実際には他の住民の理解が得られないなどといったケースもあるでしょう。そこで、最後の選択肢として、スラム化する前にご自身の不動産のみの売却も検討しましょう!
不動産仲介で売却するなら、築年数や立地、専有部分の状況によっては、思いの外高く売れる可能性があります。しかし、老朽化が深刻な限界マンションでは売却できないことも。
そこで、不動産仲介での売却が難しい場合は、不動産買取も一つの選択肢となりますが、どうしても売却価格は低く見積もられることになります。
ただ一方で、不動産買取は以下のようなメリットが得られます。
①老朽化があっても売却可能
②スピーディーな現金化
③他の住民に知られずに売却できる
限界マンションでも、買取実績を持つ不動産買取業者さんは多数存在します。まずは無料査定だけでも依頼し、現状を客観的に把握してみる行動が大切です。
私たちエスエイアシストも、そういった不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々と解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較して頂ければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。