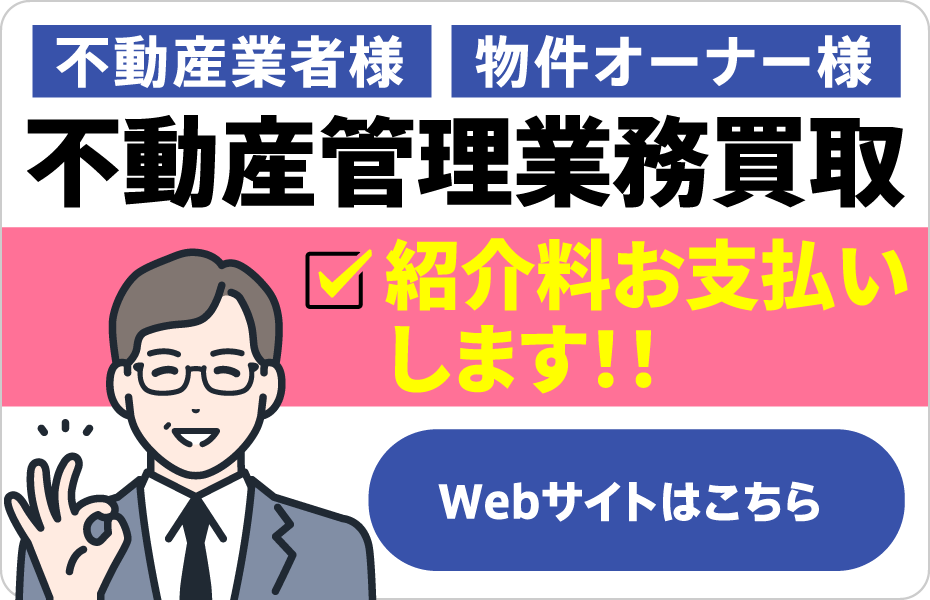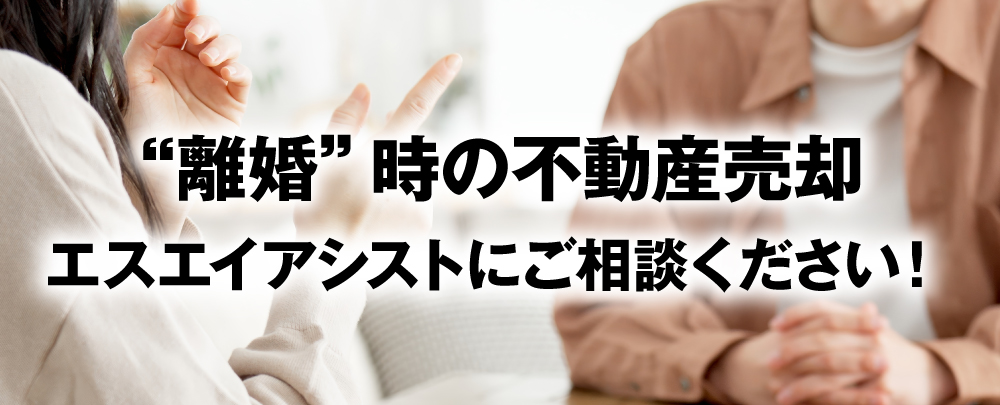
独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!今回も農地を宅地として売却する方法を解説します。
農地を宅地に転用して売るための流れ
農地を宅地に返却して売却する場合、複雑なプロセスを踏む必要があります。いかに6つのステップを解説します。
①不動産会社の選定と相談
農地の売却を検討する際、最初に行うべきは、農地取引に精通した不動産会社への相談です。農地の売買は、通常の宅地取引と異なり、農業委員会の許可や地目変更などの行政手続きが必要となるため、専門知識と実績を持つパートナーの存在が不可欠です。適切な不動産会社であれば、買主の選定から価格査定、転用手続きの支援まで一貫したサポートが期待できます。
②停止条件付き売買契約の締結
買主が決まった段階で、農地転用の許可を前提とした「停止条件付き売買契約」を締結します。これは、転用許可が下りた場合にのみ契約が有効となる形式で、許可が得られなかった場合のリスクを回避するための措置です。農業委員会は、買主が明確でない場合や契約の実現性が不透明な場合、許可を出しにくいため、事前にこの契約を結ぶことが実務上の要件となります。
③農業委員会への転用許可申請
契約締結後、農業委員会を通じて都道府県知事宛に農地転用の許可申請を行います。申請は売主・買主の連名で行い、郵送やオンラインでは受け付けられないため、窓口での手続きが必要です。許可が下りるまでには通常6週間程度を要するため、スケジュールには余裕を持たせることが重要です。
④仮登記による所有権移転の保全
転用許可が下りる前に、所有権移転の仮登記を行います。これは、買主にとって契約の安全性を担保するための措置であり、登記順位を確保する役割を果たします。ただし、この段階では所有権はまだ移転しておらず、許可取得後に本登記が必要です。
⑤地目変更登記の実施
転用許可が下りた後、速やかに地目変更登記を行います。農地から宅地への地目変更は自動的には行われず、申請が必要です。変更が発生してから1カ月以内に登記を行わなければならないため、許可取得後の迅速な対応が求められます。なお、建物の新築と同時に登記を行うケースもありますが、原則として地目変更が完了しないと所有権移転登記もできません。
⑥本登記と代金支払いによる取引完了/span>
最後に、法務局に転用許可書を提出し、所有権移転の本登記を行います。これにより、買主への正式な所有権移転が完了し、代金の精算をもって一連の取引が終了します。なお、転用許可が下りなかった場合は、停止条件付き契約に基づき契約は無効となり、取引は白紙に戻ります。
農地転用・売却における注意点
農地の宅地転用と売却には、以下のような実務上のリスクや制約が存在します。事前に把握しておくことで、トラブルの回避やスムーズな売却が可能になります。
①転用には長期間を要する
市街化区域内であっても、許可取得までに1週間から数カ月、市街化調整区域では1年近くかかるケースもあります。スケジュール管理を誤ると、買主の工事予定に影響を与えるなど、契約トラブルの原因となります。
②無許可転用は法的リスクを伴う
農地転用の許可を得ずに造成や売却を行うと、原状回復命令や懲役・罰金といった法的制裁の対象となります。手続きの順序を誤るだけでも違法と見なされる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
③転用前の売却は出来ない
農地のままでは、非農家への所有権移転登記ができません。したがって、売却前に必ず転用許可を取得し、地目変更を済ませておく必要があります。
④転用面積には制限がある
農地の無秩序な転用を防ぐため、転用できる面積は「必要最小限」に制限されています。事業計画に基づいた合理的な面積設定が求められます。
⑤土地改良区域では除外申請が必要
土地改良区域内の農地を転用する場合、土地改良区からの除外申請と除外金の支払いが必要です。除外が認められないケースもあるため、早めの協議と準備が重要です。
⑥地目変更前は住宅ローンが組めない
農地のままでは、買主が住宅ローンを利用できません。金融機関は農地に対して抵当権を設定しないため、買主が自己資金で造成を行う必要があり、購入希望者が限定される要因となります。
⑦転用しても価格上昇は限定的
農地を宅地に転用しても、必ずしも高値で売却できるとは限りません。造成費用や手続きの煩雑さ、買主側の負担などを考慮すると、宅地と比べて市場価値は相対的に低いままです。農地価格は長期的に下落傾向にあるため、早期の売却判断が有利となる可能性があります。
専門の買取業者へ依頼すべき理由
農地の宅地転用と売却は、法的・行政的な知識と実務経験が求められる高度なプロセスです。適切な専門家の支援を受けながら、計画的かつ段階的に進めることが成功の鍵となります。特に、許可取得のタイミングや契約形態、登記手続きの順序などを誤ると、法的リスクや経済的損失につながるため、慎重な判断が求められます。個人での売却が難しい場合は、専門の買取業者への依頼も選択肢の一つです。専門の買取業者であれば、現金化までの期間が短いだけでなく、一般の不動産仲介業者では取り扱いが難しい物件でも買い取ってもらえる可能性があります。
まとめ
今回は農地を宅地として売却するための手続きや注意点について解説してきました。これらの手続きなどが面倒だと感じる場合は専門の不動産買取業者への依頼も検討してみてください。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することができますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!