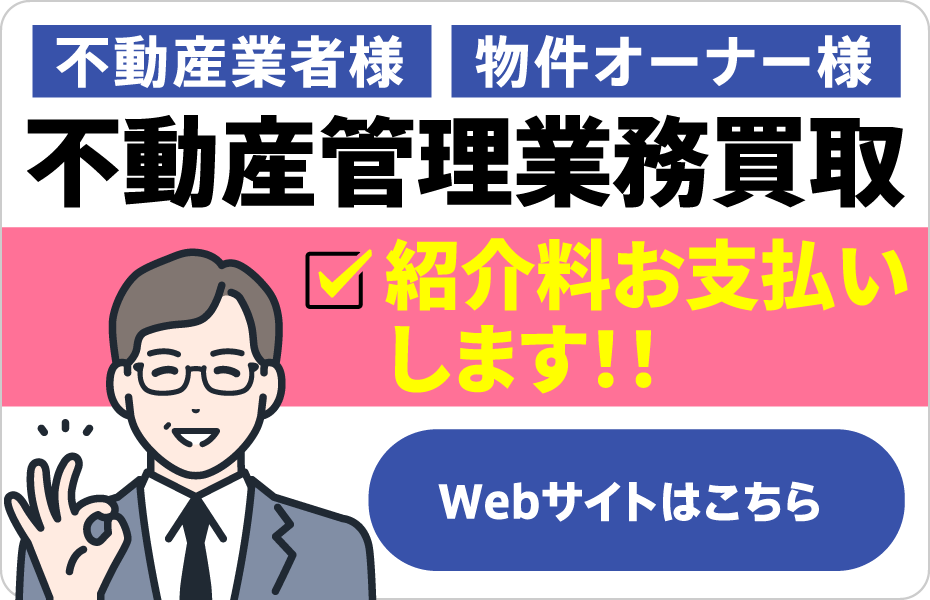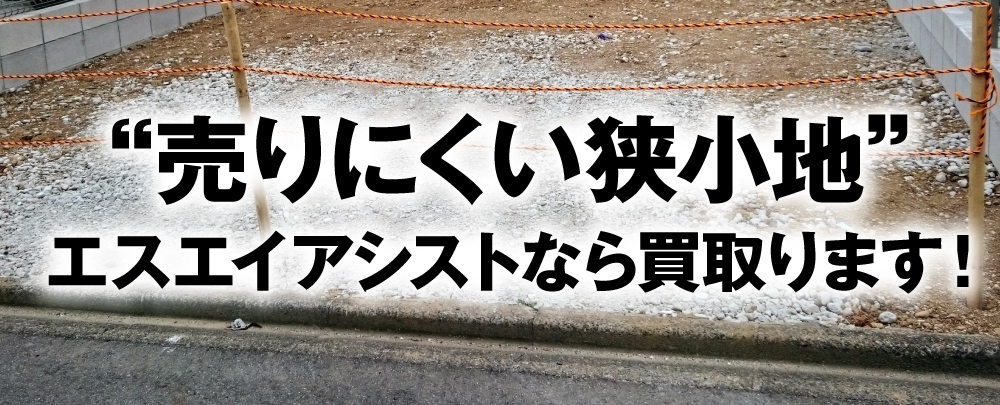
独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!今回は狭小地について解説します。
狭小地とはなにか?
都市部における不動産取引では、「狭小地」や「狭小住宅」といった言葉が頻繁に登場します。これらは不動産業界で一般的に使用される用語ですが、法律上の明確な定義は存在しません。実務上は、敷地面積が20坪(約66㎡)以下、あるいは15坪(約50㎡)以下の土地を指して「狭小地」と呼ぶケースが多く、形状も三角形や台形などの不整形地であることが少なくありません。
狭小地は、特に地価の高い都市部で多く見られます。限られた土地を最大限に活用するため、敷地いっぱいに建物を建てる設計が主流となっており、庭などの外構スペースはほとんど確保されません。建物は床面積を確保するために3階建てとなることが多く、駐車スペースも建物と一体化しているケースが一般的です。
狭小地が売却しづらい理由
①住宅ローンの審査が通りにくい
狭小住宅を建築する際、土地の面積が40㎡以下、あるいは建物の床面積が50㎡以下の場合、金融機関の住宅ローン審査が通りにくくなる傾向があります。これは、金融機関が融資審査において、返済能力だけでなく、担保価値も重視するためです。狭小住宅は一般住宅に比べて担保価値が低いと判断されることが多く、融資のハードルが高くなります。
さらに、住宅ローン減税の適用条件にも「床面積50㎡以上」という要件があるため、税制面でのメリットも享受できない可能性があります。金融機関によっては、土地面積50㎡以上、延べ床面積60㎡以上など、独自の基準を設けている場合もあり、狭小地の流通をさらに難しくしています。
②建築・修繕における制約
狭小地に建てられる住宅は、敷地を最大限に活用するため、建物が土地の境界ギリギリまで建てられることが多く、建築時に足場を組むスペースが確保できないケースがあります。また、道路に面していない土地では重機の乗り入れが困難で、資材の搬入にクレーンが使えず、人力や特殊工法による施工が必要となることもあります。
これらの制約により、建築費用やリフォーム費用が一般住宅よりも割高になる傾向があり、将来的な建て替えや大規模修繕にもコスト面での課題が残ります。
狭小地を売却する方法
①隣地所有者への売却交渉
狭小地の売却において、まず検討すべきは隣接する土地の所有者への売却交渉です。特に、隣地も狭小地である場合や再建築不可物件である場合、土地を一体化することで再開発の可能性が広がり、隣地所有者にとってもメリットが大きくなります。
築年数が近い物件であれば、隣地所有者も売却を検討している可能性があり、同時期に売却することで、より高い評価額での売却が期待できます。交渉が難しい場合は、不動産会社を介して仲介を依頼するのが一般的です。
②専門の買取業者への相談
隣地との交渉に抵抗がある場合や、迅速な売却を希望する場合は、狭小地の取り扱いに特化した買取業者への相談が有効です。これらの業者は、狭小地を再生・商品化するノウハウを持っており、資金調達力も高いため、スムーズな取引が可能です。
専門業者は、狭小地の価値を独自の視点で評価し、再建築不可物件や不整形地でも積極的に買い取るケースが多く、売主にとっては安心して取引を進められる選択肢となります。
まとめ
今回は狭小地について解説してきました。狭小地の売却や活用には一定の制約が伴い、一般の不動産仲介業者へ依頼してもなかなか売却することが難しい可能性があります。もし、迅速に売却したいなどの要望があれば、専門の不動産買取業者への依頼も検討してみてください。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することができますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!