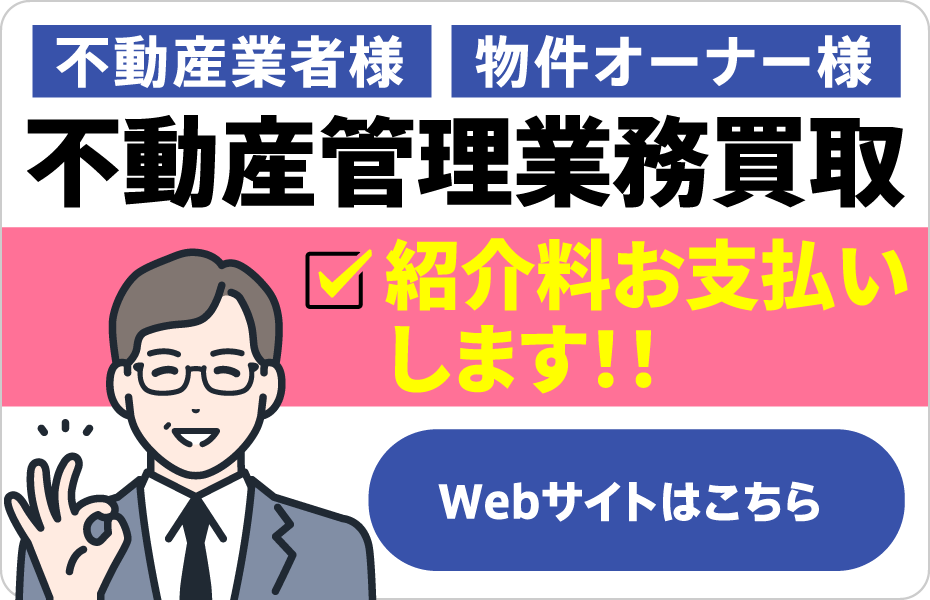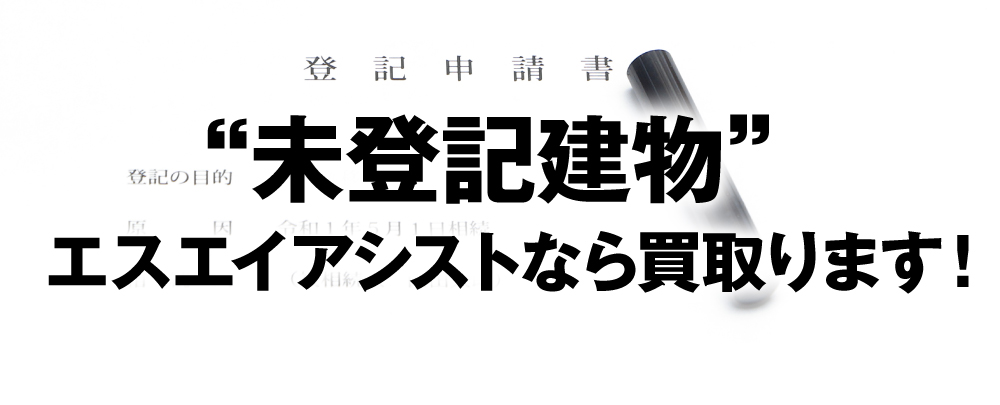
独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!今回は未登記の物件を相続してしまった場合に登記するについて解説します。
登記をしないとどうなる?
登記手続きをせず未登記建物のままにしておくと罰則を受けたり、売却できなかったりと様々なデメリットが発生します。相続登記としても2024年の義務化が始まっており、即属の開始を知った日から3年以内に相続登記をする必要があるため、未登記の物件を相続した場合は思わぬトラブルに巻き込まれないよう登記の手続きを行いましょう。
未登記建物か確認する方法
相続した建物が登記されているか分からない場合は下記の方法で確認しましょう。
・固定資産税や都市計画税納税通知書で確認する
毎年4月頃に送られてくる固定資産税や都市計画税納税通知書に未登記と記載されている場合は未登記建物である可能性が高いです。また、同封されている課税明細書の家屋番号欄に記載がない場合も未登記である可能性が高いです。
・役所や税事務所で確認する
固定資産税・都市計画税納税通知書が手元になく、すぐに確認した場合は、役所で閲覧できる固定資産課税台帳や市税事務所で取得できる家屋公課証明書に家屋番号が記載されているか確認しましょう。
・法務局で確認する
法務局で「全部事項証明書」 の取得申請を行なうことで確認することが出来ます。「全部事項証明書」が存在せず取得できない場合は未登記建物であることが分かります役所や税事務所で確認する方法は同居家族や代理人など確認できる人に制限がありますが、法務局で確認する方法は誰でも取得申請をすることで確認することが出来ます。
登記手続きの方法
先程、説明した内容で登記がされているか確認を取った結果、未登記だった場合、実際にどのように登記手続きを進めなければいけないか説明します。
①遺産分割協議で相続する人を決める
未登記建物を相続した場合は、まず最初に相続する人を決める必要があります。相続人全員参加していない場合は遺産分割協議が無効になってしまうので、連絡の取れない相続人がいる場合は不在者財産管理人の選任をして遺産分割協議に参加してもらうようにしましょう。誰の名義で登記するか決まれば、決まった内容を示す遺産分割協議書を作成します。
②建物表題登記の申請を行う
表題登記とは、登記されていない不動産に対して初めて行う登記のことを指します。所在や構造、床面積などの建物の物理的な情報が記載されており、新築や建て替えなどのタイミングで登記が必要になります。相続した未登記建物の場合、表題登記の名義人は相続人でも被相続人でも構いません。
③建物所有権の保存登記(権利部登記)の申請を行う
権利部の登記とは、不動産に対して所有している権利を第三者へ証明するための登記のことを指します。所有者・権利者の氏名や所在、登記の目的など権利関係においての情報が記載されており、不動産の売買や相続などの際に所有権を明示するために登記します。
未登記物件を売却する方法
未登記物件を売却するためには登記手続きを行ったうえで不動産仲介業者を通して売却するか、専門の不動産買取業者に売却するかになります。自分自身で登記手続きを行うことが出来ないようであれば、一般的な不動産仲介業者に依頼するのではなく、専門の不動産買取業者に依頼しましょう。専門の不動産買取業者であれば、直接売却することが出来るため、素早く現金化することが可能になります。
まとめ
今回は未登記物件の登記手続きについて解説してきました。不動産仲介業者に依頼して売却をしたい場合は登記手続きを個人で実施することも出来ますが、素早く現金化したいなどの希望や手続きが面倒だと思う場合は、専門の不動産買取業者への売却も検討してみてください。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することができますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!