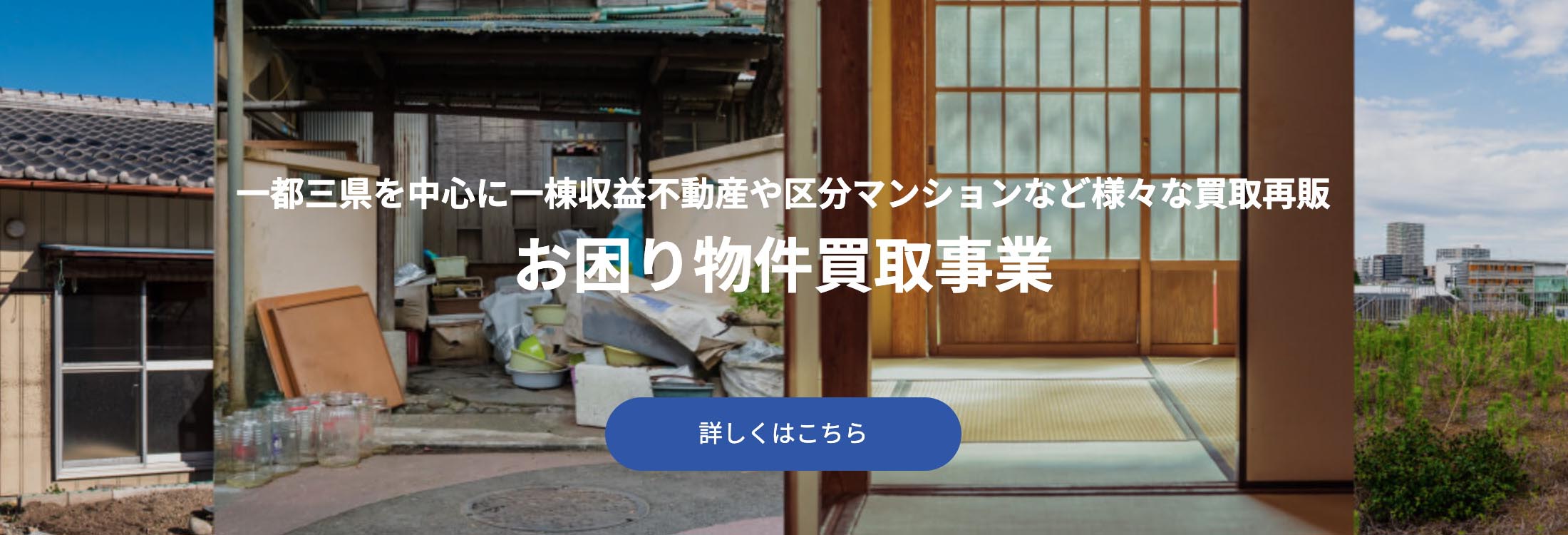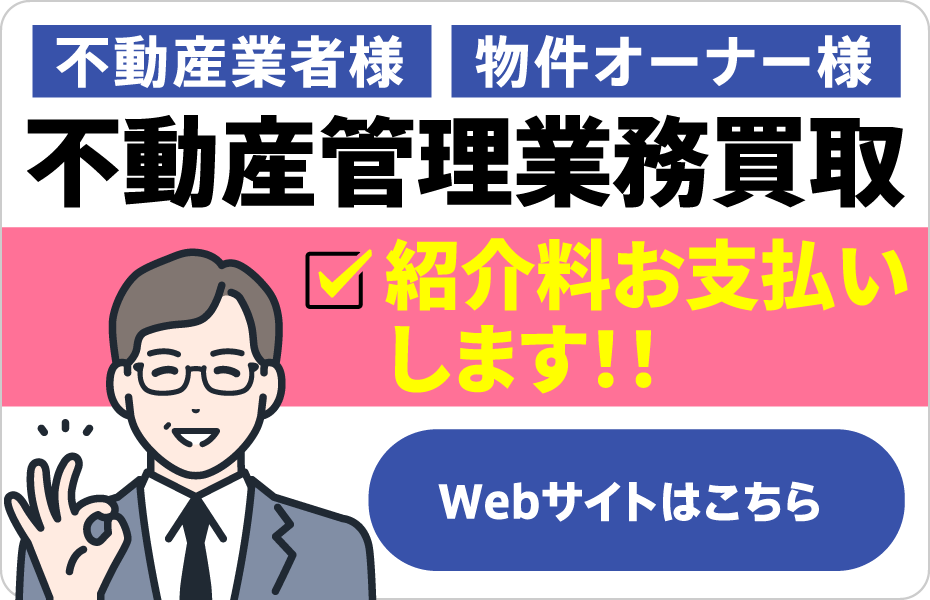独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第99回目は「農地付き空き家の売却」です。
「農地付きの空き家を相続したものの、手続きが分からず放置してしまっている……」こうした声は意外と多いかもしれません。実は、「農地付き空き家」は売却を進めるうえで農地法や農業委員会の許可など、押さえておくべき法律・制度が存在します。さらに、相続登記の義務化や測量、そして補助金などの手続きを把握しなければなりません。
今回の記事では、「農地付き空き家を売りたい!」と考えている人に向けて、法律や税金の概要から、農地転用や空き家バンク、さらに不動産買取業者を利用する際のメリットまで、詳しくご紹介。最後まで読んでいただくことで、スムーズな物件売却を実現するための一連の流れが、きっと見えてくるハズです!
農地付き空き家を売りたい人が知るべき全体像!

まず、「農地付き空き家」とは、「敷地内に宅地部分と農地(登記上の地目が「田」「畑」「山林」「原野」など)が一緒になっている空き家不動産」を指します。通常の宅地不動産と違い農地があるだけで、その扱いに制約が伴います。たとえ現状では耕作していなくても、地目が農地扱いであれば多くの規制を受けることになり、不動産売却には考慮すべき事項が増えることになります。
そんな農地付き空き家の特徴は以下のようなものがあります。
①農地法の影響
はじめに、農地は一般的な土地と違い、農地法での厳しい管理の影響下にあります。この農地法は、農地の保全と適切な利用をさせることを目的としたもので、不動産売却や農地転用には農業委員会の許可が必要になります(詳細は後述します)。
②そのままでは売却先が限定される
もし農地を農地のままで売ろうとすると、原則として買主さんは農業を継続できる人(農家)に限定されます。一方で農地転用する場合は、個人・法人など農家以外の層にも広くアプローチできますが、転用許可には一定の条件をクリアする必要があります。
③地域の規制によっては売りやすさが変わる
また、宅地化を抑制しているエリアだと農地転用が厳しく、売却そのものが難航するケースもあります。その逆に、市街地に近い農地ほど転用しやすい傾向にあり、地域の規制によっては売りやすさが変わることに!
これらのことから、「何か面倒くさそう…」「売却は諦めるしかない…」と考えてしまう人も多いかもしれませんが、それによって農地付き空き家を長期間放置してしまうと、固定資産税などの負担や、建物の老朽化、農地の荒廃といったリスクが発生してしまいます。
であるので、ともかくは「法律面での手続きを知ること」が大変重要となり、そこを押さえておけば農地付き空き家でも売却できるチャンスが十分にあります。
押さえるべき農地法とは?
ここからは、最も基本となる法制度について解説していきます。農地付き空き家を売る場合、農地法を理解せずに進めるのは困難です。
「農地法」とは、「農地を無秩序に宅地化させないよう保護すると同時に、耕作できる土地を確保し食料自給率を維持するための法律」であり、土地の利用規制です。国からすれば、日本の食料自給率に大きく関わる農地は特別に重要な土地であるため、農地所有者さんに自由に取引や管理できる状況は好ましくはありません。農地法によって売却や農地転用を禁じて、日本国内の農地が減少してしまうリスクから、農地を守っているということです。
農地法は国の法律であり、違反すれば罪に問われます。
・懲役刑と罰金刑:違反すれば、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられる
・現状回復:違反して農地転用して売却した場合、農地を元に戻さなくてはならない
といった重い罰を受けなくてはならないため注意が必要です。
具体的には、農地の所有者さんが変わる(不動産譲渡する)場合や農地転用する場合に、農業委員会や都道府県知事などの許可を受ける仕組みとして、特に以下の3つの許可区分を規定しています。
①農地法3条許可
・内容:農地を農地のまま売買や貸借する
・ポイント:買主が農業を継続する意思・能力を持っているかどうかが審査
・注意点:買主が「農家であるか」「営農計画があるか」を確認しないと許可がおりにくい
②農地法4条許可
・内容:自分が所有している農地を宅地などに転用する
・ポイント:(売却・譲渡ではなく)転用許可を得て別の用途に使いたい場合
・注意点:将来的に農地転用して売却するのであれば、4条許可だけでは不十分
③農地法5条許可
・内容:農地の売却と同時に、買主が宅地や商業用地などに用途を変更する
・ポイント:農地付き空き家の売却では、最も適用頻度が高い許可区分
・注意点:転用許可されない地域(市街化調整区域など)だと不許可になりやすい
多くの場合は、農地法5条許可を得ることで、農地を宅地などに転用して農家以外に売却することを考えることになります。もし農地転用できれば、宅地並みの売却価格が期待できますが、それには転用するための手続きが煩雑な上、場所によって農地転用できるとは限らないんですね。
農地を宅地転用するための基準とは?
ということで、農地付き空き家を売却するためには、農地を宅地転用できるかがポイントになりますが、そのための重要な基準が2つあります。
①一般基準
農地の宅地転用によって、「周りの農地に悪い影響はないか」「宅地転用に確実性はあるか」などを確認する「一般基準」があります。それは、住宅を建てるにあたって、適した敷地の広さがあり十分な建築資金はあるかを確認される基準になります。
この一般基準には、「農地の宅地転用の許可が下りたら、すぐに建築に向けて行動する」ことが必要になります。そのため、「将来的に建築することが出来るように転用だけ済ませておく」というのでは認めてもらえません。ただその点、本気で宅地に変えて建物を建てたい人にとっては、問題にはならないかもしれませんね。
②立地基準
その一方で、この「立地基準」の方が、問題があれば解決は難しいです。何故なら宅地転用したい農地が、「どのようにして利用されている農地なのか」「周辺の市街地化がどれくらい進んでいる地域か」によって、ほぼ結果が決まってしまうからです。
立地基準は、以下の5区分に分類されます。
・農用地区区域内農地と甲種農地と第一種農地:
重要な農業地帯として保護されているため、転用は原則不可
・第二種農地:
周辺状況や既に宅地が点在しているかなどを総合的に判断するため、転用は条件付きで一部許可の可能性あり
・第三種農地:
市街地化が進んでいる地域にあり、農地としての優先度が低いとみなされる場合が多いため、転用は原則許可
最後2つの第二種・第三種農地については、駅や官公庁のある地域に近いなど、市街地の傾向が強いとの理由から、農地転用の許可が降りる可能性が高いと言えます。
農業委員会への問い合わせがスタートライン?

では、自身の所有する農地が、5つの区分の内でどれに該当するのかを、どうやって確認すれば良いでしょうか?農地の売却や転用を行う際に必ず関わってくるのが、各自治体の「農業委員会」です。
農地を宅地転用するなら、この農業委員会への問い合わせがスタートラインになります。農地法の許認可や地域の農業施策を担っており、具体的には申請書類の受理から審査まで行い、住民の農地転用や不動産売買をチェックする仕組みとなっています。
であるので、農地付き空き家を売りたいなら、最初に農業委員会に行って「農地転用予定だが可能か」「買主が農地を続ける必要はあるか」といった部分を早めに確認しておくことは、不許可リスクを下げるうえでも非常に有効です。また、実際に売却活動を始めるに当たり、
・許可の可否はもちろん、審査期間の目安を教えてもらえる
・書類不備や見落としが減り、スムーズに申請ができる
・自治体独自のルールや事業者向け支援策などの情報を得られる場合もある
といったメリットがあるので、事前に確認しておきましょう。
その上で、農地付き空き家の農地を宅地転用して、不動産売却するための具体的な手順は以下のように進めます。
売却を不動産業者に依頼する:農地法や転用手続きの知識がある業者を選ぶ
↓
農地転用の許可申請をする:必要書類を揃えて提出
↓
売買契約を締結する:許可前に仮契約として締結することが多い
↓
買主が仮登記する:転用許可が下りるまでの間、法的リスクを減らすための措置
↓
許可後に本登記と精算をする:農地法5条許可がおりた段階で、正式に売買取引を完了
スムーズな売却に欠かせない準備とは?
ここまで、法律面の大枠を把握してきましたが、売却を実際に進めるにはさらにいくつかの手続きが必要です。ここでは、相続登記・譲渡所得税・測量の3つをピックアップして解説します。
①相続登記
ひとつに、相続した農地付き空き家を売却する場合、名義が被相続人のままだと売却契約が成立しません。まして、2024年4月に相続登記は義務化されているので、放置すると過料を科される可能性も出てきました。そのため、しっかりと登記を行っていきたいところ。
法定相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成し、誰がその空き家・農地を相続するのか確定させておく必要があります。
②譲渡所得税と住民税
つぎに、不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。譲渡益は売却額から取得費や経費を差し引いた金額になるため、可能であれば過去の契約書などの関係書類の確認をしておきます。
税金は不動産所有期間によって、5年以下だと「短期譲渡所得」、5年超で「長期譲渡所得」と区分され、税率が大きく異なることになります。ただ、相続によって取得した場合は、被相続人(亡くなった人)さんの取得時期を引き継ぐルールがあるため、多くは長期譲渡に該当することになるでしょう。
③測量や境界確定
さらに、農地付き物件は土地面積が広い場合が多く、隣地との土地の境界が不明瞭なケースも多いものです。これでは、買主さんは安心して不動産購入できませんし、金融機関も測量図や境界確認がない土地に対しては融資をしぶる傾向があります。
一方で測量を実施して境界確定を行うことで土地の権利関係をはっきりさせれば、トラブルを避けつつより高値で売却できる可能性が高くなります。境界確定測量には、時間や手間、数十万〜百万円程度かかるため、検討するなら早い方が良いでしょう。
加えて、農地付き空き家の解体やリフォームにかかる費用の一部を、国や自治体がサポートしてくれる制度も存在するので確認しておきましょう。代表的な補助金と助成金には、以下のようなものがあります。
・空き家対策総合支援事業:空き家の取得費や改修費等についての支援
・農地利用効率化等支援交付金:農地の利用効率化を図るための支援
・荒廃農地等利活用促進交付金:荒廃農地等を引き受けて耕作を再開することを支援
その他、「老朽空き家解体補助」や「耐震リフォーム助成金」などがあり、具体的な適用条件や申請方法は各制度によって違い、そして制度自体の変更等もあるため、最新の情報を各自治体や関係各所に確認することが大切です。
複数の売却ルートを知ろう!
さいごに、実際に農地付き空き家の売り方を選ぶために、いくつかの選択肢を比較していきます。自分の目的や状況に合った売却ルートを選ぶことが大切です。以下では、農地を含む不動産売却で注目される代表的な方法を複数解説します。
①不動産仲介によって売却
農地売却による売却の最もオーソドックスな方法が「不動産仲介」です。それは、地元の不動産業者さんやインターネットを通じて、一般の買主さんを探してもらいます。
メリット:
・市場価格に近い水準で売却できる
・リフォームやクリーニングを行えば高値でも売れる可能性がある
・不動産業者が広告や交渉を代行するため負担が軽減される
デメリット:
・農地法や農地転用のノウハウのない不動産業者だと手続きに手間取る
・買主が見つかるまで時間や手間がかかる場合がある
・仲介手数料がかかる(売却価格の約3%+6万円が目安)
もし仲介で売却するなら、農地付き空き家の取り扱い経験のある業者選びが重要です。農業委員会や行政との連携の必要があるため、最初の段階で「農地付き空き家にも対応できるか」を確認しておきます。
②空き家バンクの活用
つぎに、自治体が運営する「空き家バンク」を活用するのも一つの方法です。空き家バンクを上手に使うことで、とりわけ農地付き空き家は「新規就農」「セカンドライフに自然を感じたい」などのニーズを汲めるかもしれません。一般的な宅地よりも興味を持ってもらえるケースもあり得るからです。
メリット:
・登録や利用が無料または低コストの自治体が多い
・一定の条件下で非農家でも取得の可能性がある(取得条件の緩和)
・自治体の担当者がマッチングをサポートしてくれる場合がある
デメリット:
・希望者がすぐに現れるとは限らない(成約まで時間が読めない)
・売却までの間は管理維持の継続しなくてはならない
・農地転用が必須なら買主によっては手続きが複雑になる
こうした空き家バンク経由で、「こういう物件を探していた!」と喜ばれるケースもあるため、少しでも広くアピールしたいなら登録を検討するといいです。ただし、転用手続きや税金・測量などは通常通り必要になる点には変わりありません。
③不動産買取によって売却
さいごに不動産買取なら、業者さんが直接物件を買い取る仕組みです。農地付き空き家の場合でも、農地転用や農地法の許可申請などを業者さんがサポートしてくれるケースも多く、専門知識のない個人でも安心して進められるのが強みです。
メリット:
・直接取引で売却活動を省略できるため、仲介手数料が不要で早期現金化できる
・測量や境界確定の手配、農業委員会との折衝などをサポートしてもらえる
・リフォーム不要で現状のままでも売却後に問題が起きづらい
デメリット:
・仲介より売却価格が低くなりやすい
・買取業者が農地法に精通していない場合、トラブルが起こる可能性がある
・業者選びに注意が必要である
ここまで、農地付き空き家の売却について、必要な準備や制度を押さえてきましたが、「いろいろとやることが多すぎて、どうしても気が重い」「とにかく早く売りたい」という方も少なくないでしょう。そんなときは「不動産買取」という選択肢が有力になります。複数の買取業者さんに査定を依頼し比較することで、より納得のいく条件が得られるでしょう。
まとめ
今回の記事では、農地付き空き家の売却を考えている人に向けて、法律や税金の概要から、農地転用や空き家バンク、さらに不動産買取業者を利用する際のメリットまで、詳しくご紹介してきました。
まず、「農地付き空き家」とは、「敷地内に宅地部分と農地が一緒になっている空き家不動産」を指し、多くの規制を受けることになるため、不動産売却には考慮すべき事項が増えます。
そんな農地付き空き家の特徴は以下のようなものがあります。
①農地法の影響
②そのままでは売却先が限定される
③地域の規制によっては売りやすさが変わる
これらを面倒に感じて農地付き空き家を長期間放置してしまうと、多くのリスクが発生してしまいます。そのため売却をすることが得策ですが、農地付き空き家を売る場合、農地法を理解せずに進めるのは困難です。
「農地法」とは、「農地を無秩序に宅地化させないよう保護すると同時に、耕作できる土地を確保し食料自給率を維持するための法律」であり、土地の利用規制です。国は農地法によって売却や農地転用を規制して、日本国内の農地を守っています。農地法は国の法律であり、違反すれば罪に問われます。
農地転用する場合には、農業委員会や都道府県知事などの許可を受ける仕組みとして、特に以下の3つの許可区分を規定しています。
①農地法3条許可(農地を農地のまま売買や貸借する)
②農地法4条許可(自分が所有している農地を宅地などに転用する)
③農地法5条許可(農地の売却と同時に、買主が宅地や商業用地などに用途を変更する)
農地法5条許可を得て農家以外に売却することができれば、宅地並みの売却価格が期待できますが、転用するための手続きが煩雑な上、場所によって農地転用できるとは限りません。
農地を宅地転用するための重要な基準が2つあります。
①一般基準:「周りの農地に悪い影響はないか」「宅地転用に確実性はあるか」
②立地基準:「どのようにして利用されている農地なのか」「周辺の市街地化がどれくらい進んでいる地域か」
立地基準は、以下の5区分に分類されます。
・農用地区区域内農地と甲種農地と第一種農地:転用は原則不可
・第二種農地:転用は条件付きで一部許可の可能性あり
・第三種農地:転用は原則許可
第二種・第三種農地については、市街地の傾向が強いとの理由から、農地転用の許可が降りる可能性が高いと言えます。
農地の売却や転用を行う際には、農地法の許認可や地域の農業施策を担う各自治体の「農業委員会」への問い合わせをします。「農地転用予定だが可能か」「買主が農地を続ける必要はあるか」と早めに確認しておくことは、不許可リスクを下げるうえでも非常に有効です。
売却を実際に進めるには、相続登記・譲渡所得税・測量の3つの手続きなどが必要です。
①相続登記:遺産分割協議書を作成し、誰がその空き家・農地を相続するのか確定させる
②譲渡所得税:譲渡益は売却額から取得費や経費を差し引いた金額になるため過去の契約書などの関係書類の確認する
③測量や境界確定:隣地との土地の境界が不明瞭なら測量により確定させる
加えて、農地付き空き家の解体やリフォームにかかる費用の一部を、国や自治体がサポートしてくれる制度も存在するので確認しておきましょう。
さいごに、実際に農地付き空き家の売り方を選ぶために、いくつかの選択肢を比較していきます。自分の目的や状況に合った売却ルートを選ぶことが大切です。
①不動産仲介によって売却
メリット:市場価格に近い水準で売却できる・リフォームやクリーニングを行えば高値でも売れる可能性がある・不動産業者が広告や交渉を代行するため負担が軽減される
デメリット:農地法や農地転用のノウハウのない不動産業者だと手続きに手間取る・買主が見つかるまで時間や手間がかかる場合がある・仲介手数料がかかる(売却価格の約3%+6万円が目安)
②空き家バンクの活用
メリット:登録や利用が無料または低コストの自治体が多い・一定の条件下で非農家でも取得の可能性がある(取得条件の緩和)・自治体の担当者がマッチングをサポートしてくれる場合がある
デメリット:希望者がすぐに現れるとは限らない(成約まで時間が読めない)・売却までの間は管理維持の継続しなくてはならない・農地転用が必須なら買主によっては手続きが複雑になる
③不動産買取によって売却
メリット:直接取引で売却活動を省略できるため、仲介手数料が不要で早期現金化できる・測量や境界確定の手配、農業委員会との折衝などをサポートしてもらえる・リフォーム不要で現状のままでも売却後に問題が起きづらい
デメリット:仲介より売却価格が低くなりやすい・買取業者が農地法に精通していない場合、トラブルが起こる可能性がある・業者選びに注意が必要である
農地付き空き家の売却について、「どうしても気が重い」「とにかく早く売りたい」というときは「不動産買取」という選択肢が有力になります。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々と解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較して頂ければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。