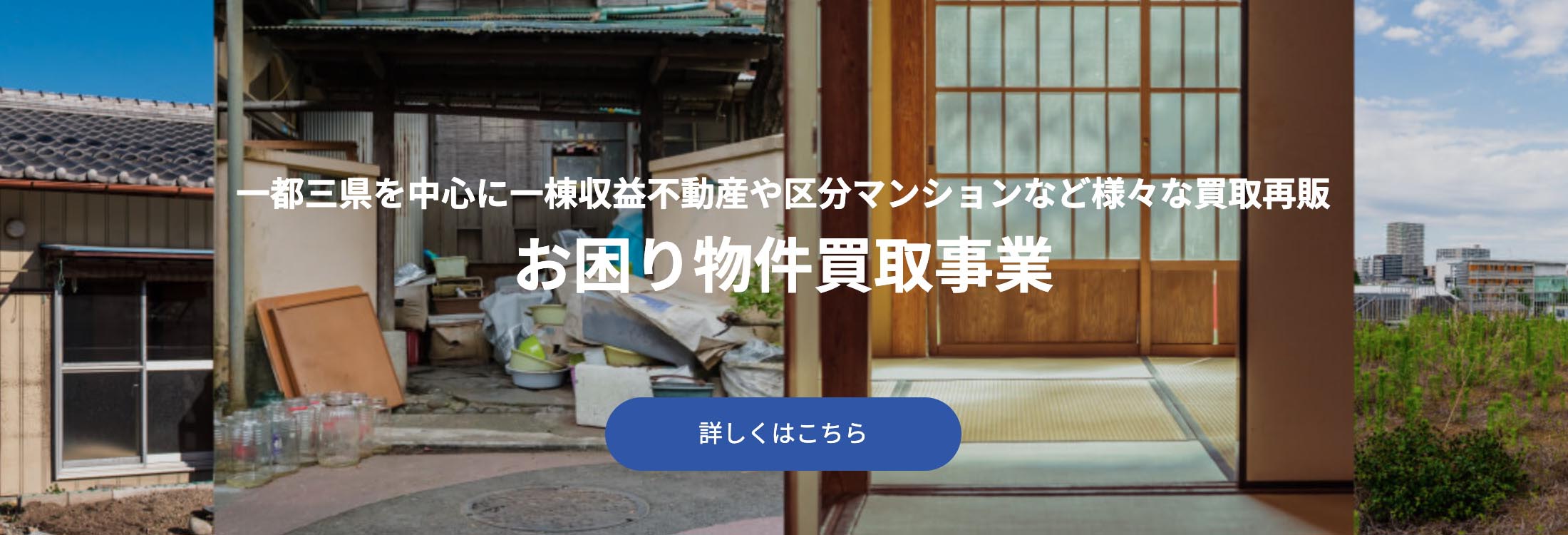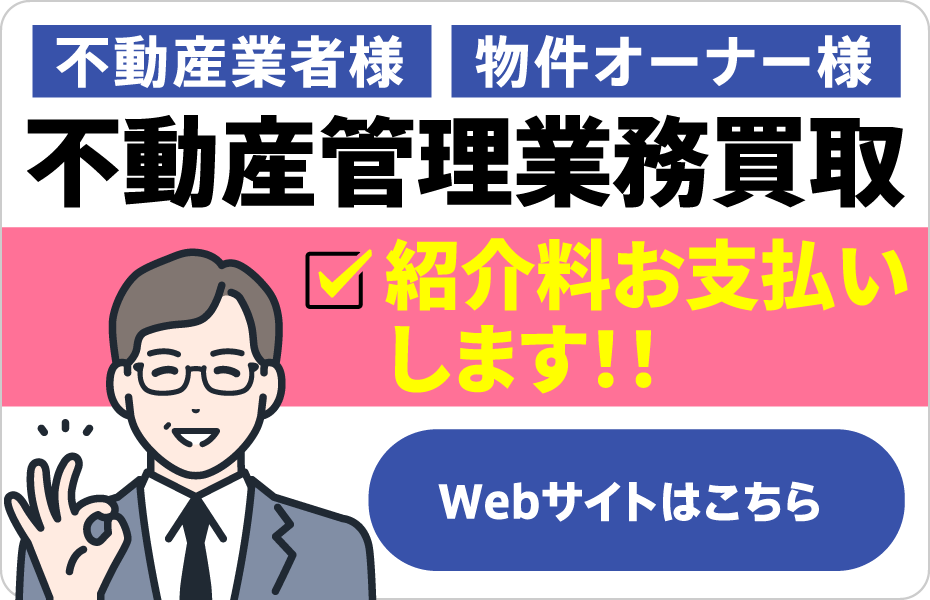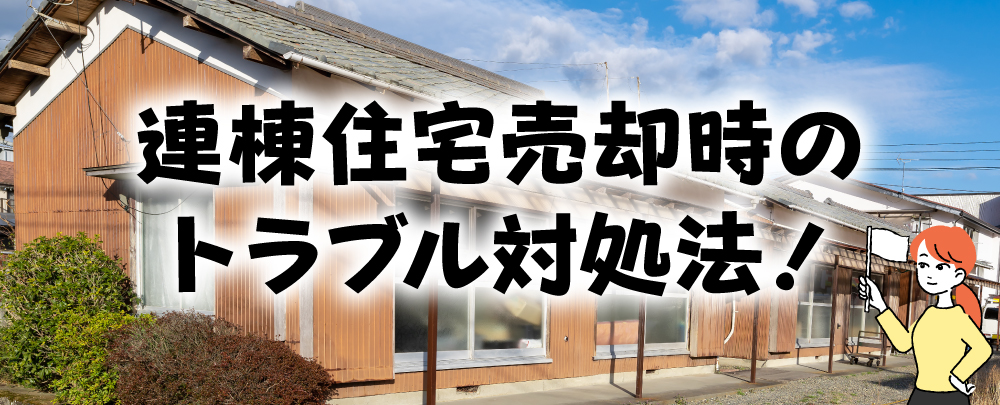
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第96回目は「連棟住宅の売却」です。
「連棟住宅を売却したいけど、隣人との関係性が心配…」「境界線が曖昧だけど、このまま売っても大丈夫?」このような不安を抱えていませんか?連棟住宅(いわゆる長屋)は、隣接する住戸と壁を共有する構造のため、不動産売却時には特有の問題が生じます。特に境界トラブルは、その問題を解決しないまま売却を進めると、思わぬ責任問題になりかねません!
今回の記事では、連棟住宅の売却に起きやすいトラブルと、「売却で失敗しない!」ための対処法を分かりやすく解説します。連棟住宅の売却は難しいと言われますが、適切な準備や対処法を知ればスムーズに進めることも可能です。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
連棟住宅(長屋)とは?

はじめに、連棟住宅がそもそもどのような建物で、どんな特徴があるのか確認しましょう。「連棟住宅」とは、「複数の住戸が壁を共有して連続的に建てられている住宅」のことを指し、いわゆる「長屋」とも言われます。その特徴からくるメリットとデメリットには以下が挙げられます。
メリットとして、
・建築コストが低い:共用部分があるため、一戸建てを比べて建築費用を抑えられる
・コミュニティの形成:隣人との距離が近いため、良好な関係が築きやすい
・防犯効果が高い:近隣住民の目が届きやすく、不審者の侵入を防ぎやすい
・資源の効率的活用:限られた土地やインフラを有効活用できる
デメリットとして、
・壁の共有:隣接住戸と壁を共有しているため、音や振動が伝わりやすい
・土地の分割が困難:土地の境界線の多くが壁芯にあり、単独での売却や解体が難しい
・維持管理の問題:共有部分の(壁や屋根)の維持管理に隣人との合意が必要
・火災のリスク:火が広がりやすいため、万が一の際に被害が拡大しやすい
・プライバシーの確保が難しい:近隣住戸と接しており、生活が筒抜けになりやすい
似た言葉で「テラスハウス」と「タウンハウス」というものがありますが、テラスハウスは連棟住宅(長屋)とほぼ同義であり、開口部のない壁以外は土地を含めて共有せず、土地もそれぞれの占有として分かれています。一方で、タウンハウスは集合住宅同様に土地を共有しており、区分所有になります。そのため、今回の記事では、タウンハウスは考慮しないものとします。
そんな連棟住宅の売却相場と不動産市場での評価は以下のようになります。
・一般的な一戸建てと比較して市場価格が低くなる傾向がある
・立地条件や建物の状態によって価格が大きく変動する
・老朽化した連棟住宅は、その管理の難しさから特に価格が下がる可能性がある
連棟住宅の売却が難しい理由とは?
そんな連棟住宅は他の不動産にはない特有の問題があり、不動産売却が難しいと言われています。その理由は以下の通り。
①共有壁の問題
ひとつに、先述したように隣接住戸と壁を共有しているため、遮音性が低く、プライバシーの確保が難しいことです。また、この共有壁の所有権が不明確な場合もある上、その修繕や改修を行う際には隣人さんの合意が必要となります。そのため、手続きが複雑になる可能性があります。
②土地の境界線が曖昧
つぎに、連棟住宅は長年にわたって隣接住戸と密接に関係しているため、壁の所有権がはっきりしないことと同様に、土地の境界線がどこにあるのか不明確になっていることがあります。これは不動産売却時に問題となり、境界確定測量などの手続きが必要になるケースがあります。
③住宅ローンを組みづらい
そして、連棟住宅は金融機関からの担保評価が低く見なされることが多く、住宅ローンの審査が厳しく組みづらい傾向にあります。そのため、購入希望対象者が減少するので、不動産売却は困難になります。
④既存不適格物件である可能性
さらに、古い連棟住宅では、これまでの建築基準法の改正によって、現行法に適合しない既存不適格物件である可能性があります。これによって、大規模な改修や建て替えが大きく制限され、売却後の利用に影響がでるため、物件としての魅力が低下します。
⑤再建築不可物件である可能性
さいごに、連棟住宅は単独での再建築が難しいことがあります。所有の土地が接道義務(前面道路に2m以上敷地が接していなければならない義務)を果たしていない場合、建築許可が下りません。
これらの理由により、連棟住宅の不動産売却は、一般戸建てに比べて難しいと言わざるを得ません!
連棟住宅の売却時に起こりやすい隣人との境界トラブルとは?
もし将来的に連棟住宅の売却を考えたとして、隣接住戸の隣人さんとの間で起こりやすいトラブルがあります。
①共有壁や共有設備のトラブル
まず、売却に先立ってリフォームを考えた際に、共有壁の修繕費用や費用負担割合を巡って、隣人さんとの争いが起こりやすいと言えます。それは、給排水設備やガス管、電気配線においても共有があれば、同じことが言えます。隣人さんとの協議から合意は必要不可欠であり、意見の相違があればいつまでも工事に着手できなくなります。
②境界未確定のトラブル
つぎに、隣接住戸との土地の境界線が明確でないこと。境界確定されていないと、売却後に新しい所有者さんと隣人さんとの間で紛争が発生する可能性が高まります。当然、売主さんは責任を問われるため、事前に正式な境界確定測量を行うことが望ましいです。その際には、全ての関係者さんを集めての立会いが必要であるため、調整に時間がかかる上に費用もかかります。
③越境物のトラブル
そして、例え境界確定ができたとしても、続けて越境物の取り扱いを通してトラブルになることもあります。それは多くの場合、共有壁の中心線に境界が決まってしまうので、壁や柱の半分が越境することになります。こうなってくると、新たに新築するなら、その半分の土地を隣人さんに買ってもらうか譲るかをしなくてはなりません。また、敷地が小さくなること、境界からセットバックして新築すること、現法の建ぺい率や容積率を守らなくてはならないことから、必然的に新築可能面積は小さくなります。
連棟住宅の「売却で失敗しない」ための対処法!

では、起こりやすいトラブルを理解した上で、連棟住宅を少しでも高く不動産市場で売却するための対処法を確認します。
①境界確定測量を実施する
先述しましたが、連棟住宅の売却では隣人との関係や境界問題をしっかり解決しておくことが、スムーズな売却に繋がります。まずは測量士さんに依頼し、公図を確認して法的な土地情報をもとに境界確定測量を実施します。その際には、隣人さんを含めた関係各所との立ち会いのもと境界を明確にした上で、境界標を打って確定します。これにより、将来的なトラブルを回避でき、買主さんにとっても安心材料になります。
②売却前のリフォーム・修繕を考える
そして、連棟住宅の価値を高めるために、売却前のリフォームや修繕の検討をします。特に重要なのは共有壁周りです。例えば、共有壁の防音材や天井裏の空間を塞ぐなどの工事を行うことで、プライバシーの確保や生活音が響くことへの問題を軽減できます。ただし、過度なリフォームは費用がかかる割に売却価格に反映されにくいことや、工事には隣人さんの同意が必要になります。さらに、そもそも建物自体を分割し取り壊す可能性もあるため、よくよく費用対効果を判断する必要があります。
③隣人への売却交渉を試みる
また、隣人さんへの売却交渉を試みるのも一つの方法です。連棟住宅の所有者同士で売却を進めることで、権利関係が整理されやすくなり、スムーズに売却できる可能性もあります。隣人さんにとっても悪い話ではなく、土地が広くなり活用の自由度が高まります。ときに、ともに売却活動に繋がることもありえます。もし、直接の交渉が難しい場合は、不動産業者さんや弁護士さんといった第三者の介入によって好転する場合もあります。
④連棟住宅の切り離し売却の可否
さらには、連棟住宅の一部を単独に売却できるか、切り離し売却の可否を事前に確認することも重要です。建築基準法や自治体の規制によっては、建物の構造上、事実上の切り離し工事が出来ないケースもあります。ときに、境界確定後の越境物の扱いを巡って、土地を分割して売却するケースでは、法的な手続きとして分筆登記が必要になります。
連棟住宅を売却するための最適な方法!
それらの対処法を実施して問題が解決するかしないかで、連棟住宅を売却するための最適な方法は分かれます。売却方法の選択によって、得られる利益や売却のスムーズさに違いが出るため、慎重に検討しましょう。
①問題解決して一般の不動産市場での売却を目指す!
ひとつに、境界問題や共有壁の管理問題を解決し、売却に適した状態に整えられた場合は、不動産仲介を利用して一般の不動産市場で売却する方法を選択できます。この方法は、適正な価格で売却できる可能性が高くなります。
そのデメリットとメリットは以下。
デメリット:
・売却までに時間がかかる可能性がある
・仲介手数料がかかる
・難しい物件であるのは変わらないので買い手が見つからないことがある
メリット:
・適正な市場価格で売却できる可能性が高い
・複数の買主候補から選択できる
②問題解決が難しく不動産買取業者を利用し売却を目指す!
つぎに、隣人さんとの関係や境界問題、再建築不可などの理由からスムーズに売却できない場合は、不動産買取を利用するのが適した選択肢になります。不動産買取であるなら、一般の買主さんが敬遠するような物件でも買い取ってくれるため、迅速な現金化が可能です。
そのデメリットとメリットは以下。
デメリット:
・一般市場価格よりも低い売却価格になる可能性が高い
・買取業者の選定が難しい
メリット:
・業者との直接取引のため確実に売却できる
・仲介手数料が不要のため手残り金額が明確
・物件の状態や問題点に関わらず買取してもらえる
まとめ
今回の記事では、連棟住宅の売却に起きやすいトラブルと、売却で失敗しないための対処法を分かりやすく解説してきました。
はじめに、「連棟住宅」とは、「複数の住戸が壁を共有して連続的に建てられている住宅」のことを指し、いわゆる「長屋」とも言われます。
メリットとして、建築コストが低い・コミュニティの形成・防犯効果が高い・資源の効率的活用があります。
デメリットとして、壁の共有・土地の分割が困難・維持管理の問題・火災のリスク・プライバシーの確保が難しいことがあります。
似た言葉で「テラスハウス」は、連棟住宅(長屋)とほぼ同義であり、開口部のない壁以外は土地もそれぞれの占有として分かれている一方で、「タウンハウス」は集合住宅同様に土地を共有しており、区分所有になります。
そんな連棟住宅の売却相場と不動産市場での評価は以下のようになります。
・市場価格が低くなる傾向がある
・状況によって価格が大きく変動する
・老朽化した連棟住宅は特に価格が下がる可能性がある
そんな連棟住宅は、不動産売却が難しいと言われています。その理由は以下の通り。
①共有壁の問題
②土地の境界線が曖昧
③住宅ローンを組みづらい
④既存不適格物件である可能性
⑤再建築不可物件である可能性
連棟住宅の売却時に起こりやすい隣人さんとのトラブルがあります。
①共有壁や共有設備のトラブル
②境界未確定のトラブル
③越境物のトラブル
では、連棟住宅を少しでも高く不動産市場で売却するための対処法は以下。
①境界確定測量を実施する
②売却前のリフォーム・修繕を考える
③隣人への売却交渉を試みる
④連棟住宅の切り離し売却の可否
それらの対処法を実施して問題が解決するかしないかで、連棟住宅を売却するための最適な方法は変わってきます。
①問題解決して一般の不動産市場で適正な価格の売却を目指す!
デメリット:
・売却までに時間がかかる可能性がある
・仲介手数料がかかる
・難しい物件であるのは変わらないので買い手が見つからないことがある
メリット:
・適正な市場価格で売却できる可能性が高い
・複数の買主候補から選択できる
②問題解決が難しく不動産買取業者を利用し売却を目指す!
デメリット:
・一般市場価格よりも低い売却価格になる可能性が高い
・買取業者の選定が難しい
メリット:
・業者との直接取引のため確実に売却できる
・仲介手数料が不要のため手残り金額が明確
・物件の状態や問題点に関わらず買取してもらえる
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々と解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較して頂ければと思います。連棟住宅のような難しい物件をお持ちの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。