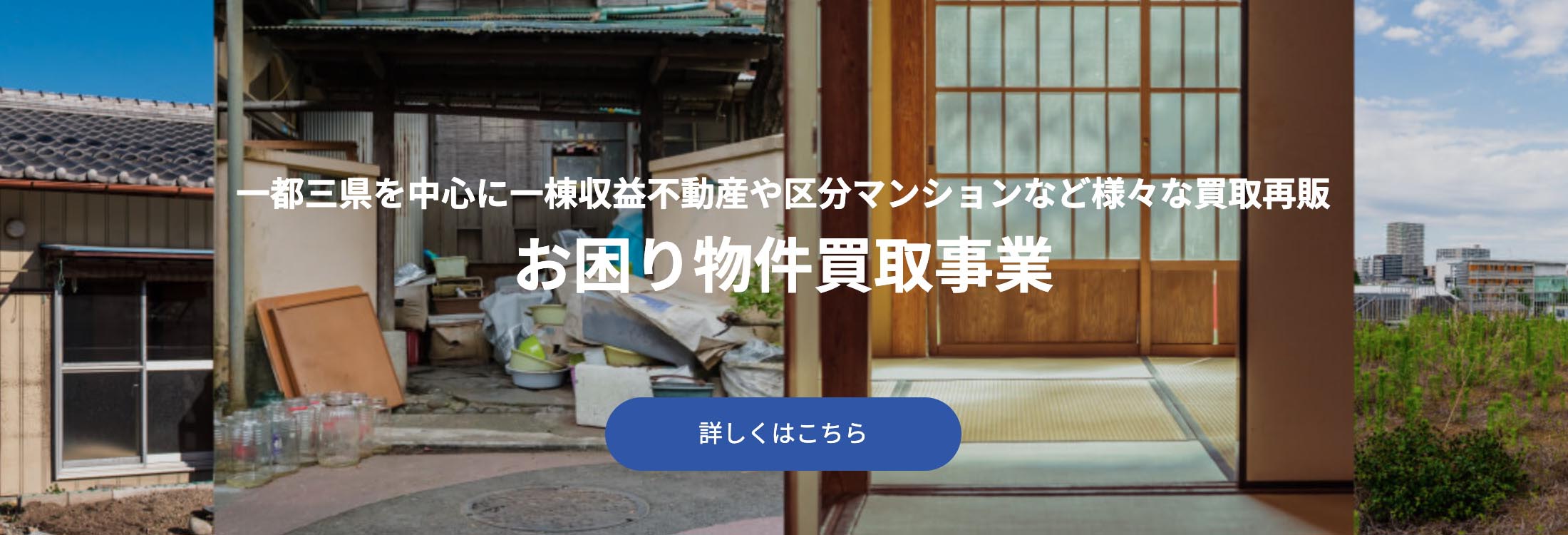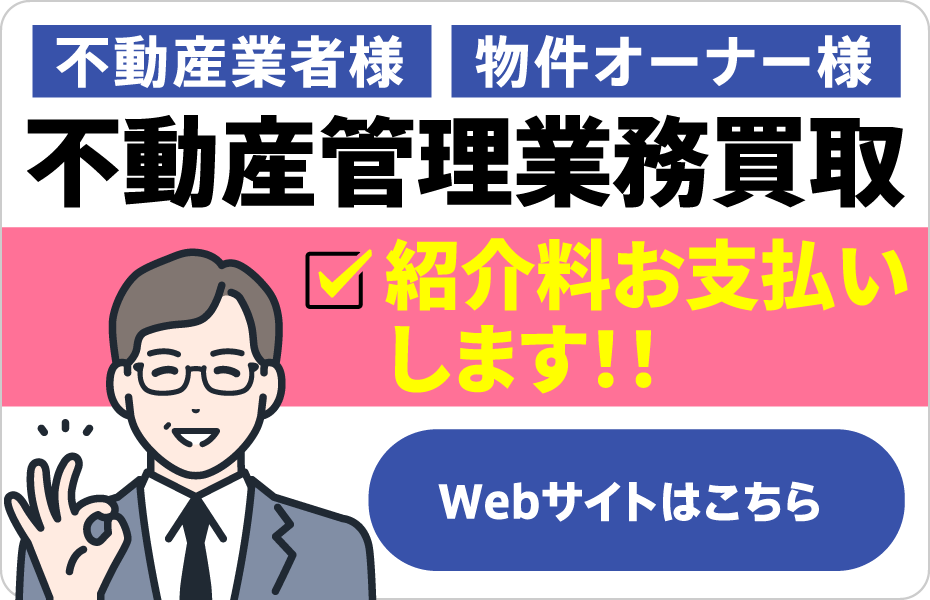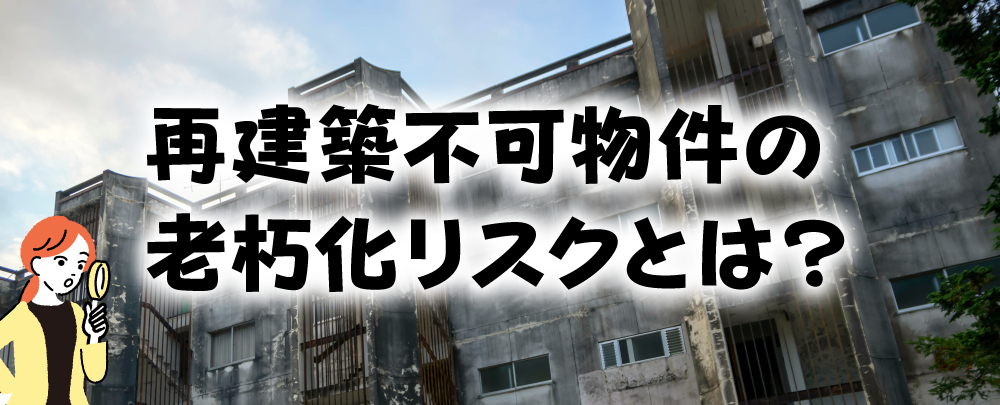
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい “お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第85回目は「再建築不可物件に2025年の建築基準法改正がどう影響するのか?」です。
再建築不可物件の老朽化に悩んでいる人はいませんか?こうした物件は、建て替えができず不動産売却も難しい上、放っておけば時間と経過とともに見た目の劣化だけでなく、資産価値の低下を引き起こします。また、老朽化が進めば建物の安全性に問題が生じ、いつ何が起こるかわからないという漠然とした不安に加え、修繕や維持管理にかかるコストも増えていきます。さらには、2025年4月の建築基準法改正にある「4号特例の縮小」が、再建築不可物件にどう影響するのかも気になるところです。
この記事では、老朽化に伴うリスクを抱える再建築不可物件の具体的な問題点と、法改正の背景や目的についてお伝えします。その上で起こり得る具体的な影響と対処法を詳しく解説します。最後まで読んで頂くことで、物件に対する不安を軽減する手がかりを得ることができれば幸いです。
再建築不可物件とは?老朽化リスクと現状!

はじめに、「再建築不可物件」とは?これは、「現在建っている建物を取り壊した後、新たに建物を建てることが法律上できない不動産物件のこと」を指します。その主な原因は、建築基準法で定められた「接道義務(安全や衛生面などを考慮して、その土地が幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない義務)」を果たしていない土地では、建物の建て替えや新築が認められていないことです。
再建築不可物件になる原因をまとめると以下。
・接道義務の未達成
・既存不適格物件(法改正により現行法の基準に合わなくなった物件)
・市街地調整区域(都市計画法により制限が厳しい)内の建物
・その他の法的制限(防火地域や高圧線が上空を通過しているなど)
再建築不可物件の問題点は、これらの法的制約により物件の資産価値は大きく下がることにあります。例えば、細い路地の奥にあるような物件は、新たに建物を建てることが非常に難しく、その上不動産市場にて買い手さんが見つけにくい物件です。古く老朽化していく建物を維持管理し続ける必要があり、結果的にリスクは増大していきます。
再建築不可物件の老朽化がもたらすリスクは以下の様なものがあります。
①安全性の低下
まず、構造の劣化により倒壊や火災のリスクが高まります。特に木造建築の場合、シロアリの被害や木材の腐食が進むことで、建物の強度が著しく低下する可能性があります。また、建物の気密性が下がり、生活の質も下がっていきます。
②資産価値の減少
また、そうして老朽化が進むと、建物の使用価値すらなくなっていき、建物や土地の評価額が下がります。不動産市場での需要が低くなり、売却できても期待した価格で売ることは難しいでしょう。
③維持管理費の増加
そして、修繕やメンテナンスに多額の費用が必要になります。老朽化した建物を安全に維持するためには、定期的な点検と修繕が大切であり、所有者さんにとっての大きな負担となります。
④近隣住民への影響
万が一、老朽化した建物や土地を十分は管理をせずに放置した場合、倒壊への不安感や衛生面での懸念から近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。
2025年の建築基準法改正に伴う4号特例の縮小とは?
そんな再建築不可物件に、2025年4月の建築基準法改正はどう影響するのでしょか?この法改正の背景には、近年の自然災害の増加や建築物の安全性向上の必要性があります。特に木造建築物の構造安全性の確保が主な目的であり、地震や台風などの災害に対する建物の耐久性を向上させることが、重要な狙いとなります。
ここから具体的な法改正の内容を確認する前に、ポイントとなる「建築確認申請」について確認しておきたいと思います。建築確認申請とは、「建物の建て替えや増築・大改修をする際に、その建物が建築基準法・都市計画法などに合致するのか行政が審査する手続きのこと」です。
この建築確認申請は、従来では下記を満たす建物であれば審査のチェック項目が少なく簡略化されています。これを「4号特例」と言います。
・木造:「2階建て以下」かつ「延べ床面積500㎡以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
・非木造(鉄筋コンクリートなど):「平屋」かつ「延べ床面積200㎡以下」
この簡略化は、特に個人所有の小規模な住宅に対して、設計者さんが倫理観に基づいて安全な構造にしている前提に立って、建築手続きを円滑に進めるための措置でした。
しかし、2025年の改正後は、こうした簡略化の対象が見直されることになります。そもそも過去に某大手企業が4号特例を悪用し、いい加減な設計の建物が多くあることが発覚。2006年当時に一度特例制度の見直しが検討されたものの、建築確認審査を行う職員の不足から改正は先送りにされていました。2025年4月以降は「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に振り分けられます。
新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200㎡超
新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200㎡以下
ただ、廃止と言いましたが、「新3号建築物」が引き続き「旧4号特例」同様に、建築確認審査は簡素化されるため、実質的には「4号特例の縮小」と言い換えられます。一方で、「新2号建築物」に該当する建物が増え、構造計算審査を含むすべての項目について建築確認審査の対象となってくるということです。これにより、耐震性能や防火性能などの安全性が、より広い範囲で厳しくチェックされるワケです。
4号特例の縮小に影響?省エネ法改正と建築物への新たな要件!
そしてもう一つ。2025年4月からは、同時に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正法も施行されます。建築物への新たな要件は以下。
①省エネ基準適合の義務化
ひとつに、幅広い建築物について省エネ基準への適合が義務化され、「新2号建築物」の建築確認申請時には、構造・省エネ図書の提出が必要となります。
②木造利用促進と省エネ対策
つぎに、木材利用の促進を通じた省エネ対策も盛り込まれており、建築物全体のエネルギー効率向上が図られます。
これらを通して政府は、2030年度に温室効果ガスの46%削減(2013年度比)という目標を掲げているワケです。この改正はその目標達成に向けた一環の取り組みと言えるでしょう。建築物の省エネ性能の向上は、エネルギー消費量の削減に寄与することになり、いわゆるカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることで、実質的な排出量をゼロにする取り組み、またはその状態を指す)の実現を後押しするものとなります。
一方で省エネ化するために、一般的な住居についても「屋根の上に太陽光発電設備を設置する」「建物の気密性を高める」などをすることになります。これにより、建物が支えるべき重量が大きくならざるを得ない状況となり、よりシビアに建築確認審査をしなくてはならなくなったと言えるので、建築基準法における「4号特例の縮小」に影響したのかもしれません。とはいえ、建物の安全性が担保されることであるので、人命を守る意味ではメリットのある法改正だと思います。
4号特例の縮小は再建築不可物件にどう影響?

これまでは、状況にもよりますが、再建築不可物件でも「柱一本でも残せば実質建て替えられる」とされてきました。具体的には、4号特例の縮小によってどう影響するのでしょうか?
①建築確認申請を通すことが困難
まず、そもそも再建築不可物件は、既に現行の建築基準法に適合していません!であるので、構造変更を伴うリフォームの際に、建築確認申請を通すことが極めて困難になります。また、新たな安全基準を満たすための大規模な改修工事が必要であり、これがリフォームの大きなハードルに。
②大規模リフォームの制限
そして、屋根の葺き替えや外壁の大規模な修繕など、建物の主要構造部分に関わる工事が実質的に不可能になるかもしれません。このため、老朽化によるリスクが放置され、建物の状態がますます悪化していく懸念があります。
③建築コストの増加
さらには、たとえ建築が認められたとしても、建築確認審査に関わる設計者さんなど、関係各所での業務量や負担の増加が見込まれます。この経費によって建築コストが高くなり、当然価格に転嫁されます。
要するに4号特例の縮小は、再建築不可物件の活用範囲を狭める可能性があるということです!
そんな中でも、可能なリフォームは限られてきます。例えば、
・小規模木造平屋のリフォーム:延べ床面積200㎡以下の木造平屋建なら建築確認申請は不要
・内装リフォーム:壁紙や床材の張替えや水回りの設備更新で居住性を上げる
などの小規模なもので、最低限の資産価値の維持を図ります。
再建築不可物件を再建築可能にする対処法!
では、再建築不可物件の老朽化リスクを回避し、資産価値の向上や将来的な売却に向けて、どう対処すれば良いでしょうか?
まず検討すべきは、再建築を可能にする方法を模索することです。再建築不可物件を再建築可能にするための主な方法は以下の通りです。
①セットバックの実施
ひとつは、前面道路との境界線を後退(セットバック)することで、先述の「接道義務」を果たす方法があります。これは、道路の中心線から一定の距離を後退させて建築することで、道路の幅員を4m以上を確保しようとするもの。特に道路の幅が狭い場合に有効で、再建築を可能にすることができます。
②43条但し書き道路の申請
ふたつ目に、ときに見た目上は道路のように思えても、建築基準法上の道路ではないものがあります。これを、特定行政庁の許可を得て、「建築基準法第43条但し書きに基づく道路」と認めてもらうことで、再建築が可能になる場合があります。この手続きでは、将来的に再建築不可に戻るリスクはありますが、時間と手間がかかりつつも成功すれば再建築できるようになります。
③隣地の一部を購入または借用する
さいごに、隣接する土地の一部を取得し接道義務を満たすことで、再建築が可能にする方法です。これは費用がかかる方法ですが、物件の資産価値を大きく向上させることができます。ただし、購入であれば恒久的に根本原因を解消できますが、借用であれば将来を保証するものではないことに注意が必要です。
上記のように、再建築可能にする方法が難しい場合は、兎にも角にも老朽化を少しでも遅らせ安全を維持するために、定期的な点検と適切な修繕が必要で、資産価値を落とさないように対処していきます。
老朽化リスクのある再建築不可物件の売却方法!
もし老朽化リスクのある再建築不可物件の不動産売却をするのであれば、売却方法には以下の様なものがあります。
①隣地所有者と同時売却する
はじめに、再建築不可物件の資産価値を最大限に引き出す方法です。再建築可能な土地を持つ隣地所有者さんに提案することで、土地2つを合わせた物件をして不動産市場で同時売却します。隣地所有者さんにとっても、単独で売却するより広い土地にして売却する方が高く売却できるので、大きなメリットと言えます。
②仲介により不動産市場で売却する
上記の対処で隣地所有者さんの理解が得られなかった場合は、不動産市場で単独の売却を目指します。想定する買い手さんの属性を意識した戦略的な売却活動をすることで、相場通りの売却価格を目指します。
ただし、老朽化のリスクのある再建築不可物件の売却の難易度は、非常に高いものとなります。その際には、
・市場相場価格より低めの適正な価格設定をする
・古家付きの土地として売却する
・適切な告知による情報開示をする
といった点に注意して活動します。
③老朽化リスクのある建物を取壊して売却する
仲介の場合、老朽化リスクのある建物が物件の価値を左右する要因になります。ならば、その建物を取り壊し更地として売却する選択肢も考えられます。更地にすることで物件の利便性や買い手さんの自由度が向上する可能性があります。
ただし、建物を取壊しても再建築不可の土地であるのは変わりありませんし、解体には高額な費用が数十万円〜数百万円単位でかかってきます。また、更地にすることで固定資産税の優遇措置がなくなり、税負担が増える可能性があるため、事前に費用対効果をよく検討することが重要です。
④不動産買取業者に直接売却する
仲介での売却が困難であるなら、確実な売却が望める不動産買取を選択するのも一つです。買取業者さんは、老朽化リスクのある再建築不可物件でも現状のまま買い取ってくれるので、大きな安心感があります。その他のメリットは以下。
・直接取引で確実かつ即金性がある
・内覧対応不要で手間が軽減できる
・建物の状態や瑕疵(かし)に関わらず売却可能
ただし、仲介売却よりも売却価格が相場より低くなることが一般的です。そのため、複数の買取業者さんに査定を依頼し、適正価格で売却できるように比較検討することが大切です。
まとめ
この記事では、老朽化に伴うリスクを抱える再建築不可物件の具体的な問題点と、法改正の背景や目的について、起こり得る具体的な影響と対処法を詳しく解説してきました。
「再建築不可物件」とは、「現在建っている建物を取り壊した後、新たに建物を建てることが法律上できない不動産物件のこと」を指します。
再建築不可物件になる原因をまとめると以下。
・接道義務の未達成
・既存不適格物件(法改正により現行法の基準に合わなくなった物件)
・市街地調整区域(都市計画法により制限が厳しい)内の建物
・その他の法的制限(防火地域や高圧線が上空を通過しているなど)
再建築不可物件の問題点は、法的制約により物件の資産価値は低くて売却しづらく、建物を維持管理し続ける必要があります。その再建築不可物件の老朽化がもたらすリスクは以下。
①安全性の低下
②資産価値の減少
③維持管理費の増加
④近隣住民への影響
そんな再建築不可物件に2025年4月の建築基準法改正が影響します。近年の自然災害の増加や建築物の安全性向上の必要性があり、特に災害に対する木造建築物の耐久性向上や構造安全性の確保が主な目的です。
この法改正内容のポイントとなる「建築確認申請」とは、「建物の建て替えや増築・大改修をする際に、その建物が建築基準法・都市計画法などに合致するのか行政が審査する手続きのこと」で、従来では下記を満たす建物であれば審査のチェック項目が少なく簡略化されています。これを「4号特例」と言います。
・木造:「2階建て以下」かつ「延べ床面積500㎡以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
・非木造(鉄筋コンクリートなど):「平屋」かつ「延べ床面積200㎡以下」
しかし、2025年4月以降はこうした簡略化の対象が見直し「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に振り分けられます。
新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200㎡超
新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200㎡以下
ただ、廃止とはいえ「新3号建築物」が引き続き建築確認審査は簡素化されるため、実質的には「4号特例の縮小」と言い換えられます。一方で、「新2号建築物」に該当する建物が増え、構造計算審査を含むすべての項目について建築確認審査の対象となってくるということです。
そしてもう一つ。2025年4月からは、同時に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正法も施行されます。建築物への新たな要件は以下。
①省エネ基準適合の義務化
②木造利用促進と省エネ対策
これらを通して政府は、2030年度に温室効果ガスの46%削減(2013年度比)という目標を掲げており、この改正はその目標達成に向けた一環の取り組みと言えるでしょう。いわゆるカーボンニュートラルの実現を後押しするものとなります。
一方で省エネ化するために建物が支えるべき重量が大きくならざるを得なくなり、よりシビアに建築確認審査をしなくてはならなくなったと言え、建築基準法における「4号特例の縮小」に影響したのかもしれません。
再建築不可物件は、4号特例の縮小によってどう影響するのでしょうか?
①建築確認申請を通すことが困難
②大規模リフォームの制限
③建築コストの増加
そんな中、可能なリフォームは限られ、最低限の資産価値の維持を図るしかありません。
要するに4号特例の縮小は、再建築不可物件の活用範囲を狭める可能性があるということです!
では、再建築不可物件の老朽化リスクを回避し、資産価値の向上や将来的な売却に向けて、どう対処すれば良いでしょうか?まず検討すべきは、再建築を可能にする方法を模索することです。
①セットバックの実施
②43条但し書き道路の申請
③隣地の一部を購入または借用する
上記のように、再建築可能にする方法が難しい場合に、不動産売却をする売却方法には以下の様なものがあります。
①隣地所有者と同時売却する
②仲介により不動産市場で売却する
③老朽化リスクのある建物を取壊して売却する
④不動産買取業者に直接売却する
メリットは以下
・老朽化リスクのある再建築不可物件でも現状のまま買い取ってくれる
・直接取引で確実かつ即金性がある
・内覧対応不要で手間が軽減できる
・建物の状態や瑕疵(かし)に関わらず売却可能
ただし、仲介売却よりも売却価格が相場より低くなることが一般的です。そのため、複数の買取業者さんに査定を依頼し、適正価格で売却できるように比較検討することが大切です。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々と解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較して頂ければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。