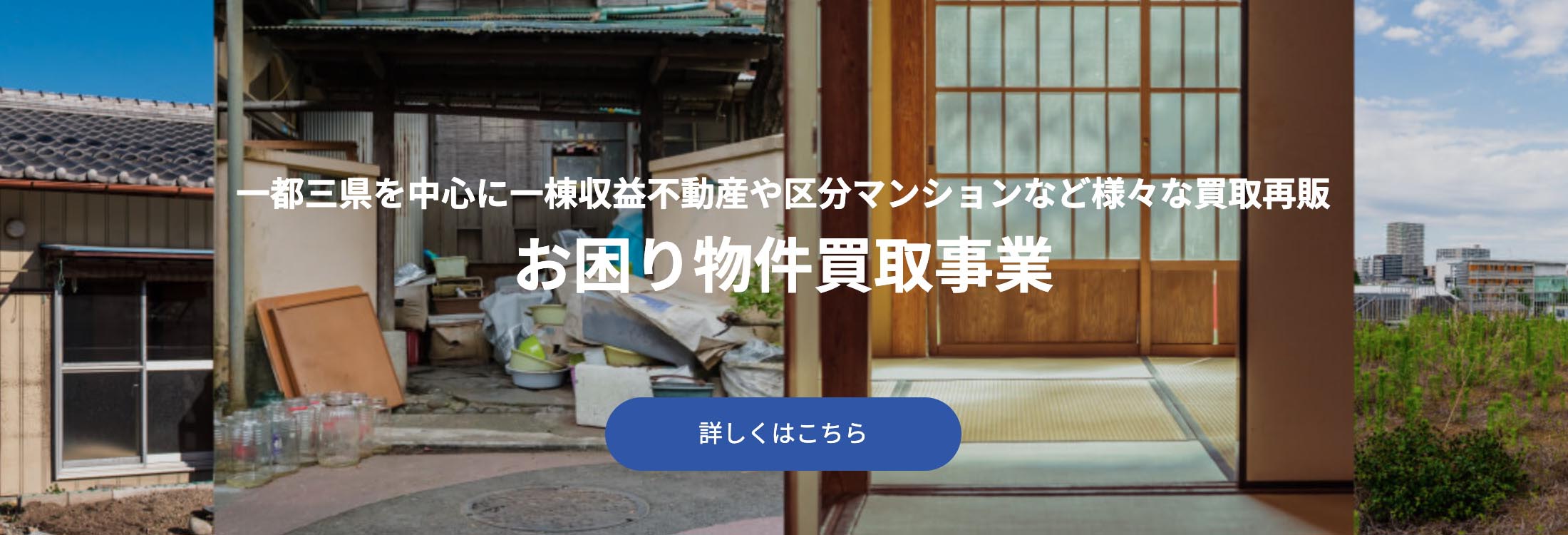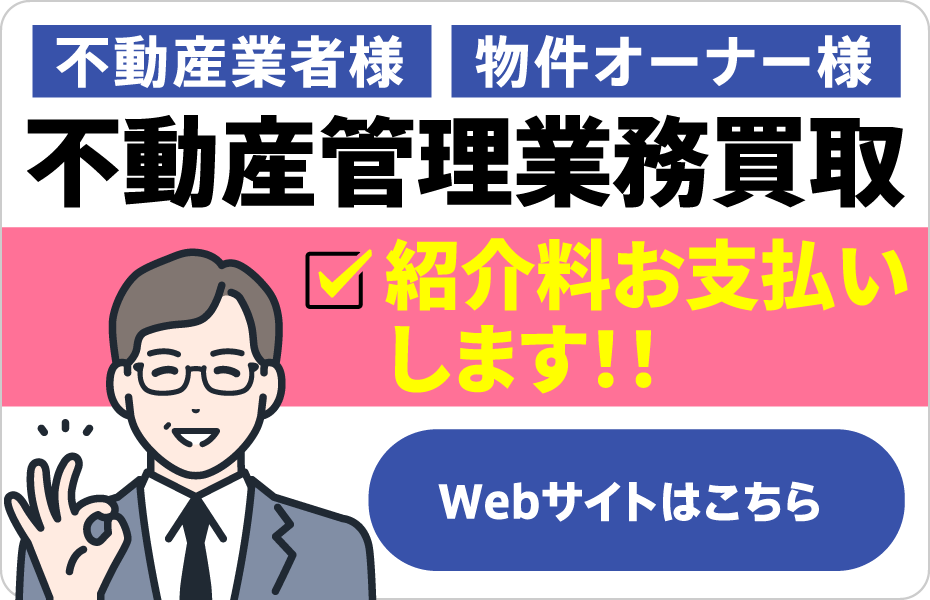独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第125回目は「二世帯住宅の相続」です。
経済面や子育て、介護を支え合ってきた二世帯住宅。けれど相続を意識するようになると、「誰が今後も住む?どう財産を分ける?税金は?」などと不安が重なりますね。共有名義のままだと単独の共有者さんの不同意で話し合いが止まる…、そんな話もよく聞きます。
今回の記事では、登記の違いと相続で使える特例制度の要点、不動産資産の分け方、不動産買取の使いどころまでを整理していきます。ポイントは「止めない・揉めない・損しない」ための進め方です!ぜひ、最後まで読んでいってくださいね。
そもそも二世帯住宅とは?登記と相続の大前提!

そもそも「二世帯住宅」とは、「一棟を親世帯と子世帯(もしくは、兄弟世帯や祖父母世帯等)で住み分けられた住宅」のことです。経済的・精神的な交流やサポートがし合える一方で、プライバシーの確保や生活スタイルの違いからストレスになり得る課題があります。
外見には同じように見えても、登記においては下記のような違いがあり、その種類によって評価や相続の進め方、特例の検討枠組みが変わります。
・共有登記:一つの不動産を複数人が「持分」を有して登記する
・区分登記:一つの不動産を複数人が「区分」された専有部分について登記する
特に共有名義の場合、管理は持分の過半数で決められる一方、売却や担保設定など性質を変える行為は原則として共有者全員の同意が必要です。意思が割れると意思決定が停止しやすいため、相続前からよく話し合っておくことが重要です。
将来、親御さんが亡くなったときに、その持分は法定相続人全員の相続対象となるのが原則で、同居の子だけに自動承継されるわけではありません。したがって、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
公平な配分と感情の折り合いが問われる領域なので、合意形成の道筋(現物分割・代償分割・換価分割)を最初から視野に入れるべきです。
・現物分割:住宅を誰か一人で相続し、他の相続人には別の財産で調整する方法
・代償分割:住宅を相続する人が、他の相続人には現金を支払って調整する方法
・換価分割:自宅を売却して現金化し、持分や合意に沿って金銭で分ける方法
それぞれの家族の実情によって、適切な判断が求められます。
二世帯住宅の相続における重要な制度3つ!
では、二世帯住宅の相続において、どの制度が誰にどれだけ活用できるのでしょうか?先に確認しておくと円滑な検討が可能になります。まずは頻出の3つを把握しておきましょう。
①配偶者居住権
ひとつに、配偶者さんの生活の安定を目的に、相続開始後も無償で住み続けられる権利を「配偶者居住権」といいます。遺言や遺産分割で設定し登記が可能ですが、一方で譲渡や無断賃貸に制約が生じます。
②小規模宅地等の特例
つぎに、被相続人さん(亡くなった人)の居住用宅地を相続や遺贈で取得した場合に、一定の要件のもと土地の相続税評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」制度があります(なお、区分登記の場合は特例の対象となる宅地等の範囲が限定されることがあります)。
③家なき子特例
そして、同居親族がいない場合に、持家のない別居の子などが一定要件を満たすと小規模宅地等の特例の対象になり得る「家なき子特例」もあります。持家の有無や転居時期、同居の実態など細かな確認が必要です。
二世帯住宅の相続を考える上で重要な点とは?
そうして二世帯住宅の相続を考える上で、社会的な情勢の変化にも注意を払う必要があります。
まず、2024年4月1日の法改正で、相続登記が義務化されました。相続を知った日から原則3年以内に相続登記をしなくてはなりません。その対象は、その法改正以前の相続についても同様で、違反すれば10万円以下の過料が科されます。その目的は、所有者不明土地の増加という社会問題の解決があります。
つぎに、2024年1月1日以降の「生前贈与加算」の改正もありました。相続開始直前の駆け込み贈与について、相続税の計算に加算される「贈与の持ち戻し」期間が3年から7年に拡大され、暦年贈与(年の基礎控除内に毎年収めて贈与)の難易度が上がっています。
その上で、二世帯住宅の相続で押さえたいのは、税務・権利・手続の三領域を進める視点です。
①税務面
まず税務面の柱は、相続税評価の「小規模宅地等の特例」で、被相続人さん(亡くなった人)の居住用宅地の評価を最大330㎡まで80%減額できる制度です。適用可否は、配偶者・同居の子・一定の別居親族(「家なき子特例」)の有無、申告期限までの居住実態など、取得者の条件で決まります。
②権利面
つぎに権利面では、配偶者さんが相続開始後も無償で住み続けられる「配偶者居住権」の設定が選択肢になります。遺言や遺産分割協議で定め、登記も可能です。配偶者さんの居住を守れる一方で、譲渡や無断賃貸に制約が出るため、売却・賃貸の計画と矛盾しない設計が欠かせません。
③手続き面
さいごに手続き面では、先述の「相続登記義務化」により、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、評価・測量、抵当や共有者の有無の確認などを並行して進める工程管理が不可欠です。名義整理が遅れると、売却や借入、代償金の支払いなど後続の意思決定が止まります。
二世帯住宅の共有名義と相続の課題!

二世帯住宅の共有名義の状態では、意思決定・資金・期限の3つが止まりやすい要注意ポイントです。
①合意形成の硬直化
まず、共有不動産の処分といった重要な判断は、共有者間での合意形成が不可欠です。しかし、「売却して現金分配したい」「思い出を重視して保持したい」といった価値観の違いや、介護貢献度や建築費負担と登記持分の齟齬が火種になりやすく、合意形成の硬直化に懸念があります。
②資金の確保
そして、一人で住宅を相続して代償分割を選ぶなら、代償金の額・支払時期・原資(自己資金、借入、持分買取)を先に決めておかないと、合意はできても実行段階で止まります。資金を確保するためには、金融機関の融資可否や担保余力、金利や返済年数も合わせて検討します。
③相続登記や相続税納付の期限
さらに、相続登記の期限管理を怠ると、過料リスクだけでなく、相続人の高齢化や所在不明などで話し合い自体が難しくなります。また、相続税の納付は相続開始を知った日から10ヶ月以内と短いため、遺産分割協議をできる限りスムーズに進める必要があります。
「複雑過ぎ!」見落としが招く大きな損失!?
特に二世帯住宅を共有状態で相続するには、どの制度をどのように活用するかの判断が「複雑過ぎ!」と難しく感じるでしょう。それも不動産という大きな財産の相続だけに、見落とせば大きな損失を招いてしまいかねません!
①登記内容の違いによるトラブル
区分登記がされている建物は、各区分が独立不動産として扱われます。そのため小規模宅地等の特例の検討は、被相続人さんが実際に居住していた区分に対応する敷地部分が中心になります。
これに対し、共有登記されている場合は、一定の要件を満たせば親族が居住していた部分も含めて「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」と評価され得ます。
区分登記を誤って共有登記の前提(いわゆる一棟扱い)で安易に申告設計を進めると、想定どおりの評価減が使えず差額が生じるおそれがあります。
②住宅の構造要件との兼ね合い
近年の実務運用では、内部の行き来可否や設備分離といった構造面よりも、「区分所有か?共有所有か?」という登記形態が小規模宅地等の特例の判断で重視されます。
先述の通り、区分登記のままだと特例の範囲が狭くなる局面があるため、ケースにより建物合併登記等で一棟化を検討する選択肢があります。ただし、特例の適用可能性を広げ得る一方で、方法によっては相続税とは別に贈与税、不動産取得税、登録免許税などの負担が生じ得るため注意。
③家なき子特例への誤解
家なき子特例の対象となる「別居の子」には、相続開始前の持家の有無や生計・居住実態など、複数の厳格な要件があります。加えて、「同居」の解釈は「被相続人と共に日常を過ごしていたか」がポイントで、形式的な住所だけでなく実態確認が求められます。
区分所有建物では各区分が独立不動産のため、家なき子特例の可否は「被相続人が住んでいた区分」と取得者要件の組み合わせで個別判断になり、認められるケースがあります。
これらは、相続の案件に強い専門家でないと難しいケースがありますので、依頼先にも注意が必要です。
大切なことは「止めない・揉めない・損しない」進め方!
大切なことは、専門家を交えて適切に判断・申告を進めていくことです。ポイントは「止めない・揉めない・損しない」です。
①止めないためにすべきこと
・登記の態様(共有/区分)、名義人、持分割合、抵当や担保、建物と敷地の面積、利用実態、ローン残債、残置物の有無を一覧化する
・相続登記の期限から逆算し、戸籍収集、評価や測量、遺産分割協議書作成、登記申請までの工程表を作る
・相続後の方針(住み続ける/売却/賃貸)と住宅取得者を家族で共有し、共有名義の解消可否も含めて、意思決定の締切日を設定する
②揉めないためにすべきこと
・相続財産の分け方を「現物分割・代償分割・換価分割」の3択で整理し、判断基準(誰が住む、資金有無、売却時期)を文書化する
・遺言書で承継者と代償金の額や支払い方法、期限を明記し、再度の共有状態になることを避ける
・価値観の相違による衝突が予想される場合は、税理士や司法書士、弁護士といった第三者の専門家の同席で合意形成を進める
③損しないためにすべきこと
・小規模宅地等の特例と家なき子特例の当否を早期に仮決めし、要件(同居継続、取得者の条件、申告期限)を満たす行動計画を作る
・区分登記のまま不利にならないか、一棟化の費用対効果(相続税メリットと他税目コスト)を比較する
・生前贈与は持ち戻し期間を踏まえ、贈与税と相続税を合算で最適化する(年末の駆け込み前に専門家へ相談)
できるのであれば相続前の事前対策として、
・親の持分を時価で買い取り単独名義に一本化するなど、共有名義の解消を検討する
・著しく低価や無償の移転は贈与課税の可能性があるため、事前に時価評価と税負担を確認する
・土地建物で名義が分かれている場合(例:土地は親、建物は子)もセットで整理し、将来の分割争いを回避する
家族の納得感と不動産買取の使いどころ!
二世帯住宅の相続において家族の納得感を高めるには、「不動産仲介にて売却」「不動産業者による買取」「代償分割」の3つを、「手取り額」「速度」「確実性」「関与コスト」で同じ前提条件にそろえて横並び比較するのがおすすめです。
・手放すのであれば、仲介によって市場相場で売却する
・手元に残すのであれば、他の相続人さんへの代償金を支払う
これらが実現できれば、一番いいのかもしれません。しかし実際のところ、そうもうまくはいきません。例えば、
・代償分割を選びたいが原資が不足する
・共有者の一部が不同意で長期化しそう
・建物の老朽や残置物で通常の売却が進まない
といったケースであれば現実的な打ち手として、不動産買取が使いどころになります。
なぜなら、現状有姿のままでも取り扱い可能であり、査定から決済までの期間が短く、資金化のスピードが求められる相続実務と相性が良いのが特長としてあるためです。
もちろん、不動産買取業者の利益を考えると、市場相場の売却価格には及びません。ただ下記のようなメリットがあります。
・自身の共有持分のみでも買取可能である
・相続税の納付期限を前に、取引の確実性が高い
・現状有姿のままでも、契約不適合責任(契約に適合しない場合の責任)が免責にできる可能性がある
・仲介手数料をはじめ、各種調査や手続きのための資金の手出しが無くて済む
・手間や時間がかからず、精神的負担から解放される
というコトで、二世帯住宅における共有名義の状態に伴う相続のトラブルを抱えている場合に、不動産買取は有力な選択肢になります。
まとめ
今回の記事では、登記の違いと相続で使える特例制度の要点、不動産買取の使いどころまでを整理してお話をしてきました。
そもそも「二世帯住宅」とは、「一棟を親世帯と子世帯(もしくは、兄弟世帯や祖父母世帯等)で住み分けられた住宅」のことです。外見には同じように見えても、登記においては「共有登記」と「区分登記」で違いがあり、それによって評価や相続の進め方、特例の検討枠組みが変わります。
特に共有名義の場合、売却や担保設定など性質を変える行為は原則として共有者全員の同意が必要であり、意思決定がしにくくなります。
したがって、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議が必要になり、「現物分割・代償分割・換価分割」のいずれかから、公平な配分と感情の折り合いが問われます。
では、二世帯住宅の相続において、どの制度が誰にどれだけ活用できるのでしょうか?
①配偶者居住権
②小規模宅地等の特例
③家なき子特例
そうして二世帯住宅の相続を考える上で、社会的な情勢の変化にも注意を払う必要があります。
・相続登記義務化
・生前贈与加算の改正
その上で、二世帯住宅の相続で押さえたいのは、「税務・権利・手続」の三領域を進める視点が重要です。
二世帯住宅の共有名義の状態では、意思決定・資金・期限の3つが止まりやすい要注意ポイントです。
①合意形成の硬直化
②資金の確保
③相続登記や相続税納付の期限
特に二世帯住宅を共有状態で相続するには、正しい判断が難しい上、見落とせば大きな損失を招いてしまいかねません!
①登記内容の違いによるトラブル
②住宅の構造要件との兼ね合い
③家なき子特例への誤解
大切なことは、専門家を交えて「止めない・揉めない・損しない」ために適切な判断・申告を進めていくことです。
できるのであれば相続前の事前対策として、
・共有名義の解消をして、単独名義に一本化する
・贈与課税の回避のため、時価評価と税負担を確認する
・土地建物で名義が分かれている場合も整理する
二世帯住宅の相続において家族の納得感を高めるには、「不動産仲介にて売却」「不動産業者による買取」「代償分割」の3つを、「手取り額」「速度」「確実性」「関与コスト」で同じ前提条件にそろえて横並び比較するのがおすすめです。
・仲介によって市場相場で売却する
・他の相続人さんへの代償金を支払う
これらが実現できればいいですが、実際のところは「原資が不足する・共有者の不同意で長期化・通常売却が進まない」といったケースがあり、現実的な打ち手として、不動産買取が使いどころになります。
もちろん、不動産買取業者の利益を考えると、市場相場の売却価格には及びません。ただ下記のようなメリットがあります。
・共有持分のみ買取可能
・取引の確実性が高い
・契約不適合責任が免責にできる可能性がある
・資金の手出しが無くて済む
・手間や時間がかからない
というコトで、二世帯住宅における共有名義の状態に伴う相続のトラブルを抱えている場合に、不動産買取は有力な選択肢になります。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較していただければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。