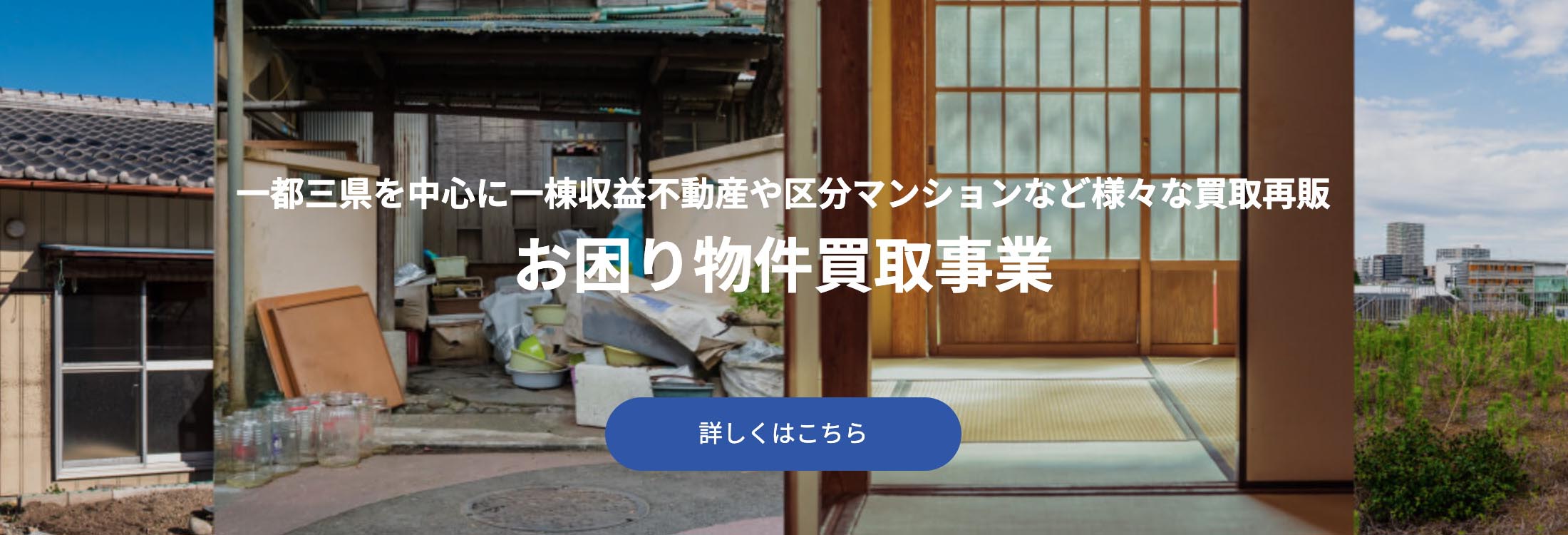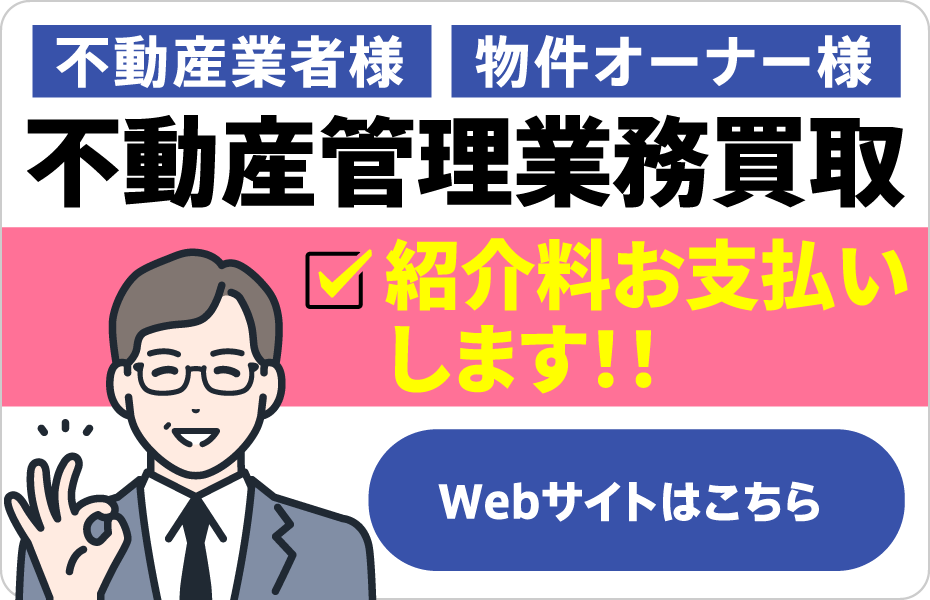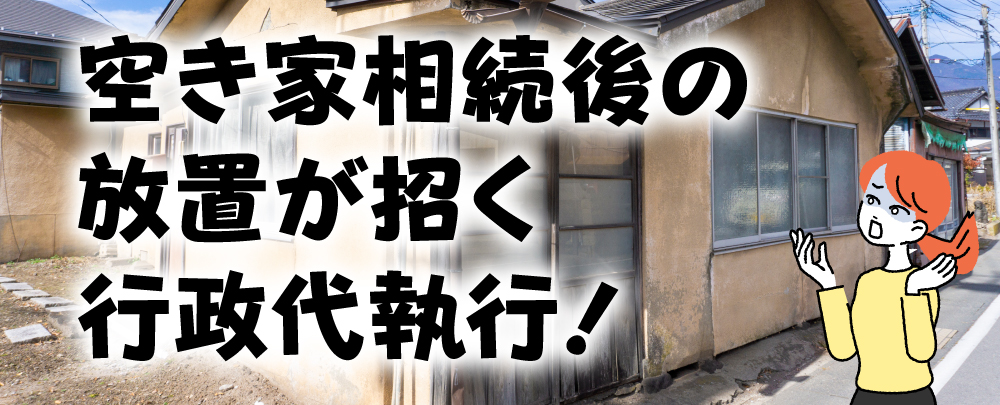
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第116回目は「空き家相続後の放置リスク」です。
「空き家を相続したけれど、どうしたらいいのか分からない…」「家族で話し合いが進まないまま、何年もそのまま…」そんな空き家、放置してしまっていませんか?実は、空き家の放置は税金・トラブル・法的リスクの温床となり、知らないうちに深刻な問題を招いてしまうことがあります。もし、行政から老朽化と管理不足が著しい「特定空家等」に指定されれば、最悪は行政代執行による建物の強制解体になる可能性があります。しかも、その高額な解体費用を請求されることに!
今回の記事では、空き家相続後の放置が招くリスク、 強制解体を避けるために今すぐすべき対策について解説します。「活用するのか手放すのか」読めば所有空き家がどんな状態であっても、後悔のない選択肢が見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
空き家の放置が社会的問題になっている!

現在の日本では、少子高齢化や人口減少で空き家が増え続けています。総務省「住宅・土地統計調査(2023年速報)」によると、全国の空き家数が約900万戸を超え、東京都内でも89万戸と過去最多を更新したとしています。
そのなかでも適切な管理をされていない空き家が増えてしまうと…、
・草木の繁茂による景観悪化
・不法占拠や犯罪の温床になるといった防犯面の問題
・老朽化による外装材の落下や建物倒壊の危険
・害虫や害獣被害などの衛生上の問題
といったリスクが伴い、周辺地域の安全を脅かす恐れがあります。
まさに、空き家の放置が社会的問題になっています!
そこで、空家等対策特別措置法では、こうした危険な空き家を「特定空家等」、または比較的軽度でも「管理不全空家等」に指定できるようになりました。こうして空き家所有者に対して、指導・勧告・命令・行政代執行(強制解体)まで、段階的に行政が介入できる仕組みを設けています。
ただ、「空き家所有者や責任の所在がはっきりしない」ケースも多かったことから、2024年には「相続登記の義務化」がスタートすることになります。これによって、相続開始から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料を科される可能性もあります(以前からの空き家も対象)。
その上で、相続人の所在不明で登記できない場合にも、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が物件を処分できる制度が整備されました。
空き家を放置してしまう3つの理由とは?
では、所有者はなぜ空き家を放置してしまうのでしょうか?頭では「放置はいけない」と分かっていても、現実にはすぐに動けない事情もあるものです。それは、大きく3つの理由があると言われています。
①遺産分割協議がまとまらない
ひとつに、「遺産分割協議」がまとまらない、話し合いが進まないことがあります。法定相続人が複数いると、それぞれの考えや事情が違うため、「誰が管理を引き受けるか」「売却するかそのままにするか」といった話し合いがまとまらず、時間だけが過ぎてしまうことがあります。
・兄弟姉妹で意見が割れている
・一部の相続人と連絡がつかない
・誰も責任を取ろうとしない
このように、感情や立場が絡み合ってしまうと「後回しにして放置」という状態に陥りがちです。
②維持管理ができない
つぎに、空き家の維持管理ができない、手がまわらないというもの。当然ですが、空き家は住んでいなくても「定期的な手入れ」が必要です。けれど、以下のような理由でなかなか管理できない方が多いのが実情です。
・空き家が遠方にあり見に行けない
・忙しくて対応ができない
・修繕費や管理サービスの費用が負担になる
その結果、空き家は劣化し続け、ゴミの不法投棄などによる景観の悪化につながっていきます。
③判断を先送りしてしまう
これらの問題が積み重なり、「判断を先送りしてしまう」ことになります。例えば、「とりあえず固定資産税を払い続ければ問題ない」「まだ親の荷物がそのままだから整理が面倒」など、見てみぬフリをしてしまいます。しかし、そのようにしているうちに問題は大きくなっていきます。
・建物の使用価値すらなくなり資産価値が低くなる
・不動産売却時の税金控除のタイミングを逸してしまう
・「特定空家等」に指定され優遇税制が外されてしまう
何もせずに時間が経つことは、問題を先延ばししているだけでなく、金銭的にも損を積み上げていくことになります。
空き家相続後の放置が招く7つのリスク!
そうして空き家相続後に放置したことで招いてしまう、7つの大きなリスクがあります。
①相続空き家3000万円特別控除の期限切れ
まずはじめに、不動産を相続した人が対象となる3,000万円の特別控除について。これは、空き家を相続から3年以内に売却することで、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2000万円)を控除できる制度です。しかしこの制度、期限が過ぎると一切使えなくなり、売却による利益に対して通常どおり課税されてしまうことになります。(ただし、現状の制度では、適用期間が令和9年中まで)
②相続登記義務違反の過料
つぎに注意したいのが、2024年4月から始まった不動産の相続登記(名義変更)の義務化。これにより、相続が発生した日(相続を知った日)から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、名義変更しなければ、「不動産売却できない」「担保にお金を借りられない」ばかりでなく、活用には法定相続人全員の同意が必要となり、時間がかかります。
③税金や維持費の増大
続いて考えたいのは、空き家は使っていなくても毎年固定資産税や火災保険料などの維持費がかかること。そして放置の状態が悪化すると「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇の打ち切りや、火災保険でも「持ち家向け」ではなく「一般物件向け」扱いになり、保険料が増額されることも。
④犯罪の温床になる可能性
さらには、誰も住んでいない空き家は、犯罪者にとって格好の標的になる可能性があります。「放火される」「不法侵入者が住みつく」「麻薬の栽培に使われていた」など、空き家が犯罪の拠点になった例も報道されています。放置した空き家が、「まさかの犯罪の現場になっていた…」となれば、悪い印象が残って不動産活用に影響も。
⑤倒壊や落下の危険と損害賠償
ときに、老朽化が進んだ空き家は、台風や地震、積雪などの自然災害で建物倒壊や外壁落下の危険性が高まります。「ブロック塀が倒れて通行人を直撃」「外壁が崩れて隣家に被害」といった事故が起きた場合、所有者として損害賠償責任を負うことになる可能性があります。
⑥近隣住民からの信用低下
これらを総じて、空き家を放置すれば近隣住民さんからの信用は低下していきます。見た目もどんどん悪くなり、「庭木が伸び放題」「郵便物が溜まっている」「ゴミを不法投棄される」「虫や異臭の原因になる」といった周辺環境への危惧も高まり、こうした状況が続けば、苦情や不信感を招くなど地域との関係が悪化します。
⑦行政代執行で高額な解体費用請求
さいごに最も深刻なリスクとして、「行政代執行」があります。放置状態がひどくなると、行政から是正指導が入り、それでも改善されない場合には最後の手段として空き家は強制的に解体されます。 それによって発生した高額な解体費用は、すべて所有者へ請求されます。その支払いを怠ると、土地に差し押さえが入ることもあり、「知らぬ間に更地にされて、さらに借金まで残った」という事態になりかねません。
強制解体を避けるには今すぐ対策を!

この「行政代執行」による強制解体は、2023年の改正空家法において「緊急代執行制度」や略式代執行の「費用徴収の円滑化」が導入されたことで、所有者不明の場合であっても行政サイドは格段に実行しやすくなりました。
具体的には、強制解体になる場合の流れは以下。
・助言や指導:担当職員が口頭や文書で改善を促す
・勧告:期限付きで改善を求め固定資産税優遇を解除
・命令:法的義務が発生し違反すれば過料
・代執行予告通知:強制解体の日程や費用負担を通告
・行政代執行:行政が解体を行って所有者に費用請求
(緊急な対応が求められる場合は、命令等を省略して即時執行もあり得る)
強制解体を回避するためには、この行政フローが進む前に今すぐにも対策を打つのが大切です。そのため、以下のような自助策を打つ必要があります。
①自ら自宅として住む
ひとつに、相続人のうち拠点を移せる人がいれば、空き家に自ら自宅として移り住む方法があります。
・住宅用地特例が維持でき、固定資産税が1/6のままになる
・一定の要件を満たせばマイホームの3000万円特別控除(空き家特例とは別の特例)が使える
・他の共有者に対しいつかは代償金(不動産に対する相続金相当)を支払う必要がある
②賃貸に出して他人に管理してもらう
つぎに、賃貸に出して他人に管理してもらう方法。
・入居者が定期的に換気や清掃を行うため劣化の進行を抑制
・賃料収入で固定資産税や保険料をまかなえる
・相続人中の誰が運用するか話し合いの必要がある
③解体して活用方法を見直す
そして、空き家の老朽化が激しく修繕が現実的でない場合に、更地にしてしまい活用方法を見直す方法。
・解体費用として公的な補助金を使える場合がある
・月極駐車場などの事業用地に転用する
・固定資産税の優遇が解除され税額は増える
・賃貸同様に相続人中の誰が運用するか話し合いの必要
これらの対策によって、空き家に対する勧告を受ける前に管理状況を改善することができます。
空き家をどう手放す?現状買取という選択肢!
ただ、「自分で管理を続ける」ことが費用や労力が見合わないと感じたら、次に紹介する処分の選択肢を検討しましょう。 「空き家をどう手放す?」かは、それぞれメリット・デメリットがあるため、状況に合った選択が大切です。
まず、「相続放棄」する方法です。これは、相続が始まってから3か月以内に家庭裁判所へ申請することで、財産や借金を引き継がない選択ができるものです。ただし、放棄したからといってすべての責任がなくなるわけではなく、管理すべき義務が一部残るケースもあるので注意が必要です。
特に空き家は、管理義務を怠ったことで第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
一方で空き家を相続し、行政の運営する「空き家バンク」や一般的な仲介を通じて売却できるなら、市場相場に近い利益を得られる可能性があります。しかし、老朽化が著しく「売ると赤字になる」ケースでは、現実的ではないことがあります。
家の状態が悪ければ、修繕費や測量費などの出費がかさみ、買い手さんが見つかったとしても売却価格が費用を下回ってしまうことも少なくありません。
もしくは、最近注目されているのが「相続土地国庫帰属制度」の活用です。この制度なら、一定の条件を満たせば土地を国に引き取ってもらえる可能性。ただし、そのためには事前に建物解体する必要と、土地管理費相当額を納めなくてはならず、その他条件に加え手続きもやや複雑…、ハードルが高い!
そこで、費用や条件に合わないのであれば、「現状買取」してもらうのも一つの選択肢。これは、不動産買取業者さんが買い取ってくれる仕組みです。買い取り価格は市場価格の7〜8割程度になるケースが多いものの、相続空き家に今後かかるであろう税金の増額や過料、さらには行政代執行による高額な解体費用を回避できると考えれば、金額以上のメリットを感じる方も少なくありません。
さらに、現状買取のメリットは他にもあります。
・老朽化した空き家に残された荷物(残置物)があってもOK
・問題があっても売却後のトラブルが少ない
・確実な取り引きでスピーディーに空き家を現金化できる
このように、空き家を手放す方法がありますが、それぞれの選択肢をしっかり比較しながら、後悔のない決断をしていきましょう。
まとめ
今回の記事では、空き家相続後の放置が招くリスク、 強制解体を避けるために今すぐすべき対策について解説してきました。
現在の日本では、空き家の放置が過去最多を更新し社会的問題となっており、そのなかでも適切な管理をされていない空き家は、「景観悪化・防犯面の問題・老朽化・衛生上の問題」を発生させ、周辺地域の安全を脅かす恐れがあります。
そこで、空家等対策特別措置法では、こうした危険な空き家を「特定空家等」とし、所有者に対して、指導・勧告・命令・行政代執行(強制解体)まで、行政による介入できる仕組みを設けています。
ただ、「空き家所有者や責任の所在がはっきりしない」ケースも多く、2024年には「相続登記の義務化」や、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が物件を処分できる制度が整備されました。
では、所有者はなぜ空き家を放置してしまうのでしょうか?
①遺産分割協議がまとまらない
②維持管理ができない
③判断を先送りしてしまう
そうして空き家相続後に放置すると、7つの大きなリスクがあります。
①相続空き家3000万円特別控除の期限切れ
②相続登記義務違反の過料
③税金や維持費の増大
④犯罪の温床になる可能性
⑤倒壊や落下の危険と損害賠償
⑥近隣住民からの信用低下
⑦行政代執行で高額な解体費用請求
この「行政代執行」による強制解体は、2023年の改正空家法において「緊急代執行制度」や「費用徴収の円滑化」が導入されたことで、行政は格段に実行しやすくなりました。
具体的には、強制解体になる場合の流れは、「助言や指導→勧告→命令→代執行予告通知→行政代執行」となります。
強制解体を回避するためには、勧告を受ける前に今すぐにも対策を打ち、管理状況を改善することが大切です。
①自ら自宅として住む
②賃貸に出して他人に管理してもらう
③解体して活用方法を見直す
ただ、「自分で管理を続ける」ことが費用や労力が見合わないと感じたら、次に紹介する処分の選択肢を検討します。
まず、「相続放棄」する方法ですが、管理義務を怠ったことで第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
一方で、「空き家バンク」や仲介を通じて売却する方法は、市場相場通りの利益を得られる可能性がありますが、老朽化が著しく「売ると赤字になる」ケースでは、現実的ではないことがあります。
もしくは、「相続土地国庫帰属制度」の活用で、一定の条件を満たせば土地を国に引き取ってもらえる可能性がありますが、難しい条件に加え手続きもやや複雑でハードルが高いものです。
そこで、不動産買取業者さんに「現状買取」してもらうのも一つの選択肢。買い取り価格は市場価格の7〜8割程度になるケースが多いものの…、
・特定空家等に指定されることで起きる負担を回避できる
・老朽化した建物や残置物があってもOK
・売却後のトラブルが少ない
・確実かつスピーディーに現金化できる
このように、相続空き家を手放す選択肢を比較しながら決断をしていきましょう。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々と解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較して頂ければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。