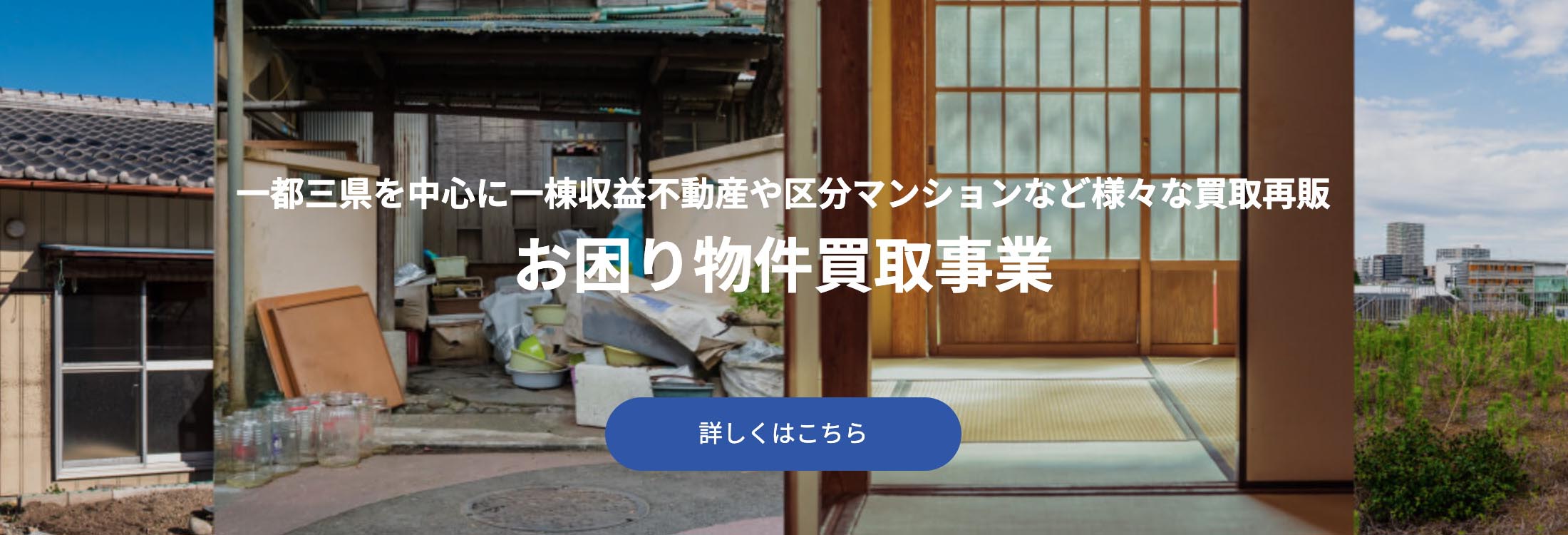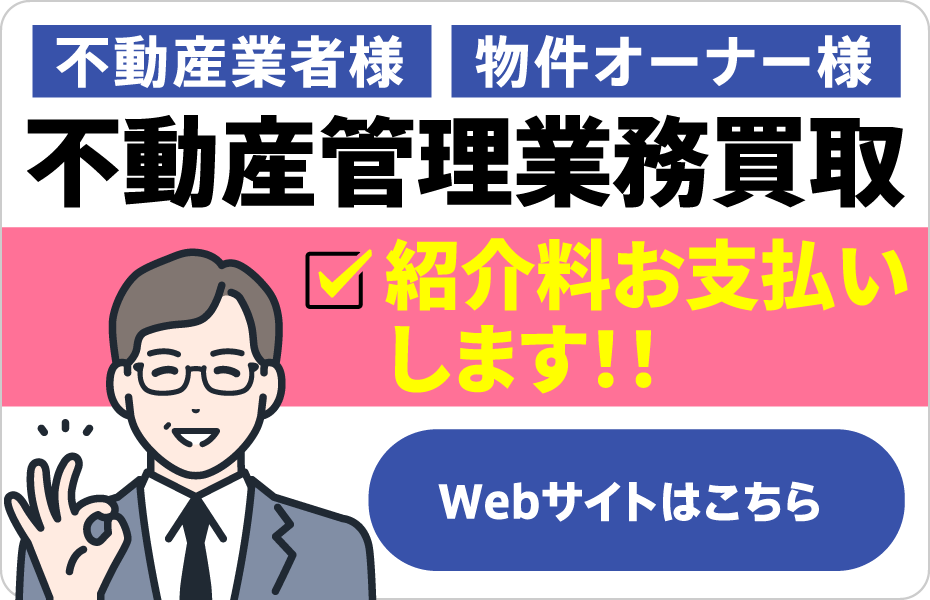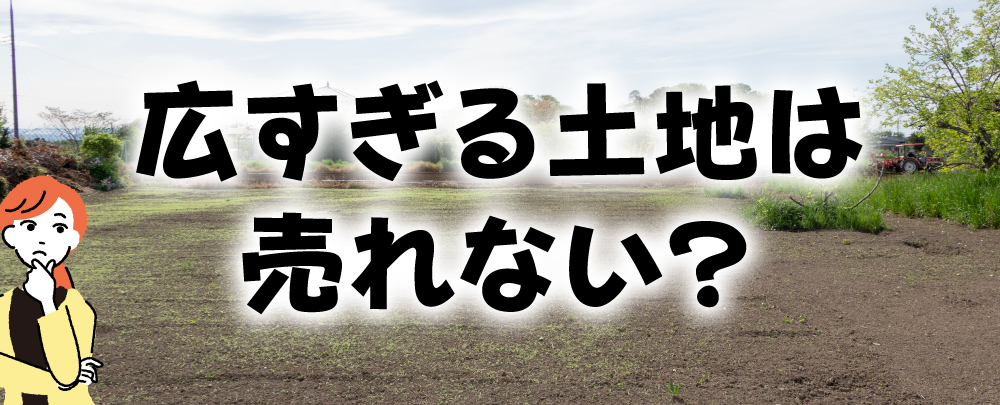
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第126回目は「広すぎる土地が売れない」です。
広すぎる土地を相続し、「固定資産税や草刈りなどの管理コストが重いのに、どう動けばよいか分からない…」そんな悩みはありませんか?「大は小を兼ねる」と言いますが、不動産についてはそう簡単なものではなく、扱いようによっては「負」動産になることも!
今回の記事では、広すぎる土地が売れない要因(ニーズのズレや規制)と、費用・税務・法リスクを分かりやすく整理。最後に、買取を含む3つの出口戦略を比較し、ご自身にあった最適解を見つけられるようにします。最短で悩みを解消に向けて、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
広すぎる土地が売れないのはニーズのズレ?

まず、「広すぎる土地」は、「戸建て敷地の一般的な広さや買い手の資金計画といった地域のニーズ(実需)から大きくズレている(外れている)規模の宅地」のことです。買い手さんが住まいのイメージを持ちにくいことが最大のハードルとなります。
たとえば名古屋市「平成30年住宅・土地統計調査結果」のデータでは、一戸建ての敷地面積は100〜199㎡(約30〜60坪)が最多という傾向が確認できます。ただ、これには地域差は大きく、「都心なのか?郊外なのか?」もしくは「駅距離や学区、道路条件、近隣相場」といった立地条件によっても違いがあります。
これが敷地面積200㎡(60坪)を超えてきてしまうと、一般的に個人には維持管理や税負担が過大で「広すぎて使い勝手が悪い土地」とされ、ニーズが低下します。そのニーズの低さや需要帯の違いが価格・流動性(流通スピード)に直結します。
他方、事業用地としても、たとえば「第一種低層地域ではマンション建設が難しかったり、商業施設の規模が制限されたりする」など、用途地域(都市計画法に基づく建物の種類や規模を制限するルール)によっては、建築の自由度と区割りの可否を左右するため、不動産開発業者でも扱いに困るケースが存在します。
広すぎる土地が売れない要因は分筆の難しさにあり!
つぎに、なぜ広すぎる土地は売れないのかの要因について。先述の通り、約30〜60坪程度に戸建てのニーズはあるため、大きい土地を分筆(分割)する方が売りやすいと感じるハズです。しかし、下記のような問題があります。
①造成工事などの費用が高額
はじめに、整地・伐採・抜根・残土処分・地盤改良・擁壁・排水計画などといった造成工事は、面積が大きいほど初期費用が膨らみます。また、分筆(一つで登記された土地を複数に分割して、新たに登記する)によって、区画数が増えるほど、インフラ整備工事や私道の新設などの費用がかさむことも見落としがちです。
②接道義務を満たす必要性
そのようにして出来た新たな区画(土地)も、それぞれで建築基準法上の原則「幅4m以上の道路に2m以上接する(接道義務)」ことが、新築の前提となります。そのため、分筆設計では「すべての区画で接道を確保」できる区割りでないと「再建築不可」と評価され、価値が大きく下がります。
③宅建業法違反の恐れ
ただし、個人が広い土地を複数に分筆し、不動産仲介業者経由で不特定多数へ反復して売却する行為は、一般に「業として行う」に該当するグレーゾーンです。明確な回数基準はありませんが、一筆を複数に分け順次売る分譲的手法は事業性が高いと判断されやすく、無免許なら宅建業法違反を問われる恐れが!
特に、「無免許営業である」とみなされてしまうと、最悪「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」等の刑事罰に及ぶ可能性があります。さらに、その罰則にとどまらず契約の信用を損ない、金融機関の審査も難しくなります。
もし、(その土地のニーズから)それでも分筆して複数売却を想定するなら、個人で分譲を企図するより、法的リスクのない出口(不動産会社への一括売却など)を先に検討したほうがいいかもしれません。
広すぎる土地を持ち続ければコストばかり膨らむ?
そんな難しさを抱え、広すぎる土地の扱いに迷っている間にも、そのコストは膨らむばかりです!
持ち続けている限り…、
・固定資産税:固定資産税評価額に標準税率1.4%を乗じて課税され、住地なら特例(小規模200㎡部分1/6、超過分1/3)があるものの、空き地には原則適用外
・都市計画税:条例で課される付加税(多くの自治体で上限0.3%)であり、市街化区域など対象の有無がある
これらの税金に加え…、
・草刈りや清掃:放置すると景観悪化や害虫発生に伴う近隣クレームの原因となる
・簡易フェンスなど不法投棄対策:進入抑止や不法投棄に対する設置や監視強化の費用
・建物の老朽化:古家付きなら雨漏りや倒壊、越境等のリスクがあり、安全措置や解体費の検討が必要
などといった管理コストが重くなります。
また、2024年4月から相続登記は原則義務化(過去の相続分も対象で原則3年以内に登記しなければならない)されました。もし、相続後に登記を済ませていないのであれば、売買契約・ローン・決済の各場面でストップがかかり、過料(行政上のペナルティ)の可能性も。
さらに、敷地内に空き家があれば、防災・防犯上の課題や雑草・害虫・不法投棄の温床となりやすく、自治体からの指導対象になることもあります。最悪は、解体の行政代執行が行われれば、その費用は高額請求になります。
時間の経過は「持ち出し」を増やし、売却活動においても心理的に「売れない→値下げ」の悪循環を招きがちです。面積が広いという根本的な課題に、これらの複雑な問題が絡むことで、個人での対応が極めて困難になるのです。
広すぎる土地における費用の重要論点!

と、ここで広すぎる土地を売却を考えるにあたって、費用面・税務面での抑えておくべき重要論点があります。
まず費用面では以下です。
①分筆・境界確定費用
・確定測量の相場感はおおむね50〜80万円、条件次第で100万円超
・分筆登記そのものは、確定測量済であれば5〜20万円程度のケースが多い
・「境界未確定・越境あり」の場合の立会いや専門家報酬が10〜40万円程度(別途、法務局手数料は、数千円〜1万円台)
②造成やインフラ引き込みなどの費用
・造成工事は一般的には坪当たり3〜10万円程度(地盤・高低差・土質で上下)
・上水道などの取出延長に概算1.5万円/m程度だが、加入金等で1口30〜50万円、下水は1口30〜50万円、電気・ガスは各数万〜十数万円が目安
・私道舗装は3,000〜8,000円/㎡程度、側溝・排水設備は仕様により100万円超の見積もりになることも
ただし、規模や条件によって全体が大きく変動(数百万円かかることも)
③私道・位置指定道路・開発許可に関わる費用
・道路位置指定の申請・設計報酬は十数万円〜(測量・設計費は別途)
・開発許可の申請報酬は数十万円〜、実費は別途(規模や自治体運用で大きく変動)
リスク回避と未登記建物を安心売却する方法を比較!
次に税務面では以下。
①固定資産税の宅地に対する特別措置
・宅地に限り200㎡部分までは課税標準1/6、超過分は1/3に軽減(自治体の運用確認必須)
・空き地や雑種地(駐車場や資材置き場など)には原則適用されない
②相続税の小規模宅地の特例
・被相続人が居住用や事業用に使用していた宅地について適用される
・一定の限度面積(居住用で330㎡・事業用で400㎡など)まで、評価額を80%減額する
・限度面積を超える土地であっても、限度面積分は適用される
③所有期間と譲渡所得税の関係
・譲渡所得は「売却価額−(取得費(取得費不明なら売却価額の5%)+譲渡諸費用)」となる
・5年以下は短期で合計税率39.63%、5年超は長期で合計税率20.315%(相続は亡くなった被相続人の期間を通算)
④地積規模の大きな宅地の評価(相続税・贈与税において)
・一定面積以上の宅地は、相続税評価で「地積規模の大きな宅地の評価」による補正が入り、評価が下がる場合がある
・三大都市圏の特定地域では500㎡以上、その他では1,000㎡以上が対象に、規模格差補正率(例0.95〜0.80)が用いられることがある
⑤相続空家の3000万円特別控除(通称・空き家特例)
・被相続人が一人で居住していた家屋(原則、旧耐震基準の昭和56年5月31日以前建築)が対象
・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋を耐震改修または解体した土地を譲渡する等の要件を満たす
・家屋と敷地を合わせた売却価格が1億円以下である必要性がある
広すぎる土地を手放すための具体的手順!
以上を踏まえて、広すぎる土地を売却するための具体的な手順です。
①用途地域や法規制の確認
まずは、自治体の都市計画情報で用途地域・建ぺい率・容積率・高さ・斜線・日影を確認。想定できる建物ボリュームと区割りの上限を把握します。
②土地家屋調査士による調査
つぎに、道路幅員・接道長・セットバック要否を測り、現況測量から関係者立ち会いでの確定測量へ。越境の有無、境界標の欠損、境界未確定の懸念を洗い出します。
③工事等の費用概算を複数社から見積もり
そして、整地・伐採・残土・擁壁・排水・舗装・上下水ガス電気の引込、私道・位置指定道路の可否まで項目を網羅。複数社の相見積もりを取り比較し、区割り案に反映します。
④税・登記・手続の見通しを揃える
さいごに、未登記なら相続登記の完了、小規模住宅用地等の特例適用の可否、譲渡所得(概算取得費の可否、短期と長期区分)、登録免許税や特例期限、印紙税の現状を整理。今後1〜2年の固定資産税・管理費も持ち出し資金として計上します。
ここでは「前提とコストの見える化」までを確実に終えることが目的です。準備が整うほどどの出口戦略でも交渉力が上がり、手取りがブレにくくなります。
広すぎる土地は活用・分割・一括の3つの最適解から選ぶ!
最後に、広すぎる土地の活用・分割(分筆)・一括といった出口戦略から比較し、ご自身の最適解を選びます!ポイントは「手残り」と「確実性・スピード・手間」の二軸です。
①土地は売却せずに活用する
まず、土地は売却せずに活用する余地はあります。活用案の代表例は、時間貸し駐車場・貸し農地・資材置場・太陽光・定期借地など。現況のままでも始めやすいものから、整備が必要なものまで様々。
メリット:
・売却せずキャッシュフロー(お金回りが改善)できる
・権利を保持し続けるため、将来の売却タイミングを選べる
・用途やテナント選定で近隣住民の合意を得やすい形も作れる
デメリット:
・初期投資や原状回復費、設備撤去費の見込みを読む必要がある
・許認可や景観と騒音などの条件を満たす手間がある
・管理負担やトラブル対応が継続し、収支が天候や需給に左右される
②分筆して不動産仲介によって売却
つぎに、ニーズ帯(例:30〜60坪)に合わせて分筆(区割り)し、宅地として市場へ不動産仲介によって売却。事前に造成・私道・インフラ整備を伴うことが多いので、前提確定と見積りが肝です。
メリット:
・ニーズ帯に合わせれば市場価格に近い成約が狙える
・区画ごとに売り分けるため資金回収の柔軟性がある
・景観整備やモデル区画の見せ方で販路を広げやすい
デメリット:
・個人が反復継続して不特定多数へ売ると宅建業法違反リスク
・測量や造成、インフラ整備など初期費用と手間が大きい
・条件の悪い土地の売れ残りリスクがある
③不動産買取によって一括売却
そして、開発・分譲の前提を買取業者が内包し、現況のままスピーディに売却する選択。条件は業者により異なるため、複数社比較が必須です。
メリット:
・現況のまま短期で現金化しやすい
・契約不適合責任(契約内容と実際が違う場合の責任)の免責が期待できる
・業者との直接取引で確実性が高い
・管理コストや税の年次持ち出しを早期に止められる
デメリット:
・一般的に提示される価格は仲介売却想定より低くなる
・業者ごとに前提(区割り・造成・販売単価)が異なり、売却価格がブレる
・取り引きをする業者選びが重要
まとめると、「手残り金額」と「確実性・スピード・手間(特にご自身の使う時間もタダではない)」の2軸、3つの中からご自身の最適解を決めるのが合理的です。とくに広すぎる土地は不確実性が多く、年次コストが嵩みやすいため、一括売却が最適解となる局面が少なくありません。
まとめ
今回の記事では、広すぎる土地が売れない要因であるニーズのズレと、費用・税務・法リスク、3つの出口戦略の最適解について解説してきました。
まず、「広すぎる土地」は、「戸建て敷地における買い手や地域のニーズからズレて広い宅地」のことです。一戸建ての敷地面積は100〜199㎡(約30〜60坪)が最多という傾向があり、地域差や立地条件によっても違いがあります。
これが敷地面積200㎡(60坪)を超えると、個人には負担が過大で「広すぎて使い勝手が悪い土地」とされ、ニーズや流動性が低下します。他方、用途地域によっては建築の自由度と区割りの可否を左右するため、不動産開発業者でも扱いが困るケースも存在します。
広すぎる土地が売れない要因は敷地の大きさであり、土地を分筆する方が売りやすいのですが、下記のような問題がでてきます。
①造成工事などの費用が高額
②接道義務を満たす必要性
③宅建業法違反の恐れ
そんな難しさから扱いに迷う間にもコストは膨らみます。固定資産税や都市計画税といった税金に加え、管理コストも重くなります。
また、2024年4月から相続登記義務化により、相続後に未登記では取り引きは滞り、過料の可能性もあります。
さらに、敷地内の空き家を放置すれば、諸問題から自治体の指導対象になり、費用が発生すれば高額請求されることもあります。
面積が広いという根本的な課題に、複合的な問題が絡み合うことで対応が困難になるため、売却には以下の重要論点を押さえる必要があります。
まず費用面。
①分筆・境界確定費用
②造成やインフラ引き込みなどの費用
③私道・位置指定道路・開発許可に関わる費用
次に税務面。
①固定資産税の宅地に対する特別措置
②相続税の小規模宅地の特例
③所有期間と譲渡所得税の関係
④地積規模の大きな宅地の評価(相続税・贈与税において)
⑤相続空家の3000万円特別控除(通称・空き家特例)
以上を踏まえて、広すぎる土地を売却するための具体的な手順です。
①用途地域や法規制の確認
②土地家屋調査士による調査
③工事等の費用概算を複数社から見積もり
④税・登記・手続の見通しを揃える
この「前提とコストの見える化」までを確実に終えることで、広すぎる土地を3つの出口戦略から比較し、「手残り」と「確実性・スピード・手間」の二軸から、ご自身の最適解を選ぶことに繋がります。
①土地は売却せずに活用する
メリット:キャッシュフロー改善・将来の売却タイミングを選べる・近隣住民の合意を得やすい形も作れる
デメリット:将来的な費用見込みを読む必要・許認可などの条件を満たす手間・管理負担やトラブル対応が継続
②分筆して不動産仲介によって売却
メリット:市場価格に近い成約が狙える・資金回収の柔軟性がある・見せ方で販路を広げやすい
デメリット:反復売却の宅建業法違反リスク・初期費用と手間が大きい・売れ残りリスクがある
③不動産買取によって一括売却
メリット:
・現況のまま短期で現金化・契約不適合責任免責の可能性・取引の確実性が高い・継続コストを止められる
デメリット:仲介売却より売却価格が低くなる・業者によって売却価格がブレる・業者選びが重要
広すぎる土地は不確実性が多く、年次コストが嵩みやすいため、買取業者による一括売却が最適解となる局面が少なくありません。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較していただければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。