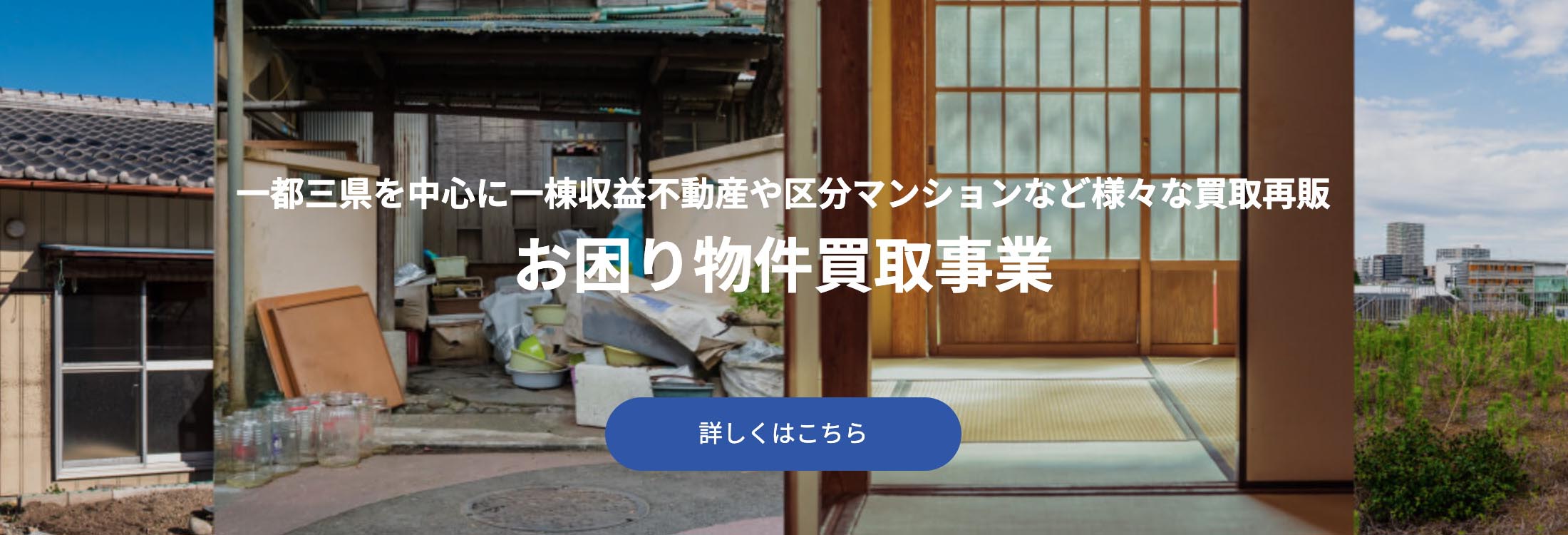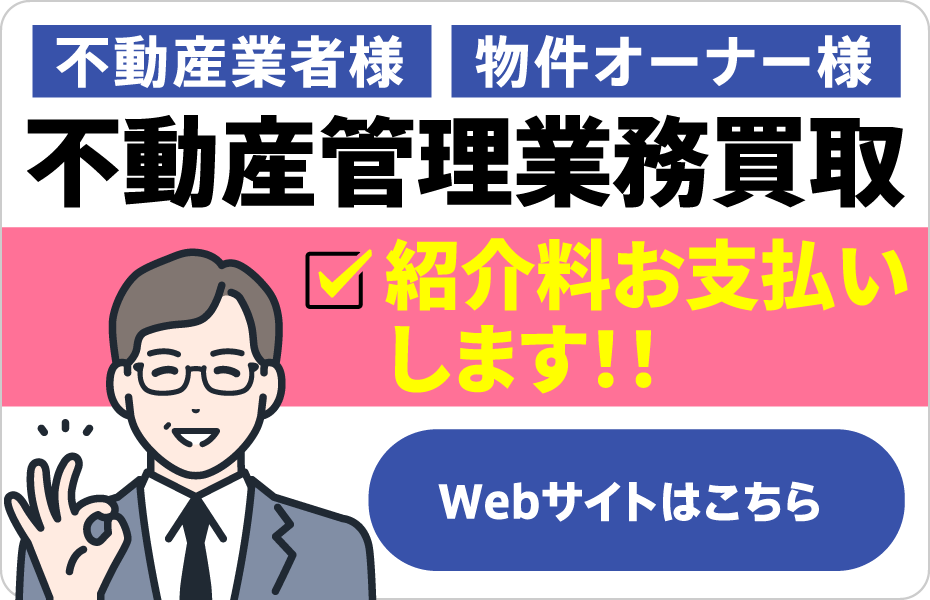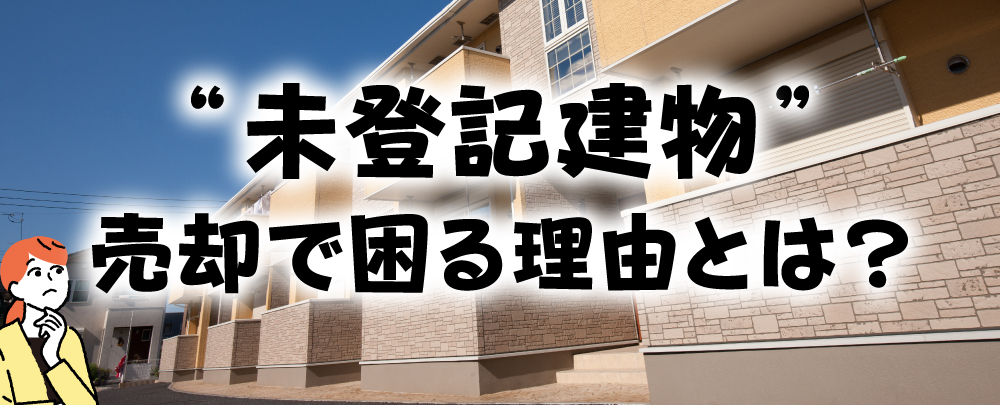
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第124回目は「未登記建物の売却」です。
「相続した古い建物を売ろうと思ったら、未登記だった…」そんな状況に困ってしまうケースは少なくありません。未登記の建物は、そのままでは売却時に、買い手が住宅ローンを利用できない、所有権の主張が弱い、税務や行政手続きに支障が出るなど、さまざまな問題が発生します。ただ、法律上は売却可能であり、正しい手続きを踏めば安心して取引することもできます。
今回の記事では、未登記建物が存在する理由、未登記建物の売却で困る理由や問題を整理し、そのリスクを回避しつつ安心売却をするための方法を比較していきます。読んでもらえれば、不動産買取業者を活用するメリットも含め、最適な選択肢を考えるための判断軸を理解することができます。ぜひ、最後までお付き合いください。
未登記建物はなぜ存在するのか?

通常、建物を新築したり相続した場合、下記の登記を行う必要があります。
・表題登記:建物が存在することを法務局に届け出る手続きで、建物の所在地・構造・床面積などを登録する
・所有権保存登記:建物の所有者を明確にし、第三者に所有権を主張できるようにするもの
・相続登記:相続によって、被相続人から相続人へと不動産の所有権移転したことを登録する
本来は必須の手続きで法律で義務付けられていますが、現実には未登記建物(登記簿に記載がない建物)が数多く存在します。なぜ、そういった建物が存在するのでしょうか?
①古い建物や離れ
ひとつに、昭和30〜40年代、自己資金で住宅を建築するケースが多くありました。当時は金融機関からの融資を受けないため、担保としての登記を必要とせず、登記費用を節約する目的で省略されることも珍しくありません。母屋に隣接する「離れ」「倉庫」「物置小屋」なども未登記で建てられた例が多く、現所有者すら登記がないことに気づかないこともあります。
②増改築
つぎに、住宅を増改築した場合、本来は「表題変更登記」(建物の床面積や構造変更を届け出る登記)が必要です。ところが、工事後も登記が更新されないまま放置されることがあります。例えば、二階を増築しても登記簿上は「平屋」と記載されたまま放置されるなど、登記簿と実態が一致せず、問題視される場合があります。
③相続時の不備
さらに、相続が発生した際、被相続人さんが生前に登記をしていなかった場合や、過去に建物を新築したものの登記を省略したまま相続が繰り返された場合では、「未登記建物」が残されることがあります。特に、遺産分割協議書や建築確認書類が残っていない場合には、誰が所有者なのかを証明するのに時間と手間がかかります。
それらの所有者さんの中には、「税金を払っているから登記も済んでいる」と誤解する人もいますが、実はそうでもありません。各自治体は、現地調査や航空写真で課税対象を物理的に把握するため、登記の有無にかかわらず固定資産税等は課税されます。
あくまでも、登記簿に登録されていない建物は「未登記建物」となります。
未登記建物が売却で困る理由とは?
法律上、未登記建物でも売却契約を結ぶことは可能です。ただし、未登記のままで建物を売却しようとすると、実務上で困った問題に直面します。
①買主が住宅ローンの利用ができない
まず、買主さんが住宅ローンの利用ができない点。住宅ローンを組む際、金融機関が融資の対象物件を担保にするためには、建物が登記簿に登録されていることが必須条件です。しかし、登記されていなければ、担保評価ができず融資対象外とされるケースがほとんどです。
②買主が登記できない不安
つぎに、未登記建物を購入した買主さんは、登記を自分で行う必要があります。専門家への依頼費用や手間、書類の不備が障害となり、「自分で登記ができないのでは」と不安を抱き、購入を避ける人も少なくありません。
③仲介による売却が難航する
そして、不動産仲介業者は未登記建物を扱いたがらない傾向があります。重要事項説明で未登記建物について明確に告知する義務があり、説明責任が重くなるため、買主さんとの交渉が難航しやすいのです。
④売却価格が低くなりやすい
さらに、未登記建物は「リスク物件」とみなされ、買主さんから値引き交渉を受けやすくなります。例えば、「自分で登記する費用分を差し引いてほしい」といった形で、売却価格が相場よりも低くなりやすい傾向にあります。
未登記状態で起こり得るリスク!
そして、未登記を放置することは、売却困難以上に権利関係・税務・行政手続きにまで影響し、深刻なリスクを招きます。
①第三者対抗要件の欠如リスク
まず、「第三者対抗要件」といって、不動産の所有権は登記がなければ第三者に権利を主張できません。そのため、未登記のままでは所有権を失うリスクがあります。この点、買主側においても登記がなければ、二重譲渡(売主による二重売却)の際に後から登記した買主さんに劣後しますし、債権者の差押えにも対抗できません。
②税金トラブルのリスク
また、未登記建物でも固定資産税は、登記の有無に関わらず課税されます。問題は売却して引き渡したにもかかわらず、「未登記家屋所有者変更届」を提出しなければ、納税通知は引き続き旧所有者さんに届く点です。さらに、過去分の課税が追徴されるケースもあり、経済的な負担が想定外に膨らむリスクがあります。
③違法建築であることが発覚するリスク
そして、増改築部分や付属建物(車庫・倉庫・離れなど)が未登記のままだと、「登記情報と実際が異なる」として問題視されます。特に、建築基準法や建ぺい率・容積率の制限に違反していた場合は、行政から是正命令を受ける可能性があり、場合によっては建物の使用制限や取引中止に至るリスクもあります。
④相続登記義務化への対応リスク
さらに、2024年4月1日以降、相続による不動産取得の登記申請は義務化された点に対応が必要です。相続開始後3年以内に行わないと、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法改正)。これには、未登記建物も対象であり、放置していると法的ペナルティが科される可能性があります。
⑤相続や贈与時の停滞と所有者不明化リスク
さいごに、未登記建物は、相続や贈与のたびに「誰が真の所有者なのか」が不明確になりやすい特徴があります。相続が繰り返されると、複数人が「口約束だけ」で権利を主張し、最終的にはいわゆる「所有者不明不動産」となってしまう可能性があります。
こうなると売却はもちろん、賃貸や建替えといった活用もできず、固定資産税の納付や管理責任だけが延々と残ることになります。
「未登記建物・境界不明でも対応可」離れた2つの物件を同時にご売却いただいた事例!

ここでは、実際に弊社をご利用いただいた不動産所有者さんの事例を紹介します。
後継者のいない木造アパートを手放したいものの、建物は未登記で敷地の境界もあいまい。加えて、離れた場所にある駅近の狭小地店舗の処分にも困っていたC様、「入居者がいるアパートは隣地が不在で境界立会いに不安があるし、もう一つの小さい土地も一緒に売れないものか…」と、弊社にご相談にみえました。
そこで当社では、まず未登記建物の登記を家屋調査士と連携して実施。費用は弊社が負担し、C様のご負担を減らしました。境界についても、隣地所有者さんが長期不在で立ち会いが難しい状況を踏まえ、立会いが不要な方法で境界を確定する対応策をご提案。
その上で、物件を2つとも弊社で買い取らせていただき、アパートについては入居者さんの立ち退き交渉を行い、円満に合意を得てから解体。現在は更地として販売活動を進めています。また、もう一方の駅近店舗については、立地の良さを活かし、改装後は地域の店舗として私たち自身で運営を続けています。
未登記建物の売却や境界未確定、立ち退き交渉といった複雑な条件でも、弊社ならワンストップで対応可能です。結果的に、C様の「この状態で買ってくれるところはあるのか」という不安は一気に解消。C様は「未登記や境界の問題まで解決してもらい、しかも店舗が地域で活用されているのが嬉しい」と安心されたご様子でした。
リスク回避と未登記建物を安心売却する方法を比較!
それでは、リスクを適切に回避しつつ、未登記建物を安心して売却するためにはどうしたら良いでしょうか?
①未登記建物を法的にクリーンにして仲介で売却
まずは、売主自身が表題登記・所有権保存登記・相続登記を行った上で、仲介業者を通じて売却する方法です。
メリット:
・建物が法的に明確な状態になるため、買主が住宅ローンを利用できる
・適正価格で売却でき、交渉もスムーズに進みやすい
デメリット:
・登記費用や専門家への依頼費用や時間が必要
・売却を急ぎたい場合には不向きとなる可能性がある
②未登記建物自体を解体して土地のみ売却
つぎに、老朽化が進んでいる場合には建物を解体して、「更地」として売却する方法もあります。
メリット:
・未登記建物のリスクを根本的に解消できる
・買主が自由に土地利用できるため需要が高まる
デメリット:
・特にアスベスト含有建材があれば、解体費用の負担が大きい
・解体後は住宅用地の特例(税軽減措置)が外れ、税額が上がる可能性がある
③仲介業者へ売却依頼をし、未登記状態を売買契約書に明記してもらいそのまま売却
さらに、あえて登記を行わず、契約書に「本物件は未登記建物である」と特約を記載して売却する方法があります。
メリット:
・登記をせずに済むため、売主にとっては費用や時間を節約できる
・買主がリスクを理解した上の現金一括購入する場合や、事業者相手であれば成約の可能性がある
デメリット:
・買主が住宅ローンを使えないため、購入希望者が限られる
・売却価格も相場より下がりやすくなる
・税務上の「未登記家屋所有者変更届」を怠れば、旧所有者に課税され続けるリスクがある
④未登記状態のまま不動産買取業者に直接売却
そして、未登記状態のまま不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法です。
メリット:
・売主が登記や解体などを事前に行わなくても、そのまま現況で引き取ってもらえる
・売却スピードが速く、仲介のような買主探しも不要
・諸問題があっても専門家間で連携して処理、心理的負担も軽減できる
デメリット:
・仲介による売却に比べ、売却価格は低めになる
・悪徳業者も多く、業者選びには注意が必要
未登記建物を不動産買取を利用するメリットは、単なるスピード感だけではありません。たとえば、登記に必要な書類の不足や、相続人間の意見がまとまらない場合でも、業者が解決に向けて動いてくれることがあります。
また、一般個人のようにローン審査落ちで契約破談にならず、費用対効果や心理的負担の軽減を考えれば、多くの方にとって合理的な解決策となり得ます。
まとめ
今回の記事では、未登記建物の売却で困る理由や問題を整理し、そのリスクを回避しつつ安心売却をするための方法を比較・解説していきました。
通常、建物を新築した場合は「表題登記」と「所有権保存登記」を、相続した場合は「相続登記」を登記を行う必要があります。本来は法律で義務付けられていますが、現実には未登記建物が数多く存在します。
①登記費用を節約する目的で省略してしまう
②増改築時に表題変更登記がもれてしまう
③相続時の不備により発生してしまう
それらの所有者さんの中には、固定資産税等が課税されていることで、登記済と誤解するケースもありますが、あくまでも登記簿に登録されていない建物は「未登記建物」となります。
法律上、未登記建物でも売却契約を結ぶことは可能です。ただし、未登記のままで建物を売却しようとすると、実務上で困った問題に直面します。
①買主が住宅ローンの利用ができない
②買主が登記できない不安
③仲介による売却が難航する
④売却価格が低くなりやすい
そんな未登記建物を放置することは、売却困難以上に深刻なリスクを招きます。売却はもちろん活用もできず、固定資産税の納付や管理責任だけが残ります。
①第三者対抗要件の欠如リスク
②税金トラブルのリスク
③違法建築であることが発覚するリスク
④相続登記義務化への対応リスク
⑤相続や贈与時の停滞と所有者不明化リスク
それではリスクを適切に回避しつつ、未登記建物を安心して売却するためにはどうしたら良いでしょうか?
①未登記建物を法的にクリーンにして仲介で売却
②未登記建物自体を解体して土地のみ売却
③仲介業者へ売却依頼をし、未登記状態を売買契約書に明記してもらいそのまま売却
④未登記状態のまま不動産買取業者に直接売却
それぞれメリット・デメリットはありますが、登記に向けた時間や手間が負担になるようであれば、不動産買取が良い選択になる場合があります。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較していただければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。