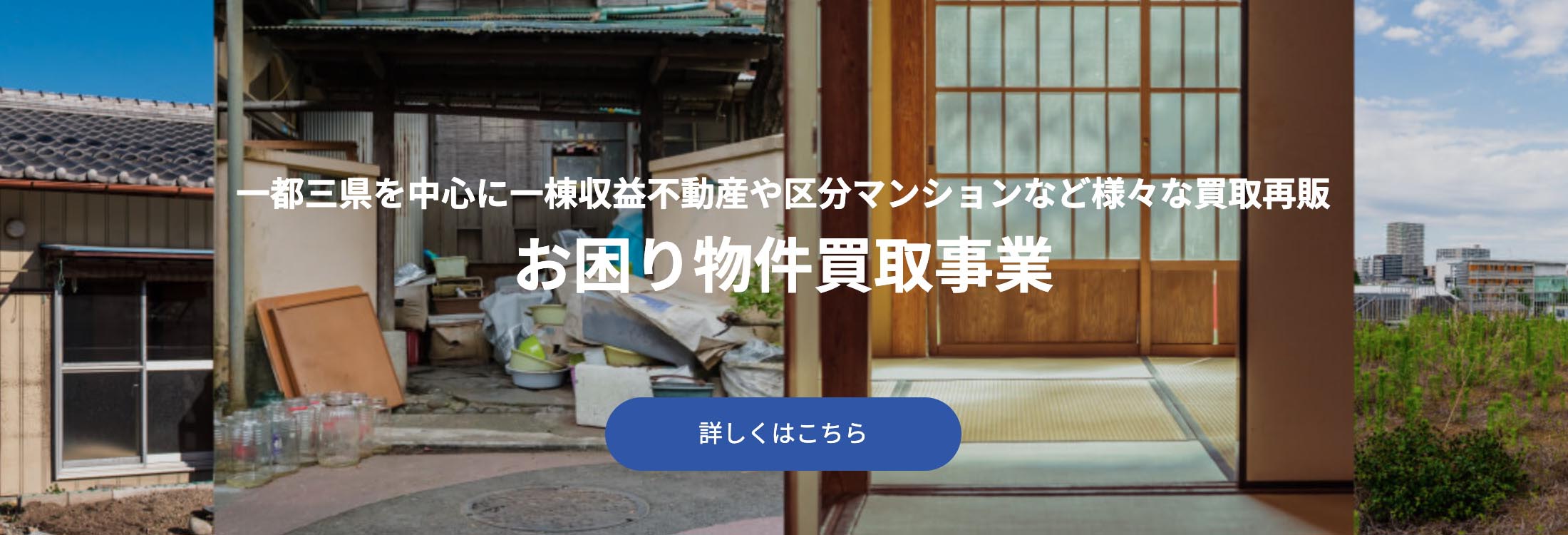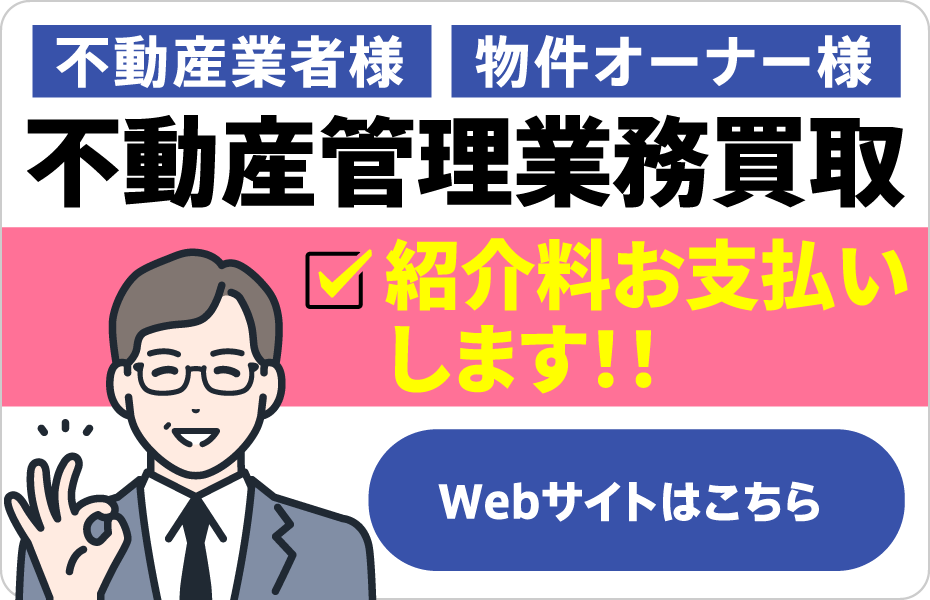独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第119回目は「高圧線下の土地の売却」です。
相続した土地の真上を高圧送電線が横切り、「建物を思うように建てられず活用できない」「健康への不安から買い手が付かない」と、不動産売却を諦めていませんか?確かに高圧線下(送電線直下)には建築制限があり、評価額も下がりやすい現実があります。しかし、制限内容と補償金、地役権を正しく理解し、専門家の手も借りることができれば、十分に売却可能です!
今回の記事では、高圧線下の土地の定義や売却難航の理由から、少しでも高値で売るステップまで、順に解説していきます。読み終えれば、管理の手間暇や固定資産税の重荷から解放されるルートが見えてくるハズ。ぜひ最後までお付き合いくださいね。
高圧線下の土地とは?

はじめに、「高圧線」とは、「高い電圧の電気を送る電線」のことであり、高電圧にすることで電気の損失を抑えつつ、効率的に遠くまで送ることができます。
・低圧:直流750V以下、交流600V以下
・高圧:直流750V〜7000V以下、交流600V超〜7000V以下
・特別高圧:7000V超
そんな「高圧線下の土地(「高圧線下地」とも言う)」とは、「送電線の垂線直下(真下に引いた直線)や離隔距離(電線と建物の最小距離)内にある土地」を指します。送電線は、感電の恐れがあるため、接近は厳しく禁じられています。また、周囲に「電磁界」を発生させ、その「電磁波」が空間を伝播します。
電気設備に関する技術基準(2012年改正経済産業省令第52号)では、下記のように定められています。
・使用電圧が17万V超えの場合、直下を含む側方3m以内は建築不可
・使用電圧が17万V以下の場合、送電線からの離隔距離3mまたは(3+c)m以上保てば、直下でも建築可 ※「c」は35000Vを超える場合に10000V毎15cm加算
加えて、「振れ幅下地」という考え方もあり、強風で電線が揺れる範囲を考慮し、直下だけでなく側方エリアにも制限が及ぶことがあります。
この建築制限により、敷地の一部が使用できずに用途が限られるため、評価額が下がる傾向です。そのため電力会社との間で「高圧線下地役権(電力会社が電線を維持管理するために、土地の上空を使用する権利)」を設定し、土地所有者さんに対して「対価補償金」が支払われることがあります。
高圧線下の土地売却が難航する5つの理由!
その高圧線下の土地売却は、実際に売却を試みたとしても、なかなかスムーズに進まないことが多くあります。それは、売却活動が難航する5つの理由があるからです。
①建築制限により需要が低くなりやすい
まず、高圧送電線の真下や周辺に位置する土地では、電気設備の安全確保のため、電力会社との私法上の契約(地役権設定など)や技術基準に基づき、送電線から建物まで一定の距離を保つ必要があり、建物の建築や増改築が困難な場合があります。
敷地全体を自由に使えないことで、住宅用地としての魅力が下がり、結果として買い手さんから敬遠される傾向。需要が低くなりやすく、売却活動が長期化する可能性が高まります。
②市場相場よりも低い提示を受けやすい
次に問題となるのが、土地の評価額です。たとえば財務省の通達によると、国有地に電力会社が線下敷地として使用許可する場合、その直下地の利用の阻害率が「更地価格の30%」とされることがあります。これは一般に「70%の評価額」を意味します。
このような評価基準は民間の不動産取引においても参考にされることが多く、買主側も「高圧線下の土地=大幅に減価される」という認識を持っています。そのため、査定額や購入希望価格が、市場相場よりも著しく低い提示を受けやすいと言えるでしょう。
③補償金に関する事情が値引き交渉の原因になる
また、土地所有者として電力会社から「対価補償金(地役権に伴う対価)」をすでに一括で受領していた場合、その後の買主さんには補償が原則支払われないため、その事情によって値引き交渉の原因に。
一方で、補償金を年額で受け取っていたとしても、契約内容や登記状況によっては新たな所有者さんが補償金を継続して受け取れない可能性もあるため、やはり売却交渉の障害になりがちです。
④建築の自由度が低く融資審査も不利になる
さらに、高圧線下の土地は送電線との離隔距離や高さに制約が生じ、「敷地全体の一部しか使えない」「思うような配置や間取りが実現できない」と建築の自由度が低く、買い手さんにとって大きなデメリットとなります。
これらの制限により、金融機関として売却しづらい土地を担保とすることを避けたがる傾向にあり、住宅ローンなどの融資審査においても不利に働きやすいです。
⑤電磁波や騒音に対する心理的抵抗感が根強い
最後に、たとえ法的な安全基準を満たしていたとしても、高圧電線の下に住むことへの心理的な抵抗感は根強く残っています。たとえば、「電磁波による健康被害」「強風時の風切り音」など、生活の質に対して不安視されます。
実際には、国際的な電磁界ガイドライン(ICNIRPやWHO)に照らしても、日本国内の健康被害の明確な科学的根拠は確認されていません。それでも、「なんとなく怖い」「子どもには住ませたくない」といったイメージ面で敬遠されることが多いのです。
このように、実害というよりも感情的・印象的な要因で価値が下がってしまうのも、高圧線下の土地ならではの特徴といえるでしょう。
高圧線下の土地放置で広がるリスクとは?
とは言え、活用のしづらさから高圧線下の土地を放置すると、次第にさまざまな問題が蓄積し、以下のような思わぬリスクに発展します。
①固定資産税や維持管理費の負担が続く
ひとつに、活用せず保有を続ければ固定資産税や維持管理費が家計を圧迫します。しかも土地の利用価値が低ければ、その費用を売却益で将来的に回収する見込みもなくなっていきます。
たとえ住んでいなくとも、草刈りやごみの不法投棄の防止といった最低限の維持管理も必要です。これを怠ると、近隣からの苦情や行政指導につながることもあり、金銭面だけでなく精神的な負担も大きくなります。
②地役権が未登記のままだと交渉権を失う恐れがある
また、長期放置で地役権未登記の場合、電力会社から時効取得を主張され交渉余地を失う恐れがあります。これは、電力会社が一定期間以上、送電線を通して使用し続けた結果、法的にその「使用権利が自動的に確定してしまう」ことを意味します。
地役権における立場が著しく低下し、補償金の交渉や契約更新のタイミングを逃すことになります。また、未登記であるがゆえに買主への情報提供も曖昧になり、重要事項説明違反とも絡んで、複合的な法的トラブルに発展しかねません。
③契約関係の記録や事情説明が不十分になりやすい
他方で、高圧線下の土地を売却を考えたとき、その告知義務違反リスクにも注意が必要です。宅地建物取引業法「重要事項説明」により建築制限や地役権は契約前に説明義務があり、放置期間が長いほど契約関係の記録や事情説明が不十分になりやすいものです。
認識の有無に関わらず、怠れば買主側に不安と不信感を与え、「情報開示不足による慰謝料の支払い命令」「補償金条件を告知しないと契約後でも損害賠償を求められる」といったリスクは高まります。
このように、高圧線下の土地を放置していると、税金・管理・法的義務・補償金・地役権といった複数の要素が絡み合い、将来的に対処がますます困難になります。そのため、少しでも早い段階で現状を整理し、売却・活用・地役権登記などの対策に踏み出すことが、将来の損失回避につながります。
高圧線下の土地は評価が難しい?

一般的に、高圧線下の土地は一律に評価できるものではなく、個別事情を考慮して慎重に価値を見極める必要があります。具体的には以下のような基準を参考に査定します。
路線価地域:(一般的なもので)路線価に線下補正率を掛け評価
公示地価:(一般的なもので)標準地価格を参考に線下補正を適用
倍率地域:(一般的なもので)固定資産税評価額×倍率を基準に減価補正
地役権:登記・面積・補償金を確認し負担分を控除
財務省基準:高圧線下地は更地価格の30%が目安
相続税評価:(建物が全く建てられない場合)最大50%減額の特例あり
電力会社減価:用地補償要綱の約17〜50%減価率(電圧による)を参照
収用委員会:公共事業収用時の判例では15〜35%の阻害率を認定
しかし、国税庁が定める「路線価」や国土交通省が発表する「公示地価」などの基準地価格には、高圧線によるリスクが十分に反映されておらず、その他それぞれの判断基準についてもまちまち…。
そこで、評価時には以下のような補正を行うことが一般的です。
物理的減価:建築制限による使用可能面積の減少や形状制限など、その利用阻害分を減価
心理的減価:景観・安全性への不安、騒音などの心理的なマイナス要因を考慮し減価
このように、高圧線下の土地評価は画一的なものではなく、現況・契約内容・地域の市場動向・心理的要因などを総合的に見て行われるべきものです。査定方法によっては数十%の差が出ることもあるため、複数社の意見を聞くのが得策です。
高圧線下の土地を少しでも高値売却するステップとは?
このように、高圧線下という不利な条件のある土地でも、事前準備と戦略的な売却活動によって、売却額を可能な限り高めることができます。ここでは、少しでも高値の売却成功に近づくための5つのステップをご紹介します。
ステップ1:登記簿と電力会社照会で建築制限面積・離隔距離を数値化
まず、土地の登記簿を確認し、建築制限の範囲、送電線の離隔距離、地役権の有無や内容、補償金の支払い履歴など具体的な数値を調べ、必要に応じて電力会社に照会します。
ステップ2:補償金の受領方法を整理し価格シミュレーションを作成
つぎに、一括受領か年額受領か、補償金の状況で売却価格に影響があるため、買主さんへの補償金あり・なしに分けて価格シミュレーションを作成し、適切な売り出し価格を設計します。
ステップ3:不動産鑑定士の意見書で減価率を裏付け、評価額を可視化
そして、不動産鑑定士の意見書を取得し、「物理的減価率は何%」「心理的抵抗による減価は何%」といった裏付け資料を作成すれば、買主さんの不安を減らし納得感に繋がります。
ステップ4:専門買取業者を含む複数社へ同条件で査定し比較
さらに、できれば3〜5社に同条件で査定依頼し、提示額や対応を比較検討します。特に、特殊事情に理解がある「お困り物件買取業者」は、査定額に大きな差が出ることも。
ステップ5:電磁界データや地役権契約書を提示し買主の心理的障壁を低減
さいごに、電磁界測定データなどの科学的根拠に基づく情報開示と併せて、電力会社との契約書、補償金の支払い証明などを提示することで、買主さんの心理的障壁を低減できます。
高圧線下の土地でも売却可能とする方法!
では、具体的にどのような売却方法があるか確認します。「高圧線下だから売れない」と決めつけることはありません!
①隣地所有者に売却する
最もスムーズな方法のひとつは、隣地所有者さんに交渉を持ちかけることです。すでに同じ送電線の影響下にあるため、心理的な抵抗感が少なく、土地の形状や利用価値が上がるため購入意欲が高い可能性があります。
ただし、隣地所有者さんとの関係性が良好であるとともに、ニーズがないと取引は成立しません。
②不動産仲介で売却する
また、一般的な方法として、不動産仲介業者に依頼し市場で売却する手段があります。広くアプローチすることで、高圧線下の土地でもそれほど気にしない買主さんを見つける率も高まります。
ただし、告知義務があるため高圧線の存在を隠せないため、人気がなく敬遠されるケースも多く、売却活動が長期化するリスクを考慮する必要があります。
③不動産買取で売却する
さいごに、不動産買取業者に直接売却する方法です。ノウハウや実績ある業者さんであれば、「現状のまま買い取ってもらえる」「契約後すぐに現金化できる」といったメリットがあります。
ただし、業者側は付加価値をつけて再販する目的であるため、多くは仲介より売却価格が低く提示されることになります。
とは言え、買取なら他にもメリット。
・契約不適合責任(売却後のトラブル)が免責となるケースが多い
・土地の引き渡しまでの流れが早く、費用も明確である
・心理的な交渉ストレスが少ない
高圧線下の土地は、たしかに通常の土地よりも売却が難しく、買主心理・法的制約・評価の不明瞭さといった複数の壁があります。しかし、状況を整理し、専門家の協力を得て適切な手順を踏めば、十分に売却することは可能です。
まとめ
今回の記事では、高圧線下の土地の定義や売却難航の理由から、少しでも高値で売るステップまで解説していきました。
はじめに、「高圧線」とは、「高い電圧の電気を送る電線」のことであり、「高圧線下の土地」とは、「送電線の垂線直下(真下に引いた直線)や離隔距離(電線と建物の最小距離)内にある土地」を指します。
送電線は、感電の恐れとともに、周囲に「電磁界」を発生させ、その「電磁波」が空間を伝播するため、電圧や状況に応じて建築不可エリアや離隔距離といった建築制限が生まれます。
この建築制限により、土地の評価額が下がる傾向があり、電力会社との間で「高圧線下地役権」を設定し、土地所有者さんに対して「対価補償金」が支払われることがあります。
その高圧線下の土地売却には、売却活動が難航する5つの理由があります。
①建築制限により需要が低くなりやすい
②市場相場よりも低い提示を受けやすい
③補償金に関する事情が値引き交渉の原因になる
④建築の自由度が低く融資審査も不利になる
⑤電磁波や騒音に対する心理的抵抗感が根強い
実害というよりも感情的・印象的な要因で価値が下がってしまうのも、高圧線下の土地の特徴です。
とは言え、活用のしづらさから高圧線下の土地を放置すると、さまざまな問題や思わぬリスクに発展します。
①固定資産税や維持管理費の負担が続く
②地役権が未登記のままだと交渉権を失う恐れがある
③契約関係の記録や事情説明が不十分になりやすい
このように、高圧線下の土地を放置していると将来的に対処が困難になります。そのため、少しでも早く現状を整理し、対策に踏み出すことが損失回避につながります。
一般的に高圧線下の土地は一律に評価できず、個別事情を考慮して「路線価地域・公示地価・財務省基準…など」のような基準を参考に査定しますが、これらには高圧線によるリスクが十分に反映されておらず、それぞれの業者さんの判断となりがちです。
そこで、評価時には「物理的減価・心理的減価」のような補正をします。しかし、現況・契約内容・地域の市場動向・心理的要因などを総合的に見た査定方法によっては数十%の差が出るため、複数社の意見を聞くのが得策です。
このように、高圧線下という不利な条件のある土地でも、少しでも高値の売却成功に近づくための5つのステップは以下。
ステップ1:登記簿と電力会社照会で建築制限面積・離隔距離を数値化
ステップ2:補償金の受領方法を整理し価格シミュレーションを作成
ステップ3:不動産鑑定士の意見書で減価率を裏付け、評価額を可視化
ステップ4:専門買取業者を含む複数社へ同条件で査定し比較
ステップ5:電磁界データや地役権契約書を提示し買主の心理的障壁を低減
では、高圧線下の土地の具体的な売却方法は以下。
①隣地所有者に売却する
②不動産仲介で売却する
③不動産買取で売却する
買取の利用は、業者側が付加価値をつけて再販する目的であるため、多くは仲介より売却価格が低くなりますが、ノウハウや実績ある業者さんであれば以下のようなメリットがあります。
・現状のまま買い取ってもらえる
・契約後すぐに現金化できる
・契約不適合責任が免責となるケースが多い
・土地の引き渡しまでの流れが早く、費用も明確である
・心理的な交渉ストレスが少ない
私たちエスエイアシストもそんな不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較していただければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。