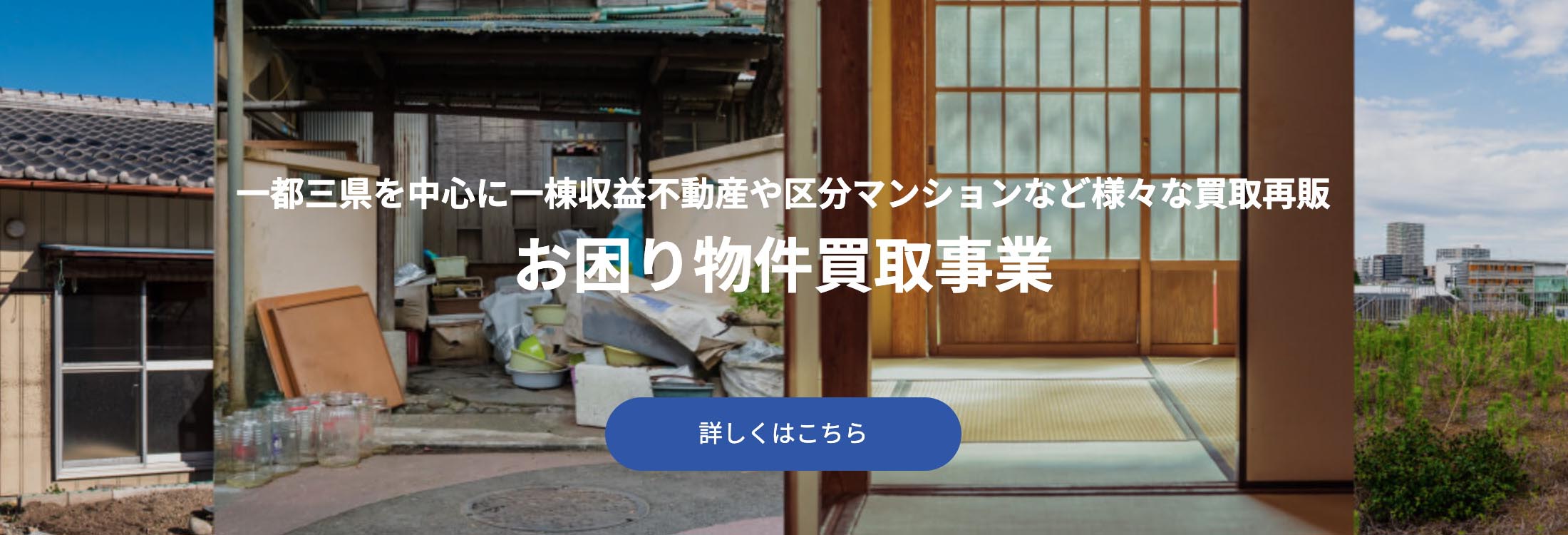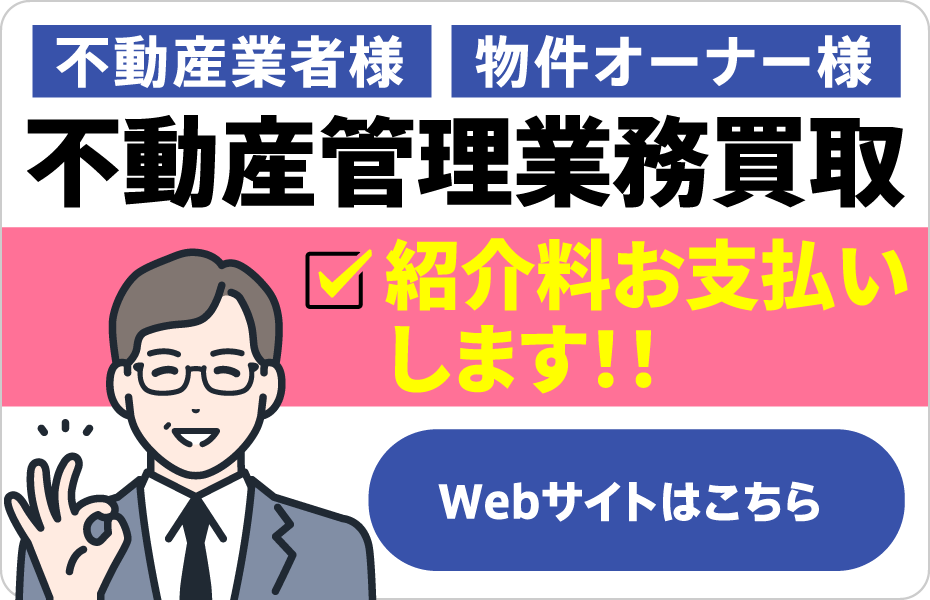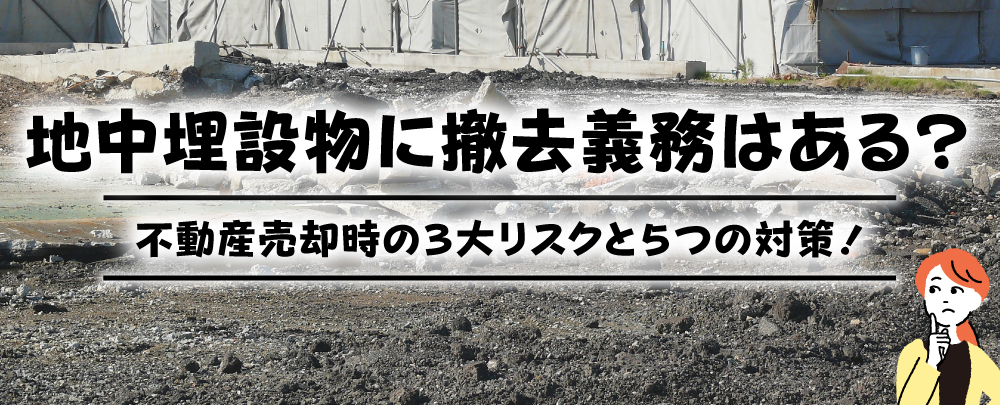
独自のノウハウにより入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”を解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシストがお届けする“お困り物件”コラム、第109回目は「地中埋設物の撤去義務」です。
相続した空き家のある土地を手放したいと考えたとき、もし売却後に「何か問題が見つかって責任を問われたらどうしよう…」といった不安はありませんか?表に見える問題なら、まだ対処もしやすいのかもしれません。でも、それが地中の見えない場所に眠っているとすれば厄介です。そもそも不動産売却時に「地中埋設物」の撤去義務はあるのでしょうか?
今回の記事では、土地売却の落とし穴である地中埋設物についてお話します。それが発覚したときの「高額な撤去費用」「損害賠償」「契約解除」という3大リスクと、売却で後悔しないための5つの対策を解説。まさに「転ばぬ先の杖」、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
地中埋設物に撤去義務はある?

はじめに「地中埋設物」とは、「土地の地中に埋まっている人工物や廃棄物」などのこと。既存の建物の構造物のみならず、過去の建物解体による残骸なども含まれ、具体的には以下のようなものです。
・建物のコンクリート殻(瓦礫・破片)
・古い浄化槽や排水設備
・古い井戸枠や井戸ポンプ
・金属くずやタイヤといった産業廃棄物
・隣地との共有設備(排水管など)や被越境物(隣地所有の基礎などがはみ出している)
多くは産業廃棄物の規制が緩かった昭和期に、処分費用や手間を省くために解体・建替時や造成時に埋め戻され、地中に隠されたもの。見た目にはわかりません。
その上で、押さえたいのが撤去義務の有無。「更地渡し」で売却する場合、売主さんは「地中の埋設物を除去した状態で引き渡すべき」と解釈されるのが一般的です。要するに、「地中埋設物の撤去義務は売主」となります。
たとえ契約書に記載がなくても、買主さんが家を建てるに困るほどの埋設物が出れば、契約不適合責任(契約内容に合わない場合に売主が負う責任)を問われ、撤去費用や損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、深く打ち込まれた杭など構造上・安全上、及び新たに新築するのに支障のないものは、買主の同意を得て残置することも可能です。その場合でも、重要事項説明と契約書に明確な記載をし、後の誤解を招かないようにしなくてはなりません。
「見えないから後回し」に潜む問題!
そんな地中埋設物、「目に見えない」「調査しづらい」ために後回し…、どころか「意識すらしていなかった」ケースもあります。特に相続で取得したような土地は、過去の工事記録や土地の利用履歴が残っていないことも多く、リスクを把握しにくいのが現実です。
そのため、正しく土地の状況を知るためには、地中埋設物の調査が必要です。しかし、この調査を省いて不動産売却してしまうと、以下のような問題が起きる可能性があります。
①新築工事中に発覚
まず、そもそも古家付きの土地として引き渡すとしても、建物を解体して引き渡すとしても、売主さん自身による調査は必須ではありません。しかし、新築工事において、安全な工事や建物の安全性を確保するために、一般的に買主さんは調査を行います。その際に、地中埋設物が発覚する可能性が高いです。
②買主の新築工事計画に影響
そうして、着工後に埋設物が発覚してしまうと、買主さんの新築工事計画に大きな影響を与えます。当然、工事は遅延し、費用も増大します。ほぼ間違いなくクレームになるでしょう。
③行政指導や工事の中止
万が一、地中埋設物が「廃棄物処理法(廃棄物を適正に処理し、生活環境保全と公衆衛生を向上させるための法律)」に違反するような産業廃棄物であった場合、行政から撤去命令や指導を受けることがあります。それは、ときに廃棄物が原因の土壌汚染の問題が発覚することも!
最悪の場合、撤去や土地の浄化が完了するまで土地が利用できなくなったり、工事自体の中止を余儀なくされることもあります。
これらは、国土交通省「不動産トラブル事例データベース」でも、地中埋設物関連の土地売買苦情について多く報告がされており、決して珍しいトラブルではありません。
地中埋設物が引き起こす3大リスク!
もう少し深掘りしてみましょう。もし、「不動産売却後に地中埋設物の事実が発覚したらどうなるか?」、それによって引き起こされる3大リスクは以下のようなものがあります。
①高額な撤去費用が発生
ひとつに、地中に残されたコンクリート殻や瓦礫、金属くずなどを取り除くには、重機による掘削・運搬・処分が必要です。撤去対象の量によっては、数十万円〜100万円以上の高額な撤去費用が発生することもあります。とくに地盤が弱いエリアでは、撤去後に地盤調査や補強工事が必要になることもあり、思った以上に出費が膨らむリスクがあります。
②契約不適合責任による賠償を求められる
それだけの想定していなかった費用が発生すれば、契約不適合責任による賠償を求められる可能性があります。たとえ売主さんが「知らなかった」としても、契約書上に「更地渡し」と書かれていれば、撤去費用を負担させられたり、場合によっては損害賠償請求や価格の減額交渉につながることもあります。
たとえ、古家付きの土地として売却したとしても、「契約書に免責条項がない」「売主が埋設物の存在を知っていた」場合、その責任から免れるワケではありません。もしその際に、買主さんとの信頼関係が悪化するようなことがあれば、話し合いだけで済まず弁護士を立てた法的対応になることも考えられます。
③契約解除に伴う負担
そうして最悪の結果ですが、新築工事に支障をきたすほどの埋設物の場合、買主さんが契約解除を申し出るケースがあります。その場合は、手付金の返還に加えて、買主さんが負担した設計費用や仮住まい費用を請求される可能性も!
また、工事が進んでいた場合には違約金の問題に発展するケースもあり、売主さんとしては金銭的にも精神的にも大きな負担を背負うことになります。
リスクを減らす5つの対策!

この3大リスク、「決して軽視できるものではない!」と思いませんか?ただ、それも適切な確認と契約時の工夫で大幅に軽減できます。以下に示す「リスクを減らす5つの対策」を組み合わせて対応しましょう!
①地歴調査で過去の土地状況を判断
かつてその土地がどのように使われていたかによって、地中埋設物の存在の可能性が高まる傾向があります。たとえば、以下のような用途の土地では埋設物のリスクが高くなります。
・工場跡地や倉庫用地として使われていた
・建物の建替えが何度も行われていた
・長年空き地だった(不法投棄されている可能性)
「地歴調査」では、土地の過去の利用状況を古地図・航空写真・旧土地台帳・登記簿などから調べ、地中に埋設物が残されている可能性を判断します。これは、インターネット上で公開されている古地図や自治体が保管している資料なども利用できるため、比較的手軽にリスクの初期把握ができる方法です。
②地中レーダー調査と試掘で現状を確認
ただし、地歴調査だけでは「実際に埋まっているか」は分かりません。地歴調査でリスクが疑われる場合や、実際の売却を見据えてより正確な情報が必要なときは、現地での物理的な調査が有効です。具体的には以下の3つの方法があります。
・地中レーダー調査:電磁波を使って地面の中の異物を探知する非破壊調査
・試掘(しっくつ)調査:実際にショベルなどで数カ所を掘り目視で確認する調査
・ボーリング調査:直径5〜10cm程度の穴を掘り、地中深くの地盤構成をサンプルリングして調査
費用の目安としては、内容によって10〜50万円前後かかりますが、万が一トラブルが発生してからの撤去費や損害賠償を考えると、事前投資として非常に効果的な対策です。
③契約書で責任範囲を明確化
そして、地中埋設物のトラブルの多くは、契約時に責任の所在が曖昧なことから発生します。そのため、契約書での事前の取り決め…、特に次の2点を明記することで、後から責任を問われる可能性を大きく下げられます。
・現況有姿(ありのままの状態)での引き渡し
・地中埋設物に関する免責事項
具体的には、「本物件は現況有姿で引き渡すものとし、地中埋設物の存在について売主は一切の責任を負わない」とすれば、契約不適合責任の範囲を制限することができます。なお、重要事項説明書にも同様に明記し、買主さんに口頭でも説明を行うことも大切です。
④瑕疵保険の活用
さらに、売主個人でも宅建業者を通じて条件が整えば、瑕疵(かし)保険に加入できることがあります。これは、売却後に買主さんから「隠れた瑕疵」を指摘されたときに、修理費用や撤去費用の補償が受けられる制度です。
この中に「埋没物対応特約」を付けることで、地中に不測の埋設物があった場合でも、より双方に安心感が得られます。これには、単にトラブルを防ぐだけでなく売却活動を円滑に進める要素にもなります。
⑤撤去費用を経費計上して税負担を軽減
さいごに、もし地中埋設物の撤去が必要になった場合、その費用はただの出費ではなく、撤去費用を経費として計上、税負担を軽減できる可能性があります。注意点としては、売却契約前後など合理的な時期に支出した場合に限られます。
具体的には、土地の売却時に発生した撤去費用を「譲渡費用」として、譲渡所得から控除します。これにより、不動産売却益にかかる所得税・住民税を節税できるのです。そのためには、支払い証明や領収書・明細書などを保存した上、できるだけ早く専門家に相談し、確定申告の準備を整えておくことをおすすめします。
補足として、発覚した地中埋設物が、隣地からの被越境物(建物の基礎や共有給排水管など)の場合は、単独で撤去を進めると隣地所有者の権利を侵害するおそれがあります。
・越境物や共有物の範囲を測量で確定
・隣地所有者と協議し文書(覚書)で合意内容を残す
・必要に応じて弁護士や土地家屋調査士に介入してもらう
という手順を踏み、後々の責任関係をクリアにしておきましょう。
地中埋設物のある土地は不安なく売却できる?
とは言え、これらの対策をするには、手間も費用もそれなりにかかってしまうワケです。地中埋設物があることが発覚した土地を、不安なく売却するにはどうすればよいでしょうか?
そもそも一般的な土地を売る方法は「仲介」と「買取」の2つ。
通常であれば、不動産仲介なら市場価格相場で売却できます。ただ、地中埋設物のある土地においてはその反面で…、
・更地渡しなら売主が撤去
・買主が撤去するなら値下げ交渉に応じざるを得ない
・問題には告知義務があるので売却活動は苦戦と長期化
・契約不適合責任は原則発生する
というコトになります。
一方で、不動産買取によって売却すると、市場相場よりも価格は低くなることが多いです。これは、買取業者さんはその土地に付加価値をつけて売却して利益を出していくため、仕組み上仕方ありません。
ただ、地中埋設物のある土地においては以下のようなメリットがあります。
・撤去や解体をしない「現況のまま売却」できる
・不動産業者相手の取引で「契約不適合責任を免責」しやすい
・交渉の手間が少なく「現金化が早い」
・直接取引のため「仲介手数料が不要」で「確実な引き渡し」ができる
・売却後の「追加費用リスクは業者が引き受け」て貰える
「調査や交渉に時間をかけられない」「早く現金化したい」という場合は、不動産買取が現実的な選択肢です。責任の所在が明確になるため、売却後の心配も大幅に減らせます。
まとめ
今回の記事では、不動産売却で地中埋設物が発覚したときの3大リスクと、5つの対策を解説してきました。
「地中埋設物」とは、「土地の地中に埋まっている人工物や廃棄物」などのこと。既存の建物の構造物のみならず、過去の建物解体による残骸なども含まれ、多くは処分費用や手間を省くために地中に隠されたもので、見た目にはわかりません。そして「更地渡し」の場合、「地中埋設物の撤去義務は売主」となります。
たとえ契約書に記載がなくても、契約不適合責任を問われ、撤去費用や損害賠償を請求される可能性があります。
「目に見えない」「調査しづらい」ために後回しになりがちで、特に相続で取得したような土地はリスクを把握しにくいため、地中埋設物の調査が必要です。この調査を省いて不動産売却してしまうと、以下のような問題が起きる可能性があります。
①新築工事中に発覚
②買主の新築工事計画に影響
③行政指導や工事の中止
これらは、国土交通省「不動産トラブル事例データベース」でも報告がされ、決して珍しいトラブルではありません。
不動産売却後に地中埋設物が発覚することによって引き起こされる3大リスクは以下。
①高額な撤去費用が発生
②契約不適合責任による賠償を求められる
③契約解除に伴う負担
この3大リスクも、リスクを減らす5つの対策をすることが大切です。
①地歴調査で過去の土地状況を判断
②地中レーダー調査と試掘で現状を確認
③契約書で責任範囲を明確化
④瑕疵保険の活用
⑤撤去費用を経費計上して税負担を軽減
補足として、発覚した地中埋設物が隣地からの被越境物の場合は、単独で撤去を進めると隣地所有者の権利を侵害するおそれがあるので注意が必要です。
一般的な土地を売る方法は「仲介」と「買取」の2つ。
通常であれば、不動産仲介なら市場価格相場で売却できますが、「更地渡しなら売主が撤去・値下げ交渉に応じざるを得ない・告知義務で売却活動は長期化・契約不適合責任は原則発生」があり、手間も時間も心理的負担も大きいです。
一方で、不動産買取によって売却すると、市場相場よりも価格は低くなることが多いですが、地中埋設物のある土地においては以下のようなメリットがあります。
・現況のまま売却
・契約不適合責任を免責しやすい
・現金化が早い
・仲介手数料が不要で確実な引き渡し
・追加費用リスクは業者が引き受け
「調査や交渉に時間をかけられない」「早く現金化したい」という場合は、不動産買取が現実的な選択肢です。責任の所在が明確になるため、売却後の心配も大幅に減らせます。
私たちエスエイアシストも不動産買取業者のひとつです。入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、困ってしまう“訳あり物件”のご相談を数々と解決してきた実績があります。ぜひ他社さんと比較して頂ければと思います。難しい物件をお持ちでお困りの方は、一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。