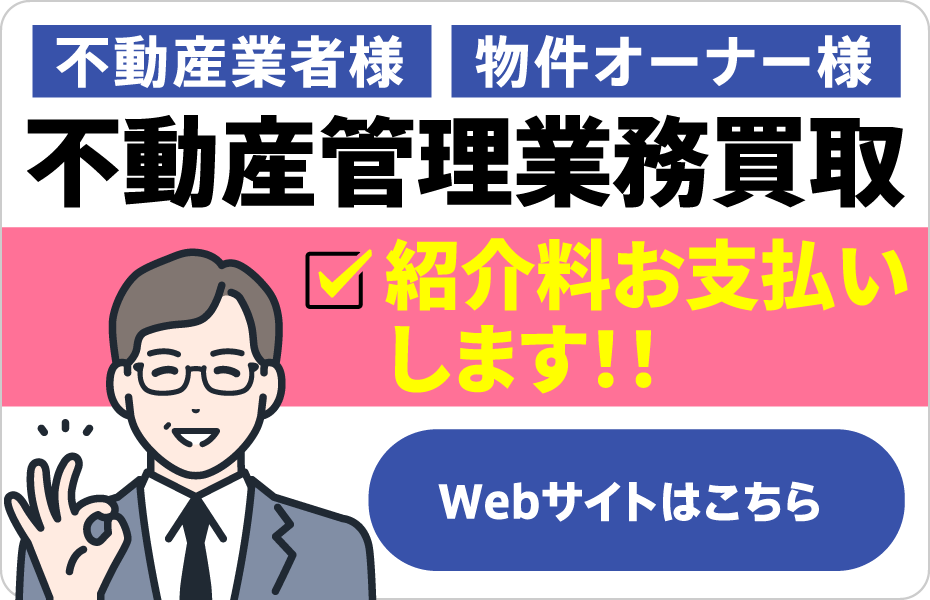独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!今回は2025年4月に改正された4号特例による影響について解説します。
4号特例とは?
そもそも4号特例とは4号建築物を対象とした緩和措置です。「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する下記条件の建築物において建築確認の審査の一部を省略できるようになっていました。
・木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
・非木造:「平家」かつ「延べ面積200平方メートル以下」
建築確認の審査とは建築基準法で定められているもので、建築工事に着手する前に住宅の新築や増改築の際に自治体または指定確認検査機関に申請書類を提出しなければなりません。
4号特例の内容
4号特例により建築確認や検査、審査などを一部省略することができますが、提供される建築物は建築士が設計したものでなければなりません。具体的には「建築設備の構造強度」や「居室の採光」、「換気設備の技術基準」、「地階における住宅等の居室」、「電気設備」、「天井、廊下、床高、除湿、遮音」といった審査項目の一部が対象外となったり、住宅の機能や安全性を示す構造計算書を提出する必要がないといったものになりますが、4号特例の改正によりこれらの審査や書類の提出が必要となります。
4号特例縮小の背景
4号特例の縮小背景は主に2つあり、建築物省エネ法の改正により2025年4月から原則すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務づけられることになりました。「延べ面積200平方メートル以下の平屋」は省エネ適合性審査が省略されるため、これに合わせる形で4号特例を縮小し、審査対象の統一がされることになりました。
①住宅の省エネ促進
4号特例の縮小は2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みに伴い、省エネ基準の適合が求められ、住宅の省エネ化を促進するために施行されます。建築確認申請が免除された状態では省エネ基準への適合チェックが十分に行えないことから見直しが必要となりました。
②住宅の安全性向上
4号特例の縮小は住宅の倒壊を防ぐことも目的としています。建築において断熱材の使用や設備の搭載により住宅の重量増加に見合う強度が必要とされています。重量のある住宅において自然災害で倒壊するリスクもあるため、適切な強度を持つ建築物の設計・施工が重要となります。1988年に建築基準法が改正されて建築確認・検査が民間に解放されました。その結果、建築確認の実施率は向上した一方で、4号特例を悪用し強度が不足した建築物も見られるようになりました。重大な構造瑕疵を責任追及する際、提出する資料がなければ被害が立証できないことからも見直しが必要となりました。
建築基準法改正により変わること
建築基準法の改正により建物の分類が変わり、4号建築物が廃止となり、建築物の分類が1号~3号になります。現行の4号建築物は、新2号建築物と新3号建築物に分類され、新3号建築物のみ引き続き審査省略制度の対象となります。新2号建築物は木造・非木造は問わず「2階建て以上」または「延べ面積200㎡超」の建築物に分類され、新3号建築物は「延べ面積200㎡以下の平屋」となります。要するに2階建て以上の住宅は新2号建築物に分類され、審査省略制度の対象外となります。また、建築確認が必要な工事は新築だけでなく、増改築や大規模な修繕といったリフォームなども含まれることになります。
まとめ
今回の記事では建築基準法改正にともなう4号特例の縮小について解説してきました。4号特例の縮小にともない、今までとリフォームなどにおける審査制度も変わるため建築物によっては一般の不動産業者に依頼しても売却できない場合が多いです。専門の買取業者であれば買取できることもあるため、専門の買取業者に依頼することも検討してみてください。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!